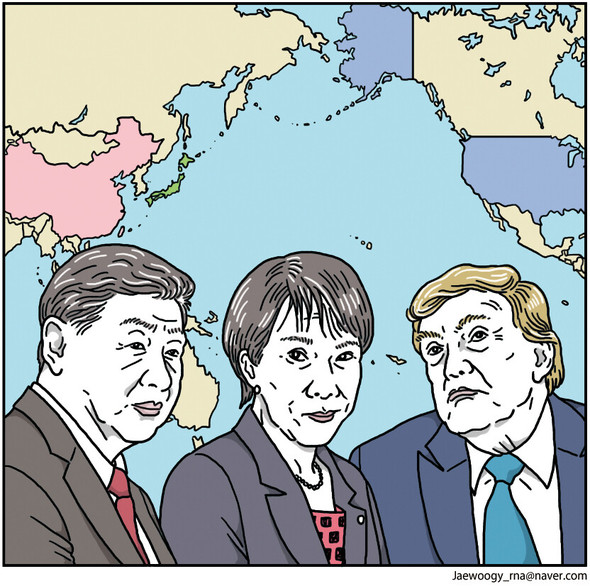[コラム]アフガンの今――「歴史の終わり」という巨大な叙事の虚構性

フランシス・フクヤマが代表作『歴史の終わり』を出版したのは、ソビエト連邦が解体されて1年が経った1992年だ。彼は1989年秋のベルリンの壁の崩壊を目撃した後、米国の外交専門誌「ナショナル・インタレスト」に同名の論文を寄稿し、地球的センセーションを巻き起こした。
フクヤマが述べた「終わり」は破滅や没落とはかけ離れている。キリスト教の終末が「人類の救援」という神的摂理の実現であるように、彼の言う「歴史の終わり」も理性のいたずらに導かれてきた人類史が最終的に完成態に達したという肯定の意味が強かった。ヘーゲル主義者のフクヤマが見たところ、世界史とは「自由の実現」という目的へと向かう進歩の過程だが、その動きを後押しするのが世界内部に存在する矛盾と対立だ。こうした点から、自由民主主義と敵対・競争してきた社会主義の没落は、世界史が進歩の終着地に達したことを告げる事件にほかならなかったのだ。
フクヤマに「歴史の終わり」を確信させたソビエト連邦の解体から今年でちょうど30年経った。1991年8月の保守派によるクーデターが拍車をかけた連邦の崩壊により、社会主義はオルタナティブな体制としての地位を失い、資本主義・自由主義に対する批判イデオロギーの次元にまで縮小した。しかし「終わり以降」に繰り広げられた世界史もまた、自由の拡大というフクヤマの予言とは程遠い。自由化・民主化の入り口に差し掛かったと思われた非西欧圏の多くの国々が「再権威主義化」という逆行に直面している。イスラム圏では左右の理念対立を世俗主義と宗教的原理主義の対決が代替し、内戦と追放、大量虐殺の地獄絵図が繰り広げられる。
このような中、米国がテロ根絶と自由民主主義体制の移植のために莫大な資金と軍事力を投じたアフガニスタンが20年ぶりにタリバンの手中に落ちたことは、何かの徴候のように思われてならない。それ自体が、歴史の終わりという巨大な叙事の虚構性を暴き出すだけでなく、女性と子ども、人種・宗教的少数派など、世界各地の弱者集団にとっては依然として一日一日の日常が「災厄」であり「破局」に近いということを悟らせる。アフガン親西欧政権が迎えた「最後の日」が、残酷な「報復と審判の日」にならないよう、歴史を司る神がいるのなら、どうか再臨してくれることを祈るのみだ。
訳D.K