[私の書斎の中の古典] 美感を楽しめる時間はオレンジの香りほどにも長くない

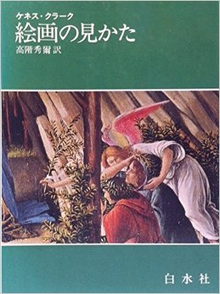
ケネス・クラーク『絵画の見かた』(高階秀爾訳、白水社)
Kenneth Clark: LookingatPictures,JohnMurray,London,1960
およそ30年前から現在まで、私は世界各地の美術館や聖堂で美術作品を見てまわった。今年の早春にもイタリアに出かけ、たくさんの美術を見てきた。初めて見たものもあり、いままでに何度も見たものもあるが、その度に新しい発見と感動があり、興趣が尽きない。…と、こんなふうに書いてみても、もどかしさばかりを感じる。「発見」「感動」「興趣」、こんな言葉では、実際には何も伝えられないと思うからである。このように、視覚芸術である美術について、その面白さを言葉で表現することには固有の困難さがあるようだ。私は美術について何かを書くとき、つねにこの困難さを感じてきた。
美術に関する書籍にもかなり親しんできた。もちろん貴重な情報を得たし多くを学んだが、本として面白く読んだと言えるものは多くない。ヴァン・ゴッホ書簡集やコレクターであるペギー・グッゲンハイムの自伝は、稀な例外である(この2点については、いずれこの欄で取り上げたい)。だが、これらは美術作品そのものの面白さを伝えるというより、むしろ画家やコレクターの人物像の面白さを伝えるものといえる。学者や評論家の書いたものに面白いものは少ない。そんななかで、過去30年間、私が繰り返し手に取り、読むたびに論旨に納得し、筆致に感嘆して、できることなら自分もこんなふうに書きたいものだと羨望しているのが、ケネス・クラークの本書である。本書の美点は、なによりも平明でありつつ洗練され、奥行きの深いその語り口にある。
「これはいわば二度蒸留された芸術作品である。人物たちは、ここに描かれる前にすでに芸術となっていたように思われる。」
15世紀フランドルの画家ロヒール・ファン・デル・ウェイデンの大作「十字架降下」についての1章は、このように書き起こされる。この出だしの1行から、私は、「ああ、そうだ。自分の言いたかったこともこういうことだった」と直感し、マドリードのプラド美術館でこの作品の前に立った時に自分の中で起こった心の動きを呼び起されて、喜びのうちにその先を読み進めていくことになる。
十字架から降ろされるイエス・キリストの以外の下方に、悲嘆のあまり地に倒れようとする聖母マリアの姿について、ケネス・クラークはこう記述する。
「そこでは真実のほんの些細な一片すら無視されてはおらず、あらゆる細部は二重の意味をもっている。聖母の顔を流れ落ちる涙は、その動きによって、顔の肉付けの感じをいっそう強調している。一つ一つの筆の跡の背後に見られる不撓の意志の力は、ほとんど彫刻師のそれを思わせるが、しかしその筆の動きを辿っていくうちに、人は、それが技術的な確実さの結果ではなく、道徳的な確信の結果であることに気づく。」
この奇跡のような作品が、画家の「道徳的な確信の結果」であるかどうか、私にはわからない(誰にそれがわかるというのか?)。だが、作品そのものから与えられる感銘と、この語り口との相乗効果によって、「いかにも、そうだろうな」と納得させられるのである。
「最後に、私は彼女(聖母)の手を見つめる。それぞれの手はそれぞれに美しいばかりではなく、身体の他の部分との関係において、共感させるものをもっている。力なく垂れながら、しかもなお生きているその左手は、すでに生命を失ったキリストの右手と並び、髑髏と聖ヨハネの精妙な足とのあいだにある右手は、大地から何か新しい生命を抽き出そうとしているかのようだ。」
このような著者の記述に導かれて、私は再び作品の細部に目を凝らし、「なるほど…」とため息をつくのである。本書には、ティツィアーノ「キリストの埋葬」に始まり、ベラスケス「宮廷の侍女たち」、フェルメール「アトリエの画家」、ボティチェッリ「神秘の降誕」など、16点の絵画が取り上げられている。著者のケネス・クラークはロンドンのナショナル・ギャラリー館長、オクスフォード大学教授などを歴任した、この分野の巨人といえる美術評論家である。BBCで放映されたテレビ番組「芸術と文明」シリーズと、その番組を1巻にまとめた同名の著書によって国際的に知られている。本書「絵画の見かた」は、もともとイギリスの新聞「サンデー・タイムス」に連載された。日本語版訳者の高階秀爾は「すぐれた美の享受者」「博識の専門家」そして「啓蒙的情熱に支えられた解説者」という3要素が、著者において見事に統一されていると述べているが、そのとおりだと思う。この3要素のどれかが欠けるか、どれかに偏っていたら本書の魅力は半減していただろう。
著者は序文で述べている。「最初にまず私は、絵を一個の全体として見る。その主題が何であるかを認めるよりもずっと前に、私は全般的な印象というものにうたれる。」それから細部に目をやり、綿密な検討に移る。すぐに「批評的能力」が活動を再開する。その作業を続けるうちに感覚が疲労を感じ始める。「私の考えでは、純粋に美的な感覚(と呼ばれるもの)を楽しむことのできる時間は、オレンジの香りを楽しむ時間より長くはない。」
この「オレンジの香り」というあたりの記述に、読者である私は「うーむ、上手いな」と感心する。著者はさらに述べる。「だが、偉大な芸術作品は、もっと長いこと、注意して眺めなくてはならない。」関心の重点が「歴史的批評」へと受け継がれ、画家の生涯の諸事実を思い出しながら目の前の作品をその発展の中に位置づけよう」と試みることになる。すると、一度は疲労していた「受容力」が再び回復してくるというのである。このような美的感覚による直感的受容と知的な批評との反復運動が、すなわち著者の推奨する「絵画の見かた」である。どちらか一方だけでは足りない。著者は「偉大な作品は底知れぬ深さをもっている」と述べ、こう付け加えることも忘れない。「私は使い古された言葉という道具でその表面をほんのわずかばかり引っかいたにすぎない。というのは、知覚能力の限界にさらに加えて、視覚体験を言語に移し変える困難というものがあるからだ。」日ごろ私が感じているのと同じもどかしさを、ケネス・クラークほどの人物でも感じているということだろうか。

ゴヤ「1808年5月3日」に関する本書の記述は、若い日の私に大きな励ましと霊感を与えた。スペインに侵攻したナポレオン軍による民衆虐殺行為を描いたこの絵を、私は30年前、プラド美術館で見た。名状しがたい厳粛な思いに満たされ、当時の私の所持金からすればかなり高価なその複製画を購入して日本に持ち帰った。それから5,6年後、長く獄中にあった兄たちのうちひとりが17年ぶりに出獄し、彼と再会するため私は日本からソウルに向かった時、兄への土産に持参したのが、その複製画である。金浦空港の税関で機関員らしい人物がこの絵を問題視し、「ソ連の絵か?」と私に執拗に尋問したことを忘れない。
ゴヤからおよそ半世紀後、マネがこの作品の構図を借りて「皇帝マクシミリアンの処刑」を描いた。本書の著者は、マネは偉大な画家であったと述べた上で、こう続けている。「マルクス主義的用語は普通には批評の妨げとなるものであるが、しかし、このマネの絵を眺めていると、私はブルジョアという言葉を使わないわけにはいかない。彼(マネ)の眼は何ものにも捉われていなかったが、彼の心は、パリの社会の上層中産階級の価値観に支配されていた。それに対し、ゴヤは生涯にわたって宮廷画家として勤めたにもかかわらず、常に革命的であった。彼は、僧侶、兵士、官僚その他どのような形式にせよ、権威というものを憎悪した。彼らは機会さえあれば、無力な人々を搾り上げ、力によって押さえこもうとするものであることを、彼は知っていた。(中略)不幸なことに社会的憤激は、他の抽象的な情動と同じく、本来芸術を生み出す力とはなりにくい。したがってまた、ゴヤのように天賦の才を一つにあわせもった場合は、歴史上きわめて稀である。(中略)ゴヤの閃光に照らし出された眼と、それに応ずる手とは、すべての点において、彼の憤激と一つのものだったのである。」
このケネス・クラークの言葉から、私は励ましを得た。最良の芸術に見合った最良の語り、たんに知的なだけではないその言葉によって、私は、自分の社会的立場についてだけではなく、自分の美的感覚にも自信を与えられたのである。
本書の末尾はレンブラント「自画像」に関する章である。「われわれは、顔の一本一本の皺の正確な形と色合いが人間の体験と結びついているということを知らない。われわれは多少の弁解と希望的な美化なしに自分自身を受け入れることはできないのである。それに対し、レンブラントの自画像は、後世に遺された最も偉大な自伝である。」このように書き始められた最終章は、次のような印象的な言葉で結ばれる。

「その赤い絵具を叩きつけたような鼻は、あまりにも尊大であるので、ほとんど笑いを誘うほどのものであるが、しかし、だからといって、体験が芸術に変貌するその魔術に人は畏れを感じないわけにはいかない。あの赤い鼻によって、私は激しく叱責されているように感ずる。突如私は、自分の道徳性の浅薄さや、自分自身の共感の狭さや、自分の職業の空しさを思い知らされる。レンブラントの巨大な天才のもつ謙虚さは、美術史家に沈黙するように警告するのである。」
何と見事な結語だろう。私はまだこれからも美術について語ったり、書いたりするだろうが、ケネス・クラークのようにできるだろうか? その鍵は「謙虚」ということかもしれない。
徐京植(ソ・ギョンシク)東京経済大学教授
(4214字)

