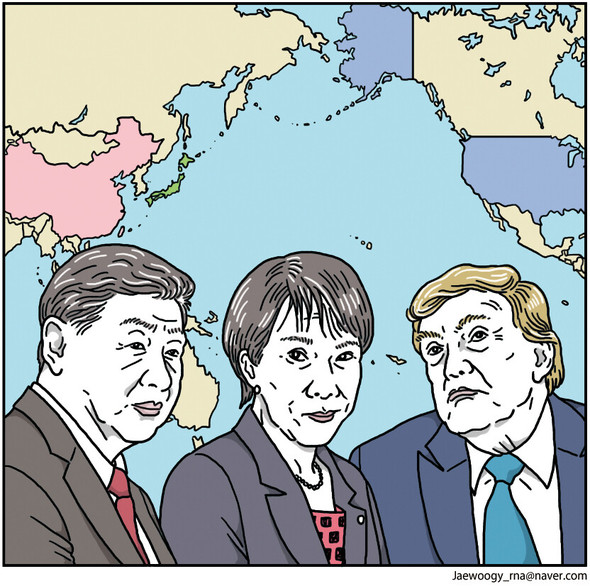政府の“お飾り”になることへの懸念強まり、タブー視
キム委員長、復元への強い意志示したが
組合員らを説得する過程で限界が露呈
強硬派「非正規・特雇労働者の保護対策ない」

「新型コロナで労使共に苦しんでおり、政府もこの状況を収拾しなければならないためやむなく集まったが、極めて低いレベル以上の合意は難しいだろう。しかも民主労総の中には政労使対話という枠組み自体をドグマ(独断的な信念)的に嫌う雰囲気が一種の遺産のように残っており、容易ではないと思う」
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)克服のための政労使代表者会議が発足した直後の今年5月中旬、全国民主労働組合総連盟(民主労総)出身のある関係者はこのように予想した。一縷の期待もないこの否定的な見通しは、今月1日、民主労総の強硬派の反発で最終合意案署名まであと15分という時点で現実として立証された。民主労総はなぜ“行き詰まりの道”を選んだのか。
通貨危機直後の1998年、当時ペ・ソクポム民主労総委員長職務代行は金大中(キム・デジュン)政府の政労使委員会に参加し、「経済危機克服に向けた社会協約」を結んだ後、内部の反発で辞任した。全教組の合法化と医療保険統合などの成果は得たが、内部では整理解雇の要件緩和と派遣法の施行などに合意したことが問題視された。そのため、政労使委員会から脱退した民主労総では、「政労使対話」は絶対にその名前を口にしてはいけない「ハリー・ポッター」シリーズの悪党「ヴォルデモート」のように、タブーとなった。政労使対話への参加を、政府の“お飾り”になることだと見なすようになったのだ。第3労総をつくることを試みるなど政権レベルで民主労総を敵対視した李明博(イ・ミョンバク)、朴槿恵(パク・クネ)政府を経て、政労使対話よりも対政府闘争を優先視するこのようなムードはいっそう強化された。
文在寅(ムン・ジェイン)政府が発足した2017年の民主労総委員長選挙でキム・ミョンファン当時候補は「孤立、分裂、無能を越えて新しい30年を開拓する民主労総」を強調し、政労使対話の復元を公約に掲げた。強硬闘争一辺倒という民主労総のイメージから脱し、社会的対話を通じて政府と経営界を相手に「集団的交渉の枠組み」を作るという構想だった。形式的には産別労組だが企業別労組の枠にとどまっている韓国労働組合と交渉の形態を発展させたいという労働運動家としての希望もあったというのが、側近たちの説明だ。しかし、キム委員長自身が議論の当事者だった大統領直属の経済社会労働委員会への参加が昨年1月に代議員大会で否決されたことで、ブレーキがかかった。
にもかかわらず、キム委員長が新型コロナ克服のための政労使対話を提案し、民主労総内部でこれを受け入れたのは、それだけ解雇などの問題が深刻になっているという危機意識のためだった。新型コロナという全国的な感染症問題で雇用危機に直面した労働者の要求を、“現場闘争”では貫けないという判断も動力となった。今回の暫定合意に反対する産別・地域支部の代表者も、4月16日に中央執行委員会で社会的対話推進の決定に同意した。

民主労総内部の政派的利害関係を除き、暫定合意に反対する最大の理由は、解雇禁止のような労働者保護対策が明示されていないからだ。公共運輸労組側のある関係者は、「航空産業に8兆ウォン(約7200億円)の資金をつぎ込んだにもかかわらず、(アシアナ航空の下請け業者の)アシアナKOでは集団解雇が発生した。8兆ウォンは大韓航空、アシアナ航空の株式をすべて購入できる金額なのに、国民の税金でそのような支援をしながらなぜ解雇は防げないのか」とし、「このような抽象的なレベルの合意は、企業が経済的な困難を訴えて合意を守らなければそれまでで、労働者にとってはむしろ足かせになる」と厳しく批判した。
非正規労働者組織では、企業経営と正社員に焦点が当てられているだけで、非正規労働者や雇用保険外の特殊形態労働者などの雇用・生計安定対策はこの暫定合意案に含まれていないと指摘する。「非正規職はもうやめよう1100万非正規労働者共同闘争」は、正社員90%の雇用を維持する条件で企業に40兆ウォン(3兆6千億円)規模の基幹産業安定基金を支給する方針なのに、非正規労働者と解雇の可能性のある正社員10%の雇用安定対策がないことや、全国民雇用保険拡大案に含まれる特殊形態労働者は法に規定された77万人だけで、残り143万人などの対策がないことなどを挙げ、暫定合意案の破棄を求めた。
一部では、新型コロナを契機に社会的対話を提案した執行部が、「最終目標」よりは政府との対話そのものに盲目的にこだわった限界が露呈したと指摘する。政労使の合意成立を重視するあまり、組織内の社会的対話反対論者をはじめ、3年前の選挙当時、現執行部を支持した組合員たちに今回の合意の必要性を説明して同意を得るのに失敗したということだ。ある労働界の関係者は、「執行部は労働界が一部譲ることで得るものがあると判断したようだが、反対の立場では“政治的宣言”に過ぎない合意であり、決して受け入れられなかっただろう」と話した。
このような要求が行き過ぎだという批判もある。パク・ジョンファン・サービス連盟政策局長は最近、フェイスブックに「各産別連盟と地域本部の政策担当者会議、中央執行委など関連会議が週1回以上開かれたのに、コミュニケーションが足りなかったというのは話にならない」とし、「統一主体国民会議のようにすべてを決める社会的対話は世界中どこにもない。政労使の代表者が方向を決めれば、それを履行する主体の努力がより重要だ」と指摘した。
訳H.J