(2)職場内の威力
完璧に近い「純粋さ」を求めて
加害者を擁護し、言い訳に悪用
事件当時、極度の恐怖は当然なのに
勇気ある対応に対して「平然としている」とみなす
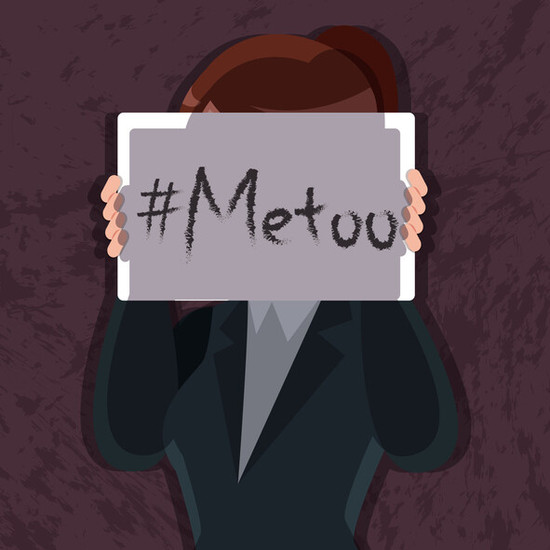
性暴力被害者は被害事実に加え、「被害者らしさ」に対する偏見とも向き合わなければならない。加害者を擁護する側は、たびたび被害者に完璧に近い純粋さと道徳性を要求し、一部メディアの報道は性暴力犯罪の深刻性を強調するための「スケープゴート」として被害者のか弱い姿ばかりを扱う。
威力による性暴力の被害者は「被害者らしさ」を徹底的に検証される。2014年に国家機関の内部で強制わいせつ事件が発生した際、被害者について内部関係者は「あの子はそんなに純粋な被害者ではない」「別の組織に移りたくて性暴力問題を提起した」と述べ、加害者を擁護した。その後、当該事件の加害者は有罪確定の判決を受けた。
アン・ヒジョン前忠清南道知事やパク・ウォンスン前ソウル市長の例も、アン前知事の性的暴行を告発したキム・ジウンさんは著書『キム・ジウンです』で「アン・ヒジョンの家族は、私に関する情報“収集”のために過去の恋愛歴や普段の行動を収集した。アン・ヒジョンの周囲の人々が準備し始めたその話の中で、私は異常で問題のある女性になった」と書いた。アン前知事側の戦略どおり、一審はキム・ジウンさんの「被害者らしさ」に集中した。「被告人が好きなスンドゥブ(おぼろ豆腐の鍋)屋を懸命に探したこと」などを挙げ、キムさんに対して「被害者らしくない」と判断した。最近、パク前市長の周辺でも被害者の告白の“真偽”を疑う声が出ている。
被害者が権力関係を意識して事件直後に被害を訴えることが困難だという事実は、かえって加害者の言い訳に利用されることもある。アン前知事は裁判の過程で、キム・ジウンさんとやり取りしたショートメールや写真などを証拠として提出し、これは「性的暴行の被害者なら見られない姿」だと主張した。昨年、国家人権委員会が発行したセクハラ是正勧告の事例集を見ると、従業員に対しセクハラ・わいせつ行為を行った事業主が「(身体接触直後に)謝罪したところ、被害者も大丈夫だと答えた」「被害者はむしろ私のそばで愛嬌を振りまいた」と被害陳情を否定するケースもあった。
「だめです、いやです」と大声を上げるなど、被害者なら当然「激しい抵抗」に出なければならないという先入観も、被害状況と脈絡を十分に考慮していないといえる。実際、性暴力被害者らは事件発生当時、極度の恐怖や戸惑いのため、どんな対応も取れないケースが多い。昨年、女性家族部が実施した「性暴力安全実態調査」では、回答者1万106人のうち13.5%ほどが性暴力の被害を受けた当時、すぐに対応できなかったと答えた。女性回答者は、「どうすればよいのか分からず」(44.0%)、「性暴力なのか分からず」(23.9%)、「どんな行動をしても無駄なような気がして」(18.5%)、「恐怖心に体が固まって」(11.1%)対応できなかったと答えた。
被害者の積極的で勇気ある対応が、かえって被害を訴えた真正性を疑われる契機となったりもする。2015年、韓国性暴力相談所付設研究所「ウリム」が公開したケースによると、大学生のMさんはサークルの会長に準強姦の被害を受けた後、自分の息の音すら耐えられないほどの後遺症を患ったが、「加害者よりもちゃんと暮らすのが真の復讐」という思いから、淡々としているように振舞って学校生活を続けた。これは、加害者がその後学校レベルの性的暴力の解決過程で、Mさんの「被害者らしさ」を指摘する口実となった。社会運動団体の先輩に強姦されそうになった被害者が現場を抜け出す過程で、防犯カメラの前でかばんの中をさぐるなど、「あまりに平然とした姿」が映ったという理由から、構成員たちが加害者を擁護したという事例もあった。
訳C.M

