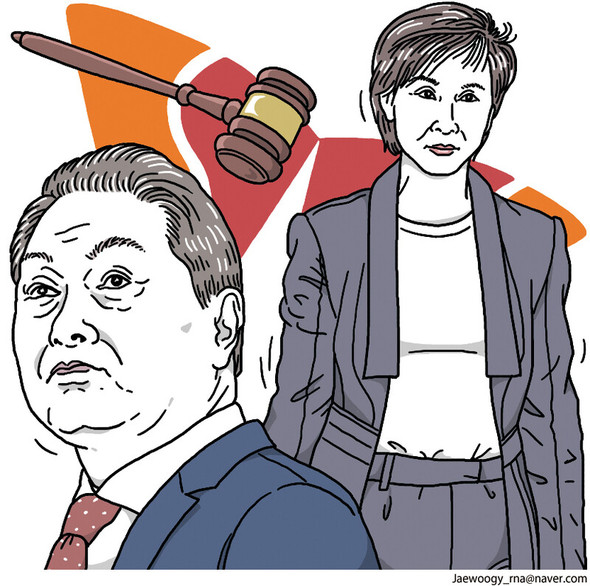[ニュース分析]「敵との対座」から260日…“正常国家の関係”への大きな歩み

「米国大統領」ドナルド・トランプが「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)国務委員長」金正恩(キム・ジョンウン)と初めて会ったのは、2018年6月12日だ。分断国家である北朝鮮が出現して2万5469日目になる日だ。また260日が経った2019年2月27日、両首脳が2回目に会う。
25469と260。2つの数字の差に、朝鮮半島の平和の命運を担った朝米首脳会談の歴史的位相と課題が含まれている。2回目の出会いは、初対面よりずっと容易だった。初めて会うのにかかった歳月の1%で十分だった。ただし260日は、「1128日戦争」を含めた2万5469日のあいだ積み重ねられた敵対と不信を鎮めるにははるかに足りない時間だ。戦争・敵対・葛藤の歳月が長いほど、和解・平和も遠のく。そのため「一か八か」という態度を避けなければならない。道のりは遠い。
2回目の出会いは、ベトナム社会主義共和国の首都ハノイで行われる。ハノイは戦争から平和へ、敵対から和解・共存へと進む道が閉ざされていなかったことを実証する歴史の証人だ。首脳会談の会場に最終確定されたことで知られるメトロポールホテルはどうだろうか。ハノイの夜空に米軍の砲弾が雨のように降り注いだ1972年、クリスマス・イブにジョーン・バエズが隠れていた地下防空壕が今もある。当時「トン・ホテル」と呼ばれたこのホテルの防空壕で、バエズは米国のベトナム侵略に反対する人々の聖歌である「勝利を我らに(We shall overcome)」を歌い続けた。メトロポールホテルは、多くの命を飲み込んだ侵略と抵抗で染まった戦争、和解と省察の苦しい身悶えを目にした歴史の証人だ。1961~68年、米国防長官としてベトナム侵略を設計・執行したロバート・マクナマラが、グエン・コ・タク元ベトナム外相と「なぜ戦争に陥り、早く終わらせられなかったのか」を振り返り、「新たな過ち」を防ぐため「失われた機会」を探索した「敵との対話」が初めて行われた場所だ。
マクナマラは1997年6月20日~23日までの最初の対話で、長い教訓を二つに圧縮した。「敵を理解しろ」と「相手が敵でも最高指導者同士で対話を続けなければならない」がそれだ。金委員長とトランプ大統領は「マクナマラの教訓」に習おうと彼らなりに努力している。最初の会談の成果を基に、2回目の会談では「正常国家の関係」への大きな一歩を踏み出すことを期待する。
悲観と落款が交錯する。まず、70年の敵対国だった両最高指導者が会い、「包括的かつ深度ある率直な意見交換」の末に設けた「セントーサ合意」(6・12シンガポール共同声明)の履行の実績は貧弱だ。最初の会談以降、金委員長は朝鮮戦争時の米軍の遺体55柱を返還し、東倉里(トンチャンリ)のミサイルエンジン試験場・発射台の永久廃棄のための基礎措置を取った。米国は、対北朝鮮制裁を理由に阻止してきた国際人道支援団体の対北朝鮮支援を、年末からほんの少し開放した。それだけだ。
しかし、朝鮮半島における冷戦構造の解体のビジョンが盛り込まれたセントーサ合意は破棄されなかった。生きて息づいている。時期尚早な悲観は警戒しなければならない。朝鮮半島は「地球上で最後の冷戦体制」(文在寅大統領)に根を下ろした敵対と葛藤が渦巻く悲劇の地だ。朝鮮半島の冷戦構造は、竹林のように根が絡み合った四つの柱が支えている。「(1)対決と不信の南北関係(2)朝鮮半島問題に深く介入した米国と北朝鮮の敵対関係(3)北朝鮮の体制生存と抑制力確保のための核兵力追求(4)敵対関係の根幹である軍事停戦体制の持続と軍備競争」だ。初期の朝鮮半島平和プロセスの設計者であり実践者であるイム・ドンウォン朝鮮半島平和フォーラム名誉理事長(元統一部長官)は、「これらの要素は相互依存性を持ち、ある一要素だけ分離して問題を解決することはできない」とし、「包括的にアプローチしてこそ朝鮮半島問題の根本的な解決が可能だ」と助言する。
セントーサ合意は四つのうち三つを同時に取り除くという朝米首脳の約束文書だ。「新たな朝米関係の樹立」(第1項)は(2)に、「恒久的かつ堅固な平和体制構築の共同努力」(第2項)は(4)に、「朝鮮半島の完全な非核化に向けた努力」(第3項)は(3)に対応する。(1)は4・27板門店宣言と「9月平壌共同宣言」、「9・19軍事分野合意書」の実践ですでに解消作業が始まった。南北は(2)(3)(4)の解消の努力にも歩調を合わせる。セントーサ合意と南北首脳宣言が完全に履行されれば、朝鮮半島の冷戦構造の四つの柱は、春の雨に溶け新しい生命を育てる氷のように平和の元肥となるだろう。南北米の首脳の「三人四脚競走」が切実だ。
金委員長とトランプ大統領があらゆる圧迫と誘惑にもかかわらずセントーサ合意を守り抜いた事実が何よりも重要だ。悲観論者と楽観論者が、全く異なる世界観と利害関係でも共感することが一つある。金委員長とトランプ大統領の2回目の会談の目的は、セントーサ合意の4項目の具体的な履行案づくりにあるという共通認識だ。これ自体が最初の会談から260日の大きな成就だ。軌道から外れれば「平和列車」は目的地に到達することができない。
最初の会談後、相互信頼の糸口
「合意履行」悲観・楽観は分かれるが
朝米、非難を自制し対話を継続
金委員長とトランプ大統領は最初の会談で「相互の信頼構築が朝鮮半島の非核化を増進させることができる」と確言した。しかし、不信は深く信頼は浅い。1回目の朝米首脳会談直後、マイク・ポンペオ米国務長官は「空のカバン」を持って平壌を訪れ、「すべて申告せよ」と圧力をかけた。北側は「強盗のような要求」と言い返した。不信の沼に沈んでいたセントーサ合意を「促進者」の文大統領が救い出した。「米国が相応の措置を取れば寧辺(ヨンビョン)核施設の永久廃棄のような追加措置を取り続ける」という金委員長の約束が明示された「9月平壌共同宣言」がそれだ。「信用できる第3者」は敵対の解消に欠かせない触媒だ。
先民意識に浸った米国が天から地上へ降り、北朝鮮が「米帝の狼」の北侵の恐怖を振りかざさず地上に上ってくるには、さらに時間が必要だった。年を越して「機会の時空間」が開かれた。米国は北朝鮮を「合理的行為者」とみなし、北朝鮮は「米国式対話法」に応じようと努力した。
スティーブン・ビーガン国務省対北朝鮮特別代表は「両国は個人の権利と人権について全く違う見解を持っており、地域とお互いに対し異なる世界観を持っている」としながらも、他の米国人と違って北朝鮮を「やくざ国家」と非難しなかった。そして「シンガポール共同声明で行ったすべての約束を同時並行的に推進する準備ができている」と明らかにした(1月31日スタンフォード大学講演)。「同時並行」は、米国の「先非核化」の圧迫に対抗して北朝鮮側が掲げた履行原則だ。金委員長は、新たな交渉窓口であるキム・ヒョクチョルの肩書きをビーガンの「対北朝鮮特別代表」に合わせた「対米特別代表」とし、米国に伝えた。
「セントーサ合意」は息づく
冷戦解体に向けた第1回会談の合意4項目
ハノイで具体的な履行案を用意
「相互信頼」を積もうとする努力は、セントーサ合意の履行の力強い推進力となり得る。まだまだ微弱ではある。双方が不信の凍土に信頼の種を撒き、耕しているという事実が重要だ。
敵が一瞬で友になるわけではない。長く苦しい過程を経なければならない。善意の一方的な措置→相互節制→交流協力の深化→新しいナラティブとアイデンティティの創出などが必要である(チャールズ・カプチャン、『敵はどのようにして友になるのか』)。友人になるためにはまず「他の人たちのようにする」ことを学ばなければならない。腹積もりが異なって争うとしても銃刀を使わず、早い利害打算にも礼儀を備える、世界の多くの「正常な国家関係」をだ。金委員長とトランプ大統領の2回目の会談が、長い敵対を越え「普通に付き合う」ための大きな一歩につながることを願う。
訳M.C