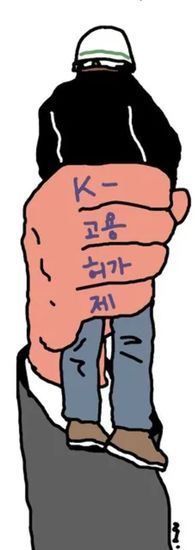「ああ、そうなんですか?」
14日行われる衆議院選挙を前に、東京の韓国特派員たちが選挙結果について意見交換を行うため、駐日韓国大使館に集まった時のことである。これまで公開された世論調査の結果を見ると、自民党は現在(295議席)よりも多い300以上の議席を確保し今回の選挙で圧勝する見込みだ。この場合、国交正常化50周年を迎える来年の日韓関係はどうなるだろうか。 「希望的観測」 が飛び交う中、「日本では選挙の時、有権者が候補者の名前を記入することになっている」という話が話題になった。そのような基本的なことも知らず、この1年間日本に関連する記事を書いてきたのかと思うと、何だか少し恥ずかしくなった。
事務所に戻って日本の公職選挙法の規定を調べてみた。同法第46条に「選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない」という規定を見つけることができた。候補者たちの名前がすべて印刷された投票用紙をもらって名前の横に印を押すだけの韓国の投票方式と違って、斬新な気がした。
なぜこのような規定が作られたのだろうか。知り合いの日本人に電話をかけ理由を訊いているうちに、もっともらしい仮説を聞かせてくれる人に出会った。日本の投票制度の淵源を辿っていくと、その理由が推定できるということだった。
1869年に明治維新を通じて近代国家の枠組みを作った日本は、1889年に「衆議院議員選挙法」を制定し、「満25歳以上で税金を15円以上納付する」(6条)人たちに選挙権を与える。以来、時間が経つにつれ、税金条項が廃止され、1925年に「25歳以上のすべての男性」(総人口の20.12%)に選挙権が拡大した。日本の近代的な教育機構がある程度整った頃だから、大人の男を基準にした非識字率は非常に低かったに違いない。参考までに日帝植民地時代の朝鮮人たちには1944年徴兵制が朝鮮に拡大実施された後の1945年4月になってようやく選挙権が与えられた。

公職候補者の名前の横に印を押す韓国の方式と、自らの手で名前を記入する日本の方式とは、どのような違いがあるのか。自分が支持する候補の名前を自らの手で書く行為には、単に印を押すのとは異なり、自分の意思を示すためのより積極的な意味が込められている気がする。人の名前を書き込むためには、その人の顔を覚えなければならず、その人の政策ももう一度検討しなければならないからだ。とんでもない人を代表に選んで国が危機に陥った場合、彼の名前を直接書いた国民の一人として、より大きな責任を感じるかもしれない。
さらに、日本の方式は韓国とは異なり、選挙区別にあらかじめ投票用紙を作成する必要もない。そうなれば、今年7月30日、「銅雀(ドンジャク)乙」選挙区で行われた再補欠選挙のように、第3候補の辞退が遅くなり、無効票の数が1位と2位候補の票差よりも大きくなるコメディのような事態を防ぐこともできる。「何も聞かずとも(無条件で)1番」、あるいは「何も聞かずとも(無条件で)2番」を選択する地域主義的な投票行為はもちろん、誰が1番になるのかによって投票の結果が大きく変わる教育監選挙の問題点も一気に解決される。ただし、投票用紙の分類が手作業で行われるため、担当公務員は骨が折れるだろうし、「なのに日本の政治が今そのレベルか」と攻撃されたら、特に返す言葉もない。
だったら用紙に「パク・クネ」ではなく「バク・クンヘ」と書かれた場合にはどうするかって? 2005年徳島県鳴門市で行われた市会議員選挙では候補者の苗字は正しく書かれていたが、名前の代わりにあだ名の「ひげ」と記入された投票用紙も有効票として認められたという。候補者の名前を有権者が、直接記入する投票制度、一度(導入を)考えてみてもいいのではなかろうか。
韓国語原文入力:2014/12/11 18:48