保坂正康著、チョン・ソンテ訳/文壺

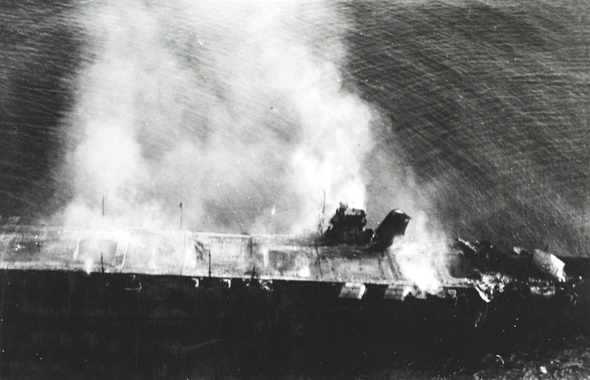

第2次世界大戦に参戦した日本帝国陸軍500人の証言
A級戦犯など、軍部の主要人物を取材
サイコパスのように被害者の悲鳴に鈍感
「虐殺には軍人たちにも、天皇にも責任がある」
戦犯ら生き残って再び出世の道へ
自己弁護や嘘に始終する無責任さを「暴露」
日本軍が満州侵略以降、敗戦までに犯した戦争(「15年戦争」)により死亡した日本軍人と軍属、民間人の数は、厚生労働省の推定(1976年の調査)で310万人。これを引用したノンフィクション作家の保阪正康氏の『昭和陸軍』(原題:『昭和陸軍の研究』)には「これに台湾と朝鮮の人々を加えると、優に400万人を上回るだろう」という説明がついている。 日本敗戦当時には生きていたが、戦争での負傷が原因で死亡した人まで加えると、死亡者が500万を超えものと見られている。昭和10年代(1930~40年代)の日本国民が7500万人だったから、国民の6~7%が戦争の犠牲になったことになる。
同書はその期間中、日本軍の手により死に至った中国人の数も3000万人に達するという推定も引用している。朝鮮人犠牲者はどのぐらいだったのだろう?誰も知らない。朝鮮人犠牲者を体系的に調査したとか、調査結果が残っているとのニュースも聞いたことがない 。日本は自国民の犠牲者の規模は推計しているが、自国が無慈悲に動員した被侵略・植民地人の犠牲者がどれほどになるのか一度もまともな調査をしたことがない。


著者は1996年に日本軍「慰安婦」補償問題の解消を狙って作った日本の「アジア女性基金」に一応賛成を示しているが、基金を受領した人に当時の橋本龍太郎首相の名前で渡した手紙形式の謝罪文を「公式謝罪」として認めていない。その理由は、手紙が「いわゆる従軍慰安婦問題」が「(日本)軍の関与の下に」行われたとして、「心からのおわびと反省の気持ち」を表したが、事実関係を明らかにしたうえで出てきた言葉ではないからだという。「まず(日本)政府がすべきことは、『当時の事実関係を詳細に調査した後、過ちがあるなら、謝罪すべきことは謝罪し、誤りや誤解があるなら、それを解消する』という約束だ。このような文言が盛り込まれない限り『公式謝罪』ではない」。謝罪は空しい言葉で曖昧に済ませるような問題ではないということだ。
この部分は同書と著者が持つ特徴をよく表している。著者は具体的な事実確認の作業を何よりも重視する。そして、加害者や強者、エリート、彼らが作り出した「公式的な記録」だけではなく、弱者や犠牲者たちが残したものや公式記録から外されたか、意図的に排除されてしまった記録に注目する。また、資料だけに依存せず、現場を回り、数千人から話を聞いている。『昭和陸軍』は、題名通り著者のこのような特性が、日本が侵略戦争に明け暮れた裕仁天皇(昭和)時代(1926~1989年)の実力者だった日本陸軍を対象に発揮される。だからこそ、日本陸軍について、これまでとは異なる角度の記述がみられる。なぜ日本軍は、あれほど侵略戦争にこだわったのか。なぜ無慈悲な大量虐殺を行ったのか。そして、敗戦後も戦犯者とその後裔たちが戦後日本の主流となり、退行的な安倍晋三政権が登場したのか。

3部で構成されたこの本の第1部は、明治時代(1868~1912年)初期の建軍から大正時代(1912~1926年)にわたる日本軍の歴史、つまり昭和陸軍前史を取り上げている。その中心となるのは、太平洋戦争で軍指揮体系の根幹となる明治10年代中期~20年代後期生まれの陸軍入隊者たちの特性と天皇との関係だ。彼らは富国強兵を志向した日本が最初に量産した近代軍人の最初の世代として、陸軍大学中心の過度なエリート主義、長州派閥からの脱却、親ドイツ・反英米、そして軍事技術にこだわるあまり、「人間に対する洞察力が著しく欠如しており、人間をただ戦時消耗品にみなす」特性を持っていた。このような特性が統帥権者である天皇だけに責任を負う「皇軍体制、反文民主義」、反文民主義、忠節・礼儀・武勇・信義・質素を強調する「軍人勅諭」と結びつくことで、彼らを怪物と化していく。天皇の旗を掲げた最高統帥機関の「大本営」の陸海軍作戦計画の最高責任者は陸軍参謀総長で、大本営会議で政治家たちは排除された。帝国日本の先制攻撃中心の戦略と、過度な精神主義、盲従を強要する前近代的家族主義は、欧米のライバルに比べて比較的に弱かった国力という弱点を補うためのものだった。大正時代に議会側の反撃があったが、昭和時代(第2部)に入ってからは、そのような体質は張作霖爆殺に続く満州侵略以降、さらに固着し増幅されていく。

日本軍、特に日本陸軍が侵略戦争に駆け上がったのは、過度な学閥・エリート・地域主義がもたらした派閥争いや天皇に依存した陸軍第一主義、出世や生存競争、そして戦争と賠償金を国家財政の確保と成長の動力にした結果だった。 1936年、天皇絶対主義者の青年将校たち(皇道派)が当時の実力者だった陸軍幹部中心のエリートたち(統制派)を追い出そうとしたクーデターの「二・二六事件」は派閥闘争の典型だった。ニ・二六事件は失敗したが、天皇機関説(天皇も国家機構の一つとみなす)を信奉する統制派の陸軍優位体制をさらに強化する結果となった。日清戦争以来、相次いで得た莫大な賠償金と資源・人材の収奪などが国家経済を豊かにしたことも、戦争を通じた軍事的勝利にこだわる原因となった。
彼らは、サイコパスのように被害者らの悲鳴には鈍感だった。 日本陸軍将兵たちの残酷な大量虐殺体験の告白は無惨なものだ。著者は1937年の南京虐殺から日本軍の大量虐殺が始まったと見ている。しかし、東学と日清・日露戦争ですでにそのような虐殺は行われていた。著者はそのような戦争犯罪に天皇がどのように介入したのかを示し、天皇にも当然「責任がある」と断言する。

敗戦以降の時代を取り上げた第3部では戦史編纂と、それと密接に絡み合った米軍政の役割が目を引く。米軍政期間に総司令部(GHQ)では参謀第2部(G2)と民政局(GS)が対立した。参謀第2部は、冷戦とともに「近いうちに再武装を許可し、反共の砦として日本を軍事大国に育てなければならないと考え」ていたが、それを主導した人がチャールズ・ウィルロビー少将だった。一方、民政局を率いていたコートニー・イッホイットニー准将は、その反対に昭和陸軍の完全な解体を主張した。このような亀裂を利用し、『太平洋戦争史』、防衛庁が発刊した102冊の『戦史叢書』など、太平洋戦争史に基礎資料の編纂を主導した人が、ウィルロビー側と手を握った服部卓四郎大佐だったが、彼は太平洋戦争の主犯の東条英機首相兼陸軍相の秘書官だった。数多くの部下と民間人を死に追いやった彼らの多くが、こうして生き残り、何の責任も負わず、再びの出世の道を歩んだ。著者の保坂氏が責任逃れ、自己弁護、合理化に満ちた偽りだらけだと批判した公認の戦史はそのように作られた。それだけ過去の歴史を否定する無責任さと不道徳さの根は広くとも深い。著者は、日本の戦後清算は日本国内外の犠牲者たちに対する調査と謝罪、賠償なしには不可能であると述べている。
韓国語原文入力:2016-08-11 18:57

