マシュー・デスモンド著、ソン・ウォン訳、チョ・ムニョン解説|アルテ刊
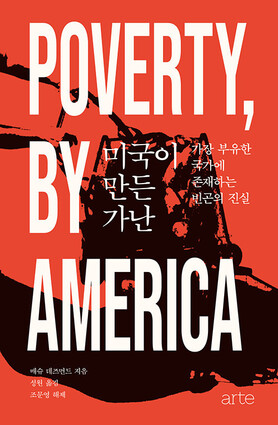
裕福で強い国である米国はなぜ貧困率が高いのだろうか。なぜ麻薬中毒者が急増し、「ゾンビ通り」ができ、都心にホームレスのテント村が増えるのだろうか。都市貧民街の住居問題を扱った著書『家を失う人々』(Evicted: Poverty and Profit in the American City)で注目を集めたプリンストン大学のマシュー・デスモンド教授(社会学)は、この質問に対して正面から答えを探った。貧しい人たちの実際の話とデータを活用し、貧困がどのようにして貧しい人たちの人生を奈落に突き落とし、裕福な人たちに利益を与えることになるのかについて、米国社会にメスを突きつける。
著書『米国が作った貧困:最も裕福な国に存在する貧困の真実』(Poverty, by America)では、「新自由主義」が貧困を引き起こすという既存の構造化分析から、具体的な現実に入って米国の貧困問題を分析する。米国の福祉予算は着実に増加しているにもかかわらず貧困が続く理由は、福祉政策が貧しい人たちに届かない「水が漏れる容器」だからだというのが著者の診断だ。たとえば、一部の州政府は、貧困者救護金を教会のコンサートや元スポーツスターの演説などのイベントに数百万ドル支出した。政府の福祉の恩恵を受けるためには複雑な手順を踏む必要があり、貧しい人たちはそのために弁護士費用を支出する。
さらに踏み込み、労働者を安く働かせる社会システムや、貧しい都市で家主が高い家賃で低所得層から絞り取る現実などを指摘する。著者は矛先を「私たち」に向ける。2015年にウォルマートが最低時給の引上げ案を発表したときに株を売ってしまった人たち、プラットホーム労働者たちの労働環境には目を向けず便利さに歓呼する市民たちは、「貧困システム」の共犯だというのだ。「人々は貧困からあらゆる手段で利益を得る」と一喝する。
著書『貧困過程』で注目を集めた延世大学文化人類学科のチョ・ムニョン教授の解説は、この本が示す現実が韓国社会とさほど離れていないという事実を痛感させる。
訳M.S

