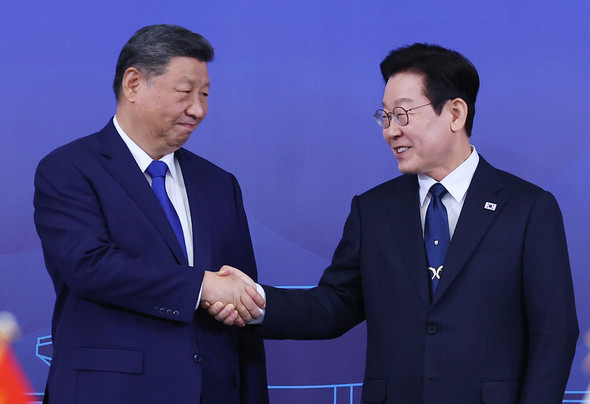安倍首相、参議院選挙で「勝利」…改憲発議の議席数確保には「失敗」
過半数を超える71議席を確保
日本維新の会を含む改憲勢力
3分の2の維持には失敗

安倍晋三政府が21日に行われた日本の参議院選挙で選出議席の過半数を占めて勝利を収めた。だが、憲法改正発議に必要な与党と改憲賛成勢力を合わせた「改憲勢力」が3分の2を維持するのは失敗した。
22日までの開票の結果、自民・公明の連立与党は71議席(自民57席・公明14議席)を確保し、今回選出議席124議席の過半数である63議席を軽く突破した。自民党の二階俊博幹事長は、今回の選挙の「最低目標」として改選議席の過半数獲得を提示していた。連立与党が過半数を獲得するという予想は早くからあったため、異変とは見られない。自民党は単独過半数までは達成できず、連立与党の公明党にさらに気を配らなければならない立場になった。
連立与党と改憲に積極的な野党の日本維新の会などを含む改憲勢力は、81議席を確保したと集計された。NHKと朝日新聞は、改憲勢力が参議院全体の3分の2である164議席以上を維持するためには、今回の選挙で85議席以上を獲得しなければならないが、失敗するのは確実だと報道した。改憲勢力はそれぞれ自民党57議席、公明党14議席、維新の会が10議席を確保した。第1野党の立憲民主党は17議席を確保し、以前よりも議席がかなり増えた。定員が245議席の参議院は3年に一度ずつの定員の半分を新たに選ぶ。今回の選挙では124議席が選出対象だった。
改憲発議の議席維持に失敗し、安倍政権の改憲に一定のブレーキがかかった。しかし、安倍首相は自民党総裁任期の2021年9月中に軍隊の保有と戦争禁止を規定した現行の「平和憲法」を改正しようとする試みを止めないものとみられる。
安倍首相は21日夜、TBS番組に出演し、憲法改正と関連して「(参議院)の結果は『やはりちゃんと議論すべきだ』という国民の審判だ。この選挙結果によって少なくとも議論をしてほしいと期待している」と述べた。彼は日本テレビの番組に出演し、「もちろん期間を決めたわけではないが、任期中に(改憲の)国民投票までしたい」と語った。改憲勢力3分の2の維持失敗が確定される前に出た発言だが、安倍首相の執念を垣間見ることができる。
憲法改正は安倍首相の生涯の宿願だ。さらに、安倍首相は別の長寿首相に比べてはっきりした“レガシー”(遺産)がないという指摘を受けており、憲法改正にさらに力を入れるとみられる。
実際、安倍首相は2017年10月の衆議院総選挙の大勝で参議院と衆議院の両方で憲法改正発議に必要な改憲勢力の3分の2の確保に成功したことがある。しかし、日本の戦後民主主義の中心軸である現行の「平和憲法」改正に反対する抵抗も強かった。
安倍首相が、参議院・衆議院の両方で改憲派が3分の2を占めている中でも簡単に憲法改正発議をしなかった理由も、日本の市民たちが戦争放棄と軍隊保有禁止を規定した憲法9条の変更に対する抵抗が依然として大きいためだった。恵泉女学園大学のイ・ヨンチェ教授は「衆院を早期解散し、憲法改正ムードをさらに盛り上げようとする可能性もある」とし、「安倍首相の最近の演説を聞くと、憲法改正の試みは軌道に入った。米国は憲法改正を要求してきており、保守も望んでいた。これまで革新勢力が阻止してきた」と述べた。
今後、安倍首相は衆議院解散の時期を天秤にかけるものと予想される。日本で衆院解散権限は首相にある。改憲勢力としてはっきり分類されてはいないが、改憲論議そのものには肯定的な国民民主党を引き入れ改憲を推進する戦略も使い得る。来年の東京五輪を機に、国民の団結を引き出し、これを改憲のための国民的動力として活用することもあり得る。今回のNHKの出口調査では、憲法を改正する必要があるかという質問に対し「必要だ」36%と「必要ない」33%で拮抗した。
韓国に対する輸出規制は、選挙後にも続くものと見られる。選挙結果に左右され輸出規制を取り消すのは、支持基盤の保守派の反発を招きかねないためだ。ただし、今回の選挙で改憲勢力が3分の2を超えられず、対韓国輸出規制の推進力がやや弱まるかもしれないという予測もなくはない。
訳M.C