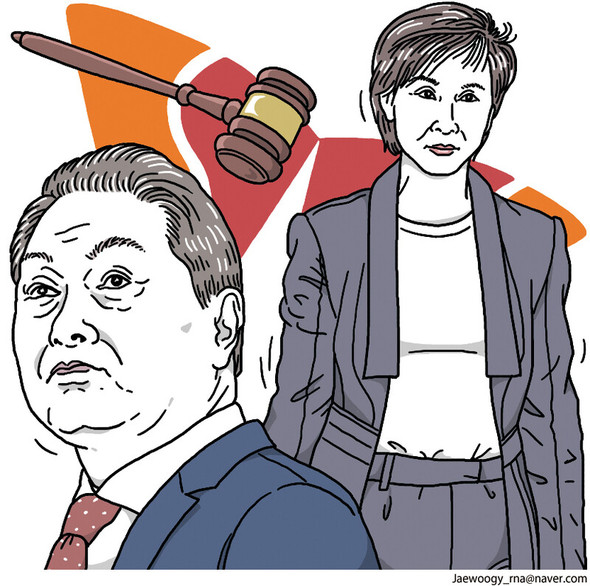多様性侵害し競争煽る
知識生産の大衆化を遠ざける

『誰が文化資本を支配しているのか?』
『文化/科学』編集委員会 編
イ・ドンヨン、ハン・ギホ、イ・ユンジョン他
文化科学社・2万ウォン
韓国の学術、大衆文化、出版分野における文化資本の独占的支配力が憂慮すべき水準まで強まったという指摘が出た。 季刊誌『文化/科学』が80号発刊を記念して特別単行本として出した『誰が文化資本を支配しているのか?』は、最近の韓国の文化資本集中現象を本格的に暴いた。 13人の専門家が学術と文化産業の各分野を点検して、資本蓄積と再生産を分析した。

オ・チャングン中央(チュンアン)大学教養学部教授(『文化/科学』編集委員)は、韓国研究財団が“学問権力”に変質したと批判した。 この機関は1981年に人文社会分野支援のために設立された韓国学術振興財団(学振)が李明博政権時期の2009年に韓国科学財団と統合されマンモス級の研究管理専門機関に変わった。 2014年の韓国研究財団の総予算は何と3兆6993億ウォン(約4000億円)。このうち人文社会分野の予算は2250億ウォン(約250憶円)に留まるのに比べ、原子力振興関連単一予算は684億ウォン多い2934億ウォン(約320億円)だったと著者は明らかにした。 機関統合に反対した研究者が憂慮したとおり、人文社会分野支援が冷遇されているわけだ。
さらに大きな問題は財団活動が若い研究者の新しい学会創立や学術誌創刊の障害物として作用している点だ。 昨年末まで財団が学術誌評価制度を廃止すると明らかにしていたが、突然立場を変えて優秀登載学術誌を選定し集中支援する計画を立てたのも学問の位階化と規律化を表わすとオ教授は分析した。 学術誌を等級付けして学問の多様性増進を妨害しているということだ。
分析を総合すれば、学界における韓国研究財団の力は独歩的だ。 国内研究開発(R&D)分野、人文韓国(HK)支援事業、頭脳韓国21プラス(BK21+)も総括している。 大学評価を左右するこれら事業の受注を握っているのはもちろん、教授採用の可能性にも関わっている。 研究支援を受けて論文を量的に蓄積すれば教授社会に進入できる道が開かれるためだ。専任教授になった後も、財団の新進研究者支援を受けて学術誌論文掲載数を増やせば定年まで保障された教授になれる。 多くの学者が登載学術誌論文を書くことに没頭し、学問的成果の大衆的共有を遠ざけるようになった。 その結果、知識生産と学術書出版の間に大きな乖離ができてしまったわけだ。
オ教授は韓国研究財団が政治権力の変化にともなうイシュー設定に足早な姿を見せたと指摘する。 李明博政権時期“緑色成長”関連研究主題を支援課題として多数選定し、昨年は朴槿恵政権の国政課題である「創造経済」と「文化隆盛」に符合する研究支援体系を提示したためだ。 これについて、オ教授は財団が「政治的効用性の側面で政権に動員」され「(学問支援を)国民国家の規律権力内に狭小化する方式で作動している」と批判した。 財団の独占的地位と権力行使で学問は大衆との距離が遠のき、研究者と学問後続世代の日常までを規律することになったということだ。
その他にも、この本は大衆文化をはじめとする文化資本全般の独占問題を集中分析した。 イ・ユンジョン『文化/科学』編集委員(成均館大学講師)はアドルノ/ホルクハイマーの“文化産業”概念とブルデューの“文化資本”理論を中心に位階化・序列化された支配構造を批判している。 美術館が難解な作品を陳列して文化の階級化・差別化を強固にするように、映画の生産と消費でも階層的区別作り(ブルデュー)現象が広がっているということだ。
カン・ジョンソク知識循環協同組合事務局長(『文化/科学』編集委員)はCJ CGVが巨大ブロックバスターだけでなく多様性映画専門上映ブランドを試みたことを「独占現状の柔軟化」と指摘する。 独占に対する代案として多様性映画分野への大企業進出がなされたが、その市場内で創作者同士によるもう一つの競争的環境が造成されたということだ。
イ・ジョンイム文化連帯メディアセンター運営委員(高麗大学講師)は、CJ E&Mがコンテンツ生産とメディアプラットホームの運営を一緒にし、放送、ゲーム、映画、音楽・公演事業部門を率い巨大メディア企業として付加市場全体を掌握しつつあると評価した。 スクリーンを独占し金を儲けるように、8個にもなる放送チャンネルで同じ時間帯に『三銃士』のようなドラマ一つを編成する物量攻勢を展開できるようになったという意味だ。 著者は「付加市場全体が一つのコンテンツ プロバイダと一つのプラットホーム社に再編されるかも知れない」と憂慮した。
ゲームコンテンツの製作と流通に現れた独占集中化現象(カン・シンギュ)、巨大象徴化された文化資本として“K-POP”の問題(イ・ドンヨン)も議論される。特に国家韓流政策と韓流文化資本のグローバル化の問題(チェ・ヤンファ)は文化政策に対する深刻な憂慮がある。
著者は文化資本の蓄積が単に市場で自然になされるわけではなく、金大中政権の時から集中的な文化振興政策にともなう投資拡大と公共支援のおかげで土台を形成できたと分析する。 しかし各政権の文化資本投資規模と公共的支援がどの程度の規模であり、どんな躍動を経たのかに対するデータと深層分析が不足している点が惜しい。 ウェブコミックのようなインターネットコンテンツ産業まで掌握しつつある文化資本の独占効果に対する一層精巧な分析と幅広い研究協力が必要だ。
韓国語原文入力:2015/01/15 21:59