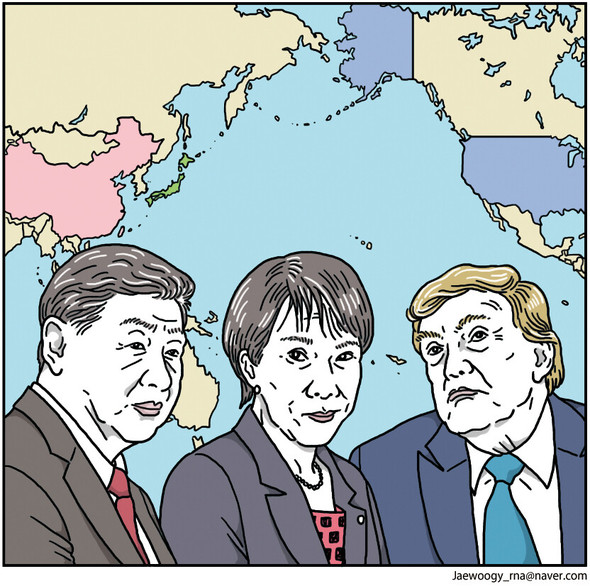最近20年はすべての社会の企業化、企業国家の時代であった。ろうそく集会は、国民が自己開発の経営者、株式投資家、そして消費者としてのアイデンティティを振り返ってみた国民再教育の過程だったと見ることができる。このように見れば、文在寅(ムン・ジェイン)政府は民主政府3期ではなく、第2の民主化を始める政府にならなければならない。
国民の党のイ・オンジュ議員は、「飯の仕度をするおばさんがどうして正規職にならなければならないのか」と発言して大きな波紋を起こした。単純労働を蔑視する彼女の普段の思想があらわれたわけだが、非正規職の正規職化の動きに負担を感じた企業側の拒否感を集約したものと見て良いだろう。数日前、中小企業と小商工人は来年の最低賃金引上げ案に反対し、最低賃金委員会への参加を拒否した。労働者に月200万ウォン払えば、自分たちが立ちゆかなくなるということだ。一方、先日文在寅政府の自律型私立高廃止政策に反対して、自律型私立高生徒の親たちは「国家競争力強化のためには人材育成が必要だ」として自律型私立高廃止反対デモをした。
文在寅政府の非正規職保護、教育公共性強化政策に対する利害関連者の反発が次第に行動になって現れている。十分に予想されたことだ。大企業の譲歩を前提としない労働保護政策は、これまで低賃金で耐えてきた中小企業・小商工人を危険にするであろうし、自律型私立高廃止政策は子供の大学入学成功に死活を賭けた自律型私立高の親を混乱に陥れるだろう。しかし、こうした抗議の背後には、企業の競争力が国家の競争力であり、少数の人材が多数の単純労働者を食べさせているという経営の観点、経営者は消費者の要求に応じているのみという消費者主権論が深く根ざしている。
こうした反発と集団行動を通じて、私たちは文在寅政府が大企業、自由韓国党、そして保守マスコミという明白な反対勢力のみならず、経営者/消費者の観点が内面化された韓国市民社会の基層とも対抗しなければならないという事実を新たに確認できる。その打破は、外国為替危機以後の過去20年余り、いや1960年代以後からこれまで、韓国の社会構成員の意識の奥深くに根をおろした能力主義、競争力至上主義、勝者一人占めの文化を越える険しい作業だ。
金大中(キム・デジュン)大統領を懐かしむ人は、今は文在寅政府が再び南北和解政策に始動をかける姿を見て歓呼し、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の“見果てぬ夢”に悲しむ人々は、文在寅大統領の検察・国家情報院改革の意志に大きな期待をかけている。私も彼らと思いを一にする。しかし、考えてみれば金大中、盧武鉉の両政府も労働を費用の観点で見る経営者主義観点、自律性と多様性という消費者主義の立場に立って労働/教育政策を展開した。金大中と盧武鉉、二人の大統領の政治的民主化の意志にもかかわらず、グローバル的新自由主義の波には対抗できなかったし、国内の財閥・官僚を制圧する力もなかった。
それゆえに、李明博(イ・ミョンバク)・朴槿恵(パク・クネ)政府が残した積弊が大きいとはいえ、社会経済的側面で見ればその前の二つの民主政府と李明博・朴槿恵政府は連続性が強い。私に言わせれば、過去20年はすべての社会の企業化、企業国家の時代であった。それで過去20年間、韓国は財閥大企業と経済官僚が作った論理、思考方式、文化が、国家機関、マスコミ、大学、教会、家庭を支配し、結局国民大多数の日常と行動を支配した。それですべての国民は自己開発経営者になり、都市中産層は不動産投資プランナーになり、社会構成員は主権的市民ではない消費主体になり、人文社会系の大学生は経営学科の学生を羨望することになった。
ろうそく市民の行動は、国民が自己開発経営者、株式投資家、そして消費者としてのアイデンティティを振り返って見た国民再教育の過程だったと見ることができる。このように見れば、文在寅政府は民主政府3期ではなく、第2の民主化を始める政府にならなければならない。第2の民主化、それは企業国家、経営国家から抜け出すことであり、労働を短期的な費用の観点からではなく社会的主体として位置づけることだ。社会的余剰に分類される単純労働者、学歴不振の学生に自信と能力を付与し、堂々とした社会的主体にしない限り、社会統合はもちろん経済活性化も難しいという考えに到達するまでに、私たちは20年の歳月が必要だった。それは熟練形成より賃金引き上げと企業福祉に重点を置いた組織労働にも反省を促すことでもある。
今は当面の利害調整、若干の政策的軌道修正よりも、はるかに根本的な政策転換と国家ビジョンが必要な時だ。この政府は「企業の国家」を皆のための国家、すなわち社会的国家に変化させるという大きな絵を描いて利益集団を説得し、譲歩を引き出さなければならない。
キム・ドンチュン聖公会大NGO大学院長、新たな百年研究院長
訳J.S(2116字)