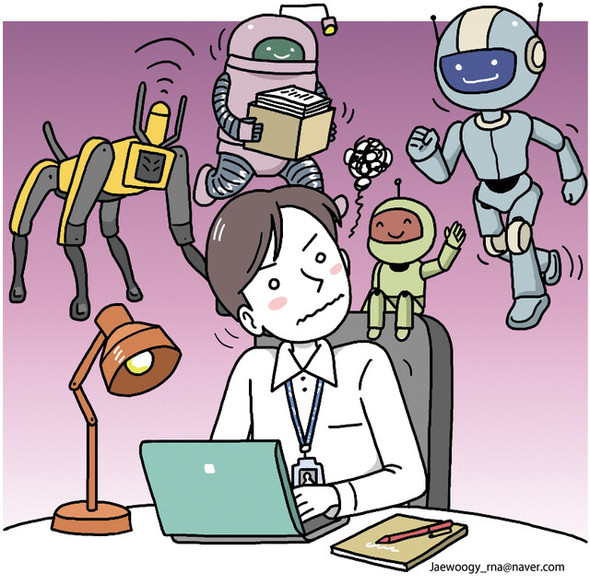日米首脳会談の際、岸田首相「相当な増額」を約束
「安倍元首相の注文で具体的な数値を明示」

日本政府は、現在国内総生産の1%水準である防衛費を、5年以内に2倍以上増額するという内容を政府政策に明記した。今後、防衛費増額議論に拍車がかかるものとみられる。
日本政府は7日、防衛費増額などの内容が盛り込まれた日本の今後の経済財政政策の主要な方向をまとめた「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太の方針)」を閣議決定した。骨太の方針には、先月22日の日米首脳会談共同声明で岸田文雄首相が「相当な増額を確保する決意を表明」した防衛費について、「予算編成過程において検討し、必要な措置を講じる」という内容を初めて明記した。防衛費増額が「政治的なスローガン」ではなく、実際の予算で編成されるよう手続きを踏むということを意味する。
骨太の方針には防衛費増額の具体的な規模は明らかにしなかったが、北大西洋条約機構(NATO)諸国が国防予算を国内総生産(GDP)の2%以上に目標値を提示したことを例に挙げた。2%以上増額するということを遠まわしに表現したわけだ。
今年の日本の防衛費は、本予算基準で5兆4005億円で、国内総生産の0.96%水準だ。5年内に防衛費を10兆円以上に引き上げるためには、毎年相当幅の増額が必要だ。日本政府は「ロシアがウクライナを侵略し、国際秩序の根幹を揺るがすとともに、インド太平洋地域においても、力による一方的な現状変更やその試みが生じており、完全保障環境は一層厳しさを増している」とし、「新しい国家安保戦略などの検討を加速化し、防衛力を根本的に強化する」と明らかにした。
今回の骨太の方針に「5年以内」、「国内総生産の2%」以上など防衛費増額と関連した具体的な数字が明示されたのは、自民党内の激しい権力闘争の結果だ。当初、岸田首相は骨太の方針草案に具体的な目標数値を入れなかった。必要な武器などを検討した後、予算を決めるべきであり、金額から表示すれば、国民を説得するのは容易ではないと判断したためだ。岸田首相は先月31日、参議院予算委員会で防衛費と関連し、「(ジョー・バイデン大統領に)数字的なものは何も明らかにしていない。国民の生命と生活を守るために何が必要なのかを積み上げ、財源と共に年末に向けて議論する」と述べた。NATOの国防予算増額目標の例も、脚注にあったものが今回は本文に書き込まれた。
時事通信はこれと関連し、安倍晋三元首相が2日、「安倍派」の会合で骨太の方針中の防衛費と関連し、「原案に目標の規模や年限が書き込まれていたことに対し、『しっかり国家意思を示すべきだ』と注文を付けた」と報じた。結局「5年以内」を明示した修正案が出てくることになった。同通信は自民党関係者の話として、「安倍氏と対立すれば政権が安定せず、首相にとっては『忍』の一文字が続く」と報道した。
訳H.J