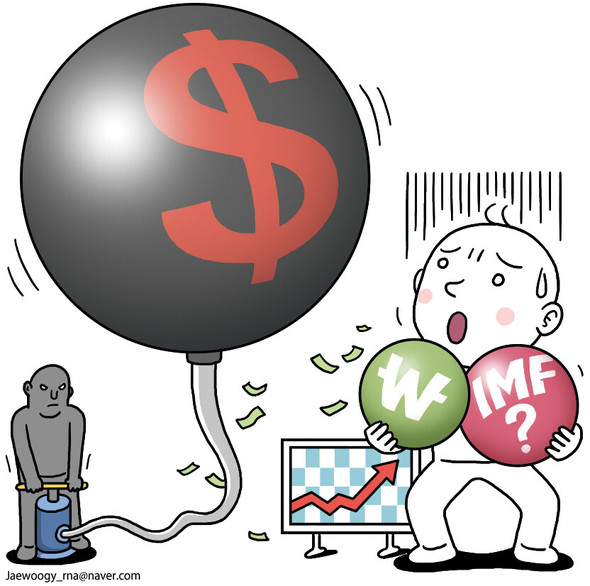今年は画家・李仲燮の生誕100年にあたる。日本のNHK・Eテレは「日曜美術館」という番組で李仲燮を特集し、私もコメンテーターとして出演した(2016年1月24日放映)。
私は2014年に『私の朝鮮美術巡礼』」を上梓したが、そこで李快大を論じた章に、つぎのように書いた。「日本留学から故郷に帰り、朝鮮戦争の際に北から南下して、避難生活の末に家族とも離別して狂死した李仲燮。解放後の南から日本に密航し、画家として社会的に認められ始めていた日本での生活を捨てて北に帰国し、消息不明となった曺良奎。朝鮮戦争の際に北の人民軍側に加担して釜山の捕虜収容所に拘束され、捕虜交換によって北へ行くことを選んだ李快大。かれら3人は、それぞれに秀でた才能をもつ画家だったが、それぞれの針路はこれほども極端に引き裂かれた。解放から70年近くたった現在もなお、李仲燮、曺良奎、李快大、3名の作品を一会場でまとめて展観することのできる展覧会すら開かれたことがないのだ。これら3人の画家が、植民地支配からの解放がすぐさま分断へと暗転したあの時代、「解放空間」と呼ばれているその時代をどのように生きたのか、それをどのように自らの芸術に投影させたのか、交錯するそれぞれの軌跡を照らし合わせて考えてみることは、「ウリ/美術」のコンテクストを理解する上できわめて重要な作業だ。」
これは私に残された「重い宿題」であると考えた。李仲燮は国内では「国民的画家」といわれるほどきわめて著名だが、私のように日本で生まれ育った者にとっては、それほどなじみ深い存在ではなかった。だが、この「宿題」に取り組む過程であらためて李仲燮に関心を抱き、済州島西帰浦の旧居にも行ってみた。文字どおり、猫の額ほどの小部屋でしかなかった。彼はそこで一家4人が食うや食わずの日々を過ごしたのだ。孤独死した彼の遺骨が埋められたソウル市忘憂里の墓地にも行ってみた。評論家の崔烈氏がこう書いている。「凍えひもじさに打ちのめされ死にいく李仲燮があまりに哀れで、こうして生き長らえる私が罪深く感じる」(「荒廃した世紀の激情」『画伝』)。私個人の感慨を一言でいうなら「哀切」という言葉に尽きる。この民族の運命そのもののように、哀切である。
彼に限らず、朝鮮民族の近代美術家たちについては一部を除いて日本ではほとんど知られていないのが現状であろう。その理由として、長年のあいだ近代美術を見たり論じたりする際に「一国的な枠組み」が先行してきたためであろう。最近になって、そのような狭く閉ざされた美術観に対する問題提起となりうる展示会が日本で開かれた。ひとつは2014年の「東京・ソウル・台北・長春――官展にみる近代美術」、もうひとつは2015年の「ふたたびの出会い、日韓近代美術家のまなざし―『朝鮮』で描く」である。いずれも日本の主要都市数か所を巡回した。批判点や注文がないわけではないが、かなり充実した内容であったといえる。後者では、曺良奎、李快大とともに李仲燮の作品も展示された。
日本で朝鮮の近代美術家があまり知られていないもうひとつの理由は朝鮮民族の側にある。民族が南北に分断されてすでに70年以上が経った。日帝植民地時代の2倍にもなる。この長すぎる分断は、美術史理解にも濃い影を投げている。昨年、ソウル市立美術館で大規模な李快大が開かれたが、曺良奎については本格的な個展はまだ開かれたことがない。北のどれくらいの人々が李仲燮を知っているだろうか?南のどれくらいの人々が曺良奎を知っているだろうか?彼の代表作は東京の国立近代美術館に所蔵されている。…南北の同胞とコリアン・ディアスポラとが一堂に会する展示を実現することすらできていないのだ。まして、ここに書いたような解放空間を交錯した3人の画家の作品をまとめて観ることのできる展示会は、国内ではまだ開かれていない。これでは、植民地期、解放空間、分断時代を通観する自らの美術史像を描くことはできないであろう。それが、ごく一部とはいえ、この3人の作品の同時展示が日本で開かれた「ふたたびの出会い」展で先行的に実現したのである。私はこのことを喜ぶと同時に、ソウルとピョンヤン(その両方)でこのような展示を行うことのできない現実を心からもどかしく思う。
李仲燮は1916年、朝鮮北部平安南道の富裕な地主の家庭に、3人兄弟の末っ子として生まれた。五山高校に学び、1934年に日本に渡って、帝国美術学校と文化学院で学んだ。ルオーに影響を受け、ボードレールやリルケの詩を好んで暗唱した。卒業後朝鮮に帰った李仲燮は、解放3か月前の1945年5月、彼を追って朝鮮に渡ってきた文化学院の後輩・山本方子(やまもと・まさこ)と結婚し、元山に居を構えた。朝鮮戦争が起きると、李仲燮は妻と2人の幼子をつれて南下し、釜山に避難、次いで済州島の西帰浦に逃れた。生活は困窮を極めたが、彼は子供たちを連れて浜辺に出かけた。画材を買うにも事欠いた彼はタバコの銀紙に太陽と海、蟹、活発に遊ぶ子供の姿などを描いた。
やがて生活苦に耐えかねた彼は、栄養失調と結核のために苦しむ妻を日本の実家に送り返した。一人になった李仲燮は、友人などを頼って国内各地を転々としながら制作をつづけ、1955年1月にはソウルの百貨店で個展を開いたが、その直後から精神を病み、健康をひどく害して、1956年9月6日、孤独のうちに世を去った。このような最期はゴッホやモジリアーニのそれを連想させる。異なるのは、そこに植民地支配、民族分断、戦争の影が濃くさしていているという点だ。日本人妻との別離も、そうした歴史を反映している。
なお、方子夫人は今もお元気で、今回の「日曜美術館」にも出演された。番組は自然に李仲燮とその家族の愛と離別に焦点を当てたものになったのだが、私としては次の点を付け加えて強調したかった。
李仲燮は牛を多く描いた。日帝時代日本に留学していた朝鮮人画学生たちが「白牛会」というグループを結成したことがある(1933年)。「白」という色も、「牛」も、彼らの民族的なアイデンティティを表す意味を持っていた。国を失い、故郷や家族とも離れているが、自らを失わずに生きたいという、ささやかな願いの表現ともいえるだろう。とくに政治的に尖鋭な意識で結集したというものではなく、ゆるやかな互助的な組織だったと見てよいでしょう。しかし、このグループ名を、日本当局が問題視し、結局、「在東京美術協会」という名称に変更することを余儀なくされたという。みずからの民族的アイデンティティを自由に表明することすら許されなかったのだ。植民地支配から解放され、ようやく気兼ねなく「牛」を描くことができる状況が到来した。民族が分断されず、朝鮮戦争が起こらなければ、画家は「牛」を描き続け、家族とともに平穏な日々を得たかもしれない。しかし、現実はそうはならなかった。
李仲燮は、いうならば「難民画家」である。すべてを失って「難民」となりながらも絵を描き続ける、いったい何のためなのか、そもそも人間という存在にとって芸術するという行為は何を意味するのか。そういう問いに私たちを向かい合わせるのが李仲燮だ。芸術に人生を捧げた画家たちの中には、栄誉や富を得ることどころか、生き残ることそのものよりも、「芸術する」ことの価値を上におく人たちが存在する。貧窮、病苦、社会的不遇という経験は珍しいものではない。李仲燮は、そういう存在だと思う。韓国の多くの人々が彼の生涯と作品に自らの物語を重ねてみる、それが彼の作品が愛されている理由だろう。「難民」となった画家が、極度の貧窮の中で、便所で拾ったタバコの銀紙に釘で刻み付けた絵。なんとささやかで、みすぼらしいことか。しかし、そこの描かれた世界は、親密で、エロスに満ち、ユーモラスでもある。じっと見ていると、かすかに狂気をおびた究極のユートピア像とも思えてくる。妻子と一緒に日本に来て暮していれば、もうすこし長く生きられただろうに、という人もいる。だが、そうだろうか? 拾った銀紙にでも描いて、描いて、描き抜くということが、彼の「生きる」ということだった。過酷な状況であればあるほど、絵を描くことが彼の「生」そのものだったのだ。それは日本という場所で暮らすことでは満たされない、芸術的欲望だったのだと私は思う。そこに、この画家の独自性と普遍性がある。

いまも全世界に「難民」が溢れている。国家の保護の外に放り出され、ただ生きるために荒れ野を素足でさまよう人々。その中に、李仲燮のような人たちがかならずいるだろう。李仲燮を哀惜することのできる人々ならば、これら無数の人々の苦難に共感することができるはずだ。そう思いたいのだが…。
韓国語原文入力:2016-02-18 19:55