その医者は内蔵が飛び出した患者の腹に指を突っ込んでいた

ドタバタと他病院の医者たちが
手術台を引いてなだれ込んできた
内蔵が飛び出した患者
患者に寄り添う医者の手は
なんと患者のお腹に入っている
腹を引き裂いた刃物は横隔膜をも裂いていた
心臓まで及んだ刺傷
手術はもう始まってしまった
一般医じゃ心臓は手に負えない
そこには胸部外科すら無かった
苦悩の末、彼が下した決断は…
1989年、とある日曜日の出来事だった。その時わたしは、ソウル新村にあるセブランス病院で働いているレジデントとして二年目を迎えていた。当時、セブランス病院は今のように新式の建物では無かった。ERは一階の外来棟の横に、ひっそりと立っていた。
私はERで患者を診た後、応急ステーション(医者やナースが処方を施した後、診療を記録するなど行政を行う場所)の前に立ち、ついさっき診た患者のカルテに診療内容を書き込んでいた。ドタバタと音がして、いきなりERの扉がものすごい勢いで開いた。『どうやら急患が入ったようだな』と、顔を上げた私は、とても驚くべき光景を目のあたりにした。なんと、緑のオペ着を纏った医者が6人、ベットに患者を乗せて押し掛けて来たのだった。実に物凄い光景だった。その医者たちは、『こっち』の病院の所属ではなかった。他の病院の服を着ていたのだ。他の病院の医療スタッフが、オペ着のままERに入ってくるのを初めて目にした私は、ビックリして彼らから目を離す事ができなかった。
1989年のある日曜日。いつもと違う、ERの風景
見慣れない医者たちが現れ、ERはざわめいた。もっと良く見てみることにした。一人の患者に6人の医者が取りついていた。二人は前と後ろでベットを担ぎ、二人は手に点滴注射を持って後を追っていて、一人は患者の口に人工呼吸器をあてがっていた。残った一人の医者は何をやっているのか、患者の横にピッタリと寄り添っていた。
チラッと除菌シートが覆い被さっている患者の胸が見えた。視線を背けたいほど酷い状態だった。腹部の内蔵がほとんど外に飛び出していたし、はみ出した腸を除菌シートが覆いきれない状態だった。はみ出した腸を包む除菌シートを、点滴を持った医者が掴んでいた。ところで患者の横にいた医者の手は腹の中に入っているのが見えた。
『あぁ、オペ中に事故か。大変だなぁ、一般医は』
私はまた踵を返して、途中で止まっていたカルテの続きを書き始めた。腹部の手術は胸部外科とは関係のない一般外科の領域だったからだ。
だが、その時。ERになだれ込んできたオペチームの一員が私の後ろを通り過ぎながら、なんと、「ここにどなたか胸部外科医の方はいらっしゃいませんかー!」と大声で叫んだのである。胸部外科医?腸がはみ出してるのに?
「私、胸部外科の研修医ですが。」
びっくりした私は振り返りながら答えた。彼は喜々とした表情で私に向かってきた。
「助かりました!早くこの患者を診てください。どうやら心臓を刃物で刺されたみたいで」
心臓?
患者は40代後半の男性だった。弟と口喧嘩をしていた最中に、段々と大事へ転じていったらしい。弟が刃物を振り回し、兄は腹部を刺された。そしてすぐ近所にある総合病院のERに運ばれたのだと言う。患者は出血症状を起こしていた。1分でも早く出血を止めなければならなかった。
腹部を深く刺された事を確認したその病院の一般外科の医者は、すぐに応急手術に取り掛かった。しかし、腹を開けてみたところ、出血は腹の中の臓器ではなく横隔膜から起きていたと言うのだ。横隔膜というのは、腹と胸の間を横切る筋肉で出来た膜のことである。人が立っているときで例えると、心臓と二つの肺が横隔膜の上に置かれているようなもので、横隔膜にケイレンが発生するときに起きるのがしゃっくりだ。横隔膜は2ミリよりも薄い厚さの筋肉で出来ているのだが、患者の場合、下から侵入してきた刃物によって、その横隔膜が少し破れていて、その破れた部位から血が流れている状況だった。
オペを執刀した外科医は、横隔膜を通じて血が流れていたので、まず右の人指し指を押し込み出血を止めた。ズブリと押し込まれた医者の手から心臓の脈動する感覚が伝わってきた。彼はすぐに、血は刃物で刺された心臓から流れていると直感した。最初に刃物は腹部を刺したけど、切っ先が上を向いたことによって刃物が横隔膜を破り、心臓の右心室を傷付けたのだと確信した。心臓から出る血が、穴の空いた横隔膜を通じて排出されていたのだ。
医者は悩み始めた。とりあえず出血は指で止めた。が、指を抜けないことが問題だ。それに彼は腹部手術を専門とする一般外科医だった。胸郭のオペは全く経験がない。せいぜい医科大学の学生だったときに見学した位が全てだ。もし、心臓の出血を放っておき、横隔膜だけを縫ってしまえば、どうなるだろうか?そのあと腹腔からの出血は無くなるだろう。しかし、血が心臓の回りに溜まっていき、まもなく患者は死亡するはずだ。それでは方法は?胸を開いて、心臓の出血部位を探し、縫うしかない。しかし、その総合病院に心臓手術を執刀出来る胸部外科医はいなかった。胸部外科の専門医を雇えるほど規模の大きな病院ではなかったのだ。
素直に誤診を認めた彼に脱帽した
指を横隔膜の中へ差し込んでいる彼の頭の中では様々な思考が駆け巡った。どうすればいいのか。彼は心臓の出血を指で止めている、その間に、他の病院で働く胸部外科医を呼ぶことも考えた。しかし応急事態の中で他の病院の医者を呼び出す事は、そんなに簡単なことでは無い。それに、その日は日曜日だった。他の病院の緊急コールを受けてすぐ医者を探し、送り出してくれるという保証もなかった。結局、彼は患者をオペの最中、そのまま近所の大学病院に運ぶという決断を下した。微かな希望に運命を委ねてしまったら、患者を亡くしてしまうかも知れない。そう考えたからである。保護者を呼び、状況を説明した後、執刀チームがオペを進めていた状態そのままで私が働いていた新村セブランス病院に患者を運んできたのだった。血の滲み出る心臓を、指で塞いだまま。
後で彼に「なぜ先に連絡を取らずに患者を運んできたのか」と訊いた。その言葉に彼は、「『来るな』と言われるかも知れないから」と答えた。ともかく彼は患者の腹に指を突っ込んだまま、この病院のオペ室へと移動した。手術が始まり、その外科医の人指し指は我々のオペチームの指に変わった。担当医が代わりに右心室を指で塞いでいる間、勤務4年の専門医が電動ノコギリで胸を開いた。開かれた胸から心臓が現れた。予想通り刃物は右心室を刺しており、専門医の指も正しくそこを塞いでいた。
実を言うと心臓の縫合は胸部外科の専門医からしてみれば、わりと簡単な方である。高度の専門的な手術で様々な心臓疾患を治す胸部外科医にとって、心臓を『縫い合わせる』くらいは簡単な手術だからだ。
オペ室で行われた次の処置は簡単だった。出血を防ぐため、担当医は指で出血部位を塞ぎ続けた。それと同時に他の医者がテフロンパッチ(糸の圧力で組織が傷むことを避けるために先に当てておくパッチ)を心臓に当てた後、ナイロン製の糸で出血部位の回りを縫い合わせた。そして最後には指を抜きながら、巾着の紐を絞めるように出血部位を纏めた。出血はピタリと止まった。幸い、その患者は入院してから約十日後、感染も余病も無く、無事退院した。
その事は記憶の奥底に深く刻まれる事件となった。胸部外科医の中でもしばらくの間、最初に執刀した勇気ある一般医の話題で持ち切りだった。逸早くその患者を診た一般医の速やかな判断と勇気が患者を救ったのだ、と。
考えてみて欲しい。最初に腹を開けた時、横隔膜を通じてドクドクと心臓から血が流れているという予想外の事態に、その一般医はかなり戸惑ったはずだ。心臓を手術出来る胸部外科医がいない状態で、その医者はどうするべきだったのだろうか? 片手で勢いよく流れる血を止めながら、彼は『手術外の要素も含めて』するべき判断を下した。休日に、他の大学に連絡を取って医者を送って欲しいと頼んだら、来るだろうか? 逆に、いま患者を送るから貰い受けて欲しいという方法はどうだ? どっちも難しいと判断した彼はそんな手順より、ただ『なだれ込む』方法を選んだのだ。
彼の行動の中でもっとも輝く部分は、ただ患者を救うため、自分の『誤診』を認めて保護者たちに全てを話した後に患者を大学病院のERに連れ込んだ勇気だった。考えれば考えるほど彼の賢明な対処に頭が下がるばかりだ。もし彼が誤診を認めたくないために、適当に横隔膜だけを縫い腹を閉じていたら、患者は死亡し、家族も多分その事実を解らないままだったはずだ。保護者に『最善を尽くしたけど、亡くなってしまった』とウソをついても、医学的常識の無い保護者は真実を知る由もない。彼の勇気ある選択のおかげで患者も助かり、患者の弟も『人殺し』にならずに済んだ。患者だけではなく彼の弟まで二人を助けたのだ。
ダムの穴を塞いだと謂われるオランダの少年のごとく
誰もが水が洩れるダムの穴を指で塞いで崩壊を止めたという『オランダの少年』の話を知っているはずだ。学校の帰りにハンス・ブリンカーという少年がダムに小さな穴が開いているのを発見した。海から街を守ってくれているそのダムから水が洩れて、もし崩れたりしたら街は水浸しになるだろう。少年は鞄を投げ捨てて指で穴を塞いだ。最初はほんの小さな穴だったが、時間が流れるにつれてだんだん大きくなる穴を少年は腕で塞いで、だんだん大きくなる穴と水の圧力にそれ以上耐えられなくなったとき、街の人達が駆け付けて少年を助けたという話だ。オランダのスバーンダムに銅像も立っているし、韓国の教科書にも乗っている実話として知られているが、この話は実を言うと1865年にメアリー・メイプス・ドッジの書いた『銀のスケート-ハンス・ブリンがーの物語』に出てくる童話の一つだ。
オランダの少年の話は作り話だが、私が経験した外科医の話は本当にあった話だ。私は今もその外科医の決意に満ちた目を覚えている。もちろん、患者の前で医者が真の勇気を出すことは誉められるべき事ではなく、当然のことだ。この至極当然な事がなかなか起きないのが現状の医療実態である。医者への信頼と尊敬が消え、医者への非難が声援を受ける世の中になった。もっとも責任があるのは信頼を失った医者達だ。そして我々は、りっぱな医者を見出し、育てる社会の制度も綿密に調べるべきだ。もし、弟の刃物に刺された患者が、この勇敢な医者に会うことができず、卑怯な医者に会ってしまったら、兄弟の運命はどうなっていただろうか?命の危機に晒された患者の運命が、どの医者に出合ったかで左右されてはならないはずだ。それが医療の特殊な所であり、全ての医者がりっぱであるべき理由でもあり、全ての医者がりっぱな医者に成長することができる制度が必要な理由でもある。
整理:ナム・ジョンヨン記者 fandg@hani.co.kr
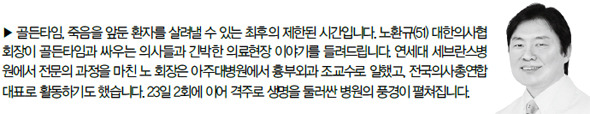
韓国語原文入力:2013/03/08 09:58

