пј»еҜ„зЁҝпјҪгғҮгғўгӮҜгғ©гӮ·гғјгҒҜи¬ҷиҷҡгҒ•гҒ§ж „гҒҲгӮӢ
жЁ©еҠӣгӮ’жҸЎгҒЈгҒҹдәәгҖ…гҒҢдёҚйҒ“еҫігҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮдәәй–“гҒ§гҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒжЁ©еҠӣгӮ’дҪҝгҒҶдәәиҮӘдҪ“гҒҢе®ҢгҒәгҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҖӮе®ҢгҒәгҒҚгҒ§гҒӘгҒ„гҒҢгӮҶгҒҲгҒ«з”ҹгҒҳгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’гҖҒжЁ©еҠӣиҮӘгӮүгҒҢж–ӯзҪӘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮеҲ°еә•жңӣгӮҒгҒӘгҒ„и©ұгҒ гҖӮиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒҜвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒ гҒӢгӮүгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘд»•дәӢгӮ’гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢиҮӘеҲҶгҒ®дҝқиӯ·гҖҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰжЁ©еҠӣгӮ’гҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒҫгҒ§иӘӨгғ»д№ұз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ
гҖҖгҖҢи‘ӣи—ӨгҒҢгӮҲгӮҠж·ұгҒҫгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒгҒ“гҒ®и‘ӣи—ӨгҒ®ж №е…ғгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҳҺзўәгҒ§ж•ҙзҗҶгҒ•гӮҢгҒҹиҰӢи§ЈгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜжҠҪиұЎгҒ®ж°ҙжә–гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢд»–гҒ«гҒӘгҒ„гҖҚгҖӮзұіеӣҪгҒ®е“ІеӯҰиҖ…гҖҒгӮёгғ§гғігғ»гғӯгғјгғ«гӮәгҒ®иЁҖи‘үгҒ гҖӮдәүгҒҶдәәгҖ…гҒҢгҖҒеёёгҒ«дәүгҒ„гҒ®зҗҶз”ұгӮ’жҳҺзўәгҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮиЎЁйқўгҒ«зҸҫгӮҢгҒҹзҗҶз”ұгҒҜгӮҲгҒҸеҲҶгҒӢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒзҡ®зӣёзҡ„ж°ҙжә–гҒ§гҒ„гҒҸгӮүж”»йҳІгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгӮӮзӯ”гҒҜеҮәгҒҰгҒ“гҒӘгҒ„гҖӮжң¬еҪ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒ®вҖңж №е…ғвҖқгҒ«гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ гҖӮ
гҖҖж–ҮеңЁеҜ…(гғ гғігғ»гӮёгӮ§гӮӨгғі)ж”ҝжЁ©гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи©•дҫЎгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢдәүгҒ„гӮӮгҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®дәүгҒ„гҒ®ж №е…ғгҒҢгҖҒзӣёеҪ“йғЁеҲҶгҒҜжЁ©еҠӣгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжЁ©еҠӣиҰігҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮжҠҪиұЎгҒ®ж°ҙжә–гӮ’дёҖж®өйҡҺй«ҳгӮҒгҒҰгҖҒгҒҫгҒҡжЁ©еҠӣиҰігҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӯ°и«–гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒдәүгҒ„гҒ®вҖңз”ҹз”ЈжҖ§вҖқгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ®гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒӘгӮүгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ«йӣҶдёӯгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖдәәй–“гҒҢзӨҫдјҡз”ҹжҙ»гӮ’гҒҷгӮӢд»ҘдёҠгҖҒжЁ©еҠӣгҒ®ж”Ҝй…ҚгӮ„зөұжІ»гҒҢгҒӘгҒ„дё–гҒ®дёӯгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒҢгҒҹгҒ„гҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹдё–гҒ®дёӯгӮ’еӨўиҰӢгӮӢдё»ејөгӮ„зҗҶи«–гҒҜеӨҡгҒҸеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒгҒҫгҒ еӨўгҒ«з•ҷгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзҸҫе®ҹзҡ„гҒ«жңӣгӮҖгҒ®гҒҜвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒ гҒҢгҖҒжЁ©еҠӣдё»дҪ“гҒҢиҮӘгӮүвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҺІгҒ’гӮӢгҒ®гҒҜгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰеҚұйҷәгҒ гҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢиҮӘеҲҶгҒҢгӮ„гӮҢгҒ°гғӯгғһгғігӮ№гҖҒд»–дәәгҒҢгӮ„гӮҢгҒ°дёҚеҖ«гҖҚпјҲдәәгҒ®иЎҢзӮәгҒҜйҒҝйӣЈгҒ—иҮӘеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜеҗҲзҗҶеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁпјүгҒЁгҖҢд»–дәәгҒ®гҒӣгҒ„гҖҚгҒ®йҖҡдҫӢеҢ–гӮ’з”ҹгҒҝгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ гҖӮ
гҖҖж°‘дё»дё»зҫ©гҒҜвҖңжӮӘгҒ„жЁ©еҠӣвҖқгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҖӮжЁ©еҠӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзө¶гҒҲгҒҡз–‘гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҖӮдёүжЁ©еҲҶз«ӢгӮ’йҖҡгҒ—гҒҹзӣёдә’зүҪеҲ¶гҒЁзӣЈиҰ–гҒ“гҒқгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹвҖңз–‘гҒ„гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ вҖқгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиғҪзҺҮгҒЁеҠ№зҺҮгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸиҗҪгҒЎгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹиІ»з”ЁгӮ’иІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжЁ©еҠӣгҒ®иӘӨгғ»д№ұз”ЁгҒҢеӨ§иҰҸжЁЎгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮҲгӮҠгҒҜгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«иүҜгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢж°‘дё»дё»зҫ©дҪ“еҲ¶гҒ«жҡ®гӮүгҒҷдәәгҖ…гҒ®жҡ—й»ҷгҒ®еҗҲж„ҸгҒ гҖӮ
гҖҖжЁ©еҠӣгӮ’жҸЎгҒЈгҒҹдәәгҖ…гҒҢдёҚйҒ“еҫігҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮдәәй–“гҒ§гҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒжЁ©еҠӣгӮ’дҪҝгҒҶдәәиҮӘдҪ“гҒҢе®ҢгҒәгҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҖӮе®ҢгҒәгҒҚгҒ§гҒӘгҒ„гҒҢгӮҶгҒҲгҒ«з”ҹгҒҳгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’гҖҒжЁ©еҠӣиҮӘгӮүгҒҢж–ӯзҪӘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮеҲ°еә•жңӣгӮҒгҒӘгҒ„и©ұгҒ гҖӮжЁ©еҠӣгҒ®дёҖж¬Ўзҡ„гҒӘзӣ®жЁҷгҒҜгҖҢиҮӘеҲҶгҒ®дҝқиӯ·гҖҚгҒ гҖӮиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒҜвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒ гҒӢгӮүгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘд»•дәӢгӮ’гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢиҮӘеҲҶгҒ®дҝқиӯ·гҖҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰжЁ©еҠӣгӮ’гҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒҫгҒ§иӘӨгғ»д№ұз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ
гҖҖгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒҶгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е •иҗҪгҒ—жІЎиҗҪгҒ—гҒҹвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒҢдәәйЎһгҒ®жӯҙеҸІгҒ«гҒҜз„Ўж•°гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢжЁ©еҠӣгӮ’жҸЎгӮӢгҒЁдәәгҒ®и„ігҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒҜзңҹе®ҹгҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮгҖҢжЁ©еҠӣгҒҜи…җж•—гҒ—гҖҒзө¶еҜҫжЁ©еҠӣгҒҜзө¶еҜҫзҡ„гҒ«и…җж•—гҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒгӮҸгҒ‘гӮӮгҒӘгҒҸеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹи…җж•—гҒ®йҒҺзЁӢгҒҜгҖҒжЁ©еҠӣиҖ…иҮӘгӮүгҒҢиӯҳеҲҘгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ»гҒ©зӣ®гҒ«иҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«йҡ еҜҶгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖгғ•гғ©гғігӮ№гҒ®е“ІеӯҰиҖ…гҖҒгӮўгғігғӘгғ»гғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гҒҜгҖҢж—ҘеёёгҒ“гҒқгҖҒгҒқгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®йқ©е‘ҪгҒҢеӨұж•—гҒҷгӮӢеҺҹеӣ гҒ гҖҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮж”№йқ©гӮӮеҗҢгҒҳгҒ гҖӮж”№йқ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҢз©ҚејҠжё…з®—гҖҚгӮ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮиүҜгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢиҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘйӣЈй–ўгҒҢдёҖгҒӨгҒӮгӮӢгҖӮж§ӢйҖ е•ҸйЎҢгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҶгӮӢз©ҚејҠгӮ’гҖҒ擬дәәеҢ–гғ»еҖӢдәәеҢ–гҒ—гҒҰдәәгӮ’дёӯеҝғгҒ«жё…з®—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒж—ҘеёёгҒ®й ҳеҹҹгҒ§гҒҜдәӢе®ҹдёҠгҖҢе‘іж–№гҒ®еғҚгҒҚеҸЈгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢж—ўеҫ—жЁ©дәүеҘӘжҲҰгҖҚгҒ«и»ўиҗҪгҒӣгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ гҖӮ
гҖҖж”№йқ©гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹгӮҠж”ҜжҢҒгҒҷгӮӢдәәгҖ…гҒҜгҖҒеҪјгӮүгҒҢж”№йқ©гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„еҜҫиұЎгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮӢдәәгҖ…гӮҲгӮҠе–„гҒ§гҒӮгӮҠжӯЈзҫ©гҒ®дё–з•ҢиҰігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®ж•ҷиӮІгҒӢгӮүдёҚеӢ•з”Је•ҸйЎҢгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§ж—ҘеёёгҒ§гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢгҒҳдәәгҖ…гҒ гҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҗҶз”ұгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҪјгӮүгҒҜе–„гҒЁжӯЈзҫ©гҒ«е‘ҪгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиӘҮејөгҒ•гӮҢгҒҹгғ¬гғҲгғӘгғғгӮҜгӮ’й§ҶдҪҝгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮҢгҒ°гҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒж—ҘеёёгҒ§еҪјгӮүгҒҢиҰӢгҒӣгӮӢиЎҢеӢ•гҒЁгҒ®гӮ®гғЈгғғгғ—гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ гҖӮ
гҖҖгҖҢж—ўеҫ—жЁ©дәүеҘӘжҲҰгҖҚгҒ®з–‘жғ‘гӮ’еӣһйҒҝгҒ§гҒҚгӮӢдәәдәӢгӮ’гҒҷгӮҢгҒ°гҒқгҒ®йӣЈй–ўгӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№жі•гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮж”№йқ©еӢўеҠӣгҒҜе–„гҒЁжӯЈзҫ©гҒ®еҗҚгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«дәәзү©гҒ®йҒҺеҺ»гҒЁгӮігғјгғүгӮ’е•ҸгҒ„и©°гӮҒгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢдәӢгӮ’иҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ гҒ‘гҒ§зӢ¬еҚ гҒ—гҒҰгҒ“гҒқж°—гҒҢжёҲгӮҖгҖӮеҪјгӮүгҒ®еҚ‘гҒ—гҒ„гҒӘж—ҘеёёгҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒҹгҒігҒ«гҖҒеҪјгӮүгҒҜиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ«жңүеҲ©гҒӘгӮҲгҒҶгҒ«еҘҪжҲҰзҡ„гҒӘгҖҢиӯ°йЎҢеҶҚиЁӯе®ҡгҖҚгҒ®з·ҸеҠӣжҲҰгӮ’иЎҢгҒҶгҒҢгҖҒдёҖжҷӮзҡ„жҲҗеҠҹгҒҜгҒҠгҒ•гӮҒгҒҰгӮӮ究жҘөзҡ„гҒ«гҒҜвҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒ®еҒҪе–„гҒёгҒ®е№»ж»…гӮ’з…ҪгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖзўәе®ҹгҒ«вҖңе–„иүҜгҒӘжЁ©еҠӣвҖқгҒ«гҒӘгӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҒӘгӮүгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮи¬ҷиҷҡгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ“гҒқз–ҺйҖҡгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғһгӮӯгғЈгғҷгғӘгҒҜгҖҢи¬ҷйҒңгҒҜз„ЎзӣҠгҒӘгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒжңүе®ігҒӘгҒ гҒ‘гҒ гҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜ500е№ҙеүҚгҒ®дё–гҒ®дёӯгҒ®и©ұгҒ гҖӮд»Ҡж—ҘгҒ®ж°‘дё»дё»зҫ©гҒҜи¬ҷиҷҡгҒ•гҒ§ж „гҒҲгӮӢгҖӮгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ®ж”ҝжІ»еӯҰиҖ…гҖҒгӮёгғ§гғігғ»гӮӯгғјгғігҒҢгҖҺгғҮгғўгӮҜгғ©гӮ·гғјгҒ®з”ҹгҒЁжӯ»гҖҸгҒ§еҠӣиӘ¬гҒ—гҒҹж¬ЎгҒ®дё»ејөгӮ’иғёж·ұгҒҸеҲ»гҒҫгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҖгҖҢгғҮгғўгӮҜгғ©гӮ·гғјгҒҜи¬ҷиҷҡгҒ•гҒ§ж „гҒҲгӮӢгҖӮи¬ҷиҷҡгҒ•гҒҜгҖҒж…ҺгҒҫгҒ—гҒҸзҙ зӣҙгҒӘжҖ§ж јгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеұҲеҫ“гҒЁзө¶еҜҫгҒ«ж··еҗҢгҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгғҮгғўгӮҜгғ©гӮ·гғјгҒ®жңҖгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒӘеҫігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӮІж…ўгҒӘиҮӘе°ҠеҝғгҒ®и§ЈжҜ’еүӨгҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒЁд»–дәәгҒ®йҷҗз•ҢгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰиӘҚгӮҒгӮӢиғҪеҠӣгҒ гҖҚ
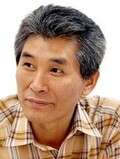
иЁіJ.S