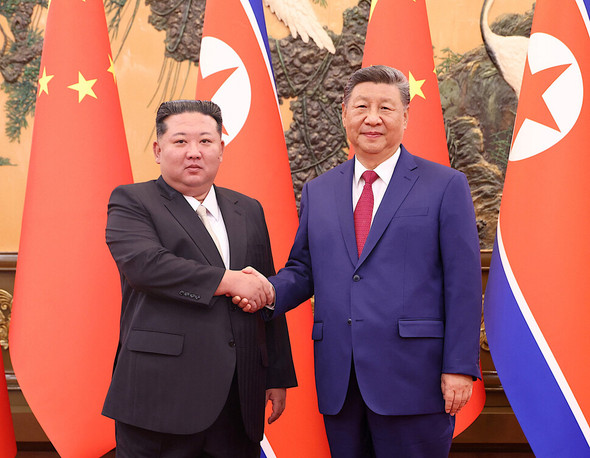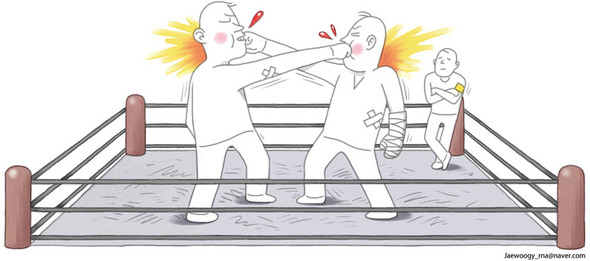去る2012年1月、キム・某氏はある産後養生院と4週間250万ウォンで産後養生を受ける契約をした。 彼女は7ヶ月後に出産するや産後養生院に入った。 現金で全額を支払ったが、産後養生院でことによると不利益を受けるかと思い、現金領収書を切ってくれとは言えなかった。 翌年初めに年末精算をして医療費控除を受けなければならなかった。 キム氏はこの時、管轄税務署に取引事実を証明できる書類とともに産後養生院の現金領収書未発給事実を申告した。 税務署は産後養生院に取引代金の半額にあたる125万ウォンを過怠料として賦課した。 キム氏は50万ウォンの報奨金を受け取った。
24日、国税庁は来月から現金領収書の発行を義務とする基準金額を現行30万ウォンから10万ウォンに拡大することにした。 キム氏の事例のように、業者が現金領収書を発行しなければ取引代金の50%に達する過怠料が決められる。申告者には未発給金額の20%以内で報奨金(1件当たり100万ウォン、年間500万ウォン限度)が支給される。 国税庁は「取引の相手方(顧客)が現金領収書を要求せず人的事項が分からない場合にも事業者が国税庁指定電話番号(010-000-1234)で取引日から5日以内に発行しなければ、過怠金を納めなければならない」と明らかにした。 現金領収書未発給を条件に価格を値引いた場合にも業者に過怠料が賦課され、申告者には報奨金が支給される。
すべての事業者が現金領収書を義務発行しなければならないわけではない。 これを適用される業種は、所得税法施行令に明示されているが、教育サービス業(一般教習および芸術学院など)、保健業(総合および一般、歯科、漢方医院など)、事業サービス業(弁護士、会計士、税理士など)、飲食宿泊業(一般遊興酒屋など)等、50業種余りに達する。 国税庁は現金領収書発行義務事業者が約47万人に達すると明らかにした。
来月から電子税金計算書の発行義務対象者も個人事業者の場合、前年度の売上額(付加価値税除外金額)が10億ウォン以上から3億ウォン以上に拡大する。法人事業者は2011年から全て義務的に電子税金計算書を発行しなければならない。 これに違反すれば、違反理由により少なくて取引代金の0.1%から、多くて2%に達する加算税を納めなければならない。 国税庁は「高所得自営業者の課税標準(税金を賦課する際に基準となる所得)を陽性化し、取引の透明性を高める」と明らかにした。 リュ・イグン記者 ryuyigeun@hani.co.kr
訳J.S(1212字)