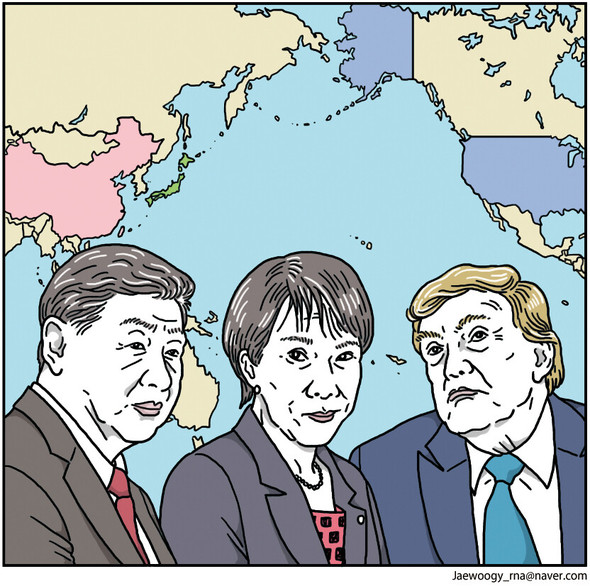[ニュース分析]非核化関連し金委員長がいかなる発言したかが最大のカギ
「核・ミサイル試験発射の猶予」明らかにした場合
朝米対話局面に入る見込み
「南北関係には積極的、朝米対話には消極的」の場合は
政府が米国を説得するのが困難になる可能性も
「韓米合同軍事演習の中止」だけ要求した場合は最悪

北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)労働党委員長が5日午後、平壌に到着した文在寅(ムン・ジェイン)大統領の対北朝鮮特使団と直ちに面会し、晩餐を共にした。予想よりも素早い行動だ。この場で、いかなる議論が行われたかはまだ明らかになっていないが、特使団が伝えたメッセージに対する金委員長の返答が、今後の朝鮮半島情勢の行く末を決める方向舵(ラダー)になるものとみられる。
特使団が平壌(ピョンヤン)に持って行ったメッセージは、大きく分けて二つだ。特使団は「朝鮮半島問題の本質的解決と持続可能な南北関係発展の環境作り」(チョン・ウィヨン首席特使)を進める一方、「朝鮮半島の非核化の進展に向けた朝米対話への進入を牽引するのに焦点を合わせる」(ペク・テヒョン統一部報道官)ものとみられる。
カギとなるのは、これに対する北側、特に、金委員長の反応である。彼がいかなるメッセージを送るかによって、今後朝鮮半島情勢が朝米接触を含めた対話局面に入ることも、停滞状態にとどまることも、緊張局面に後退することもあり得るからだ。
専門家らが挙げた最善のシナリオは、金委員長が非核化問題と朝米対話について“大胆に”応える場合だ。非核化を朝米交渉の“出口”にすると金委員長が明示的に明らかにした場合、米国としては対話を拒む名分を失うことになる。金正日(キム・ジョンイル)総書記時代から、北朝鮮は、非核化問題について「朝鮮半島の非核化は先代の遺訓」という表現を使ってきた。
金正恩委員長が、「南北対話が続いている間は、核・ミサイルの試験発射を猶予する」ことを明確にした場合、それもまた“好材料”と言える。米国側が朝米対話の前提に掲げてきたいわゆる「非核化に関する実質的な措置」(という条件)を満たすことができるからだ。核・ミサイル実験の凍結は一種の“技術的凍結措置”に当たる。「国家核武力の完成」を政治的に宣言した北朝鮮が、核・ミサイル技術水準をさらに進展させなければ、米国としては北朝鮮の核・ミサイルが本土が脅かす時期を遅らせる結果を得られる。
これに対する専門家の見通しは分かれている。チョ・ソンニョル国家安保戦略研究院首席研究委員は「特使団に非核化の原則を明らかにし、今後の南北首脳会談で核・ミサイルの凍結を表明する2段階が最善」だとし、「逆に、特使団を通じて核・ミサイル実験の凍結を宣言し、首脳会談で非核化原則を明らかにするのが次善策かもしれない」と指摘した。とりあえず、二つのうち一つでも引き出せば、対米説得に乗り出せるという意味だ。一方、キム・ヨンチョル仁済大学教授は「北朝鮮は、現水準で核・ミサイル技術を凍結させることを対話の条件ではなく、米朝対話の結果にすべきだと考えているだろう」と話した。核・ミサイル実験の凍結は交渉の“カード”であって、“前提”ではないという意味だ。
金委員長が南北関係に積極的に取り組む一方、非核化と朝米対話などについては抽象的なレベルの言及にとどまった可能性も排除できない。「米国と対話する用意がある」や「南北が朝鮮半島の状況を平和的・安定的に管理していこう」など、従来の言及を繰り返したり、様々な前提条件を掲げることも考えられる。この場合は、米国が対話に乗り出すのが難しく、政府の対米説得も困難になる公算が高い。北朝鮮が抑留している韓国系米国人3人の解放の可能性を特使団にほのめかしたかもしれないが、米国が非核化問題と人道的問題を連携させない可能性が高いことから、朝米間の「探索的対話」の入り口にするのは難しい。
金委員長が南北関係の重要性を強調し、韓米合同軍事演習と関連して、逆に韓国側に明確な立場表明を要求した最悪の状況も想定できる。ただし、平昌(ピョンチャン)五輪を契機に、南北の最高指導者が“間接対話”をする方法で目下の情勢を作り出したことから、このようなやり方で和解ムードを台無しにする可能性は低い。ク・カブ北韓大学院大学教授は「非核化と関連した北側の発言を公式的に確保するのが特使団の訪朝目的」だとし、「米朝対話のための妥協点が見つかっていないこと自体が最悪の状況」だと話した。
訳H.J