
米国独立記念日の7月4日、ワシントンのホワイトハウス上空をB2ステルス爆撃機がF35戦闘機の護衛を受けながら飛行した。ドナルド・トランプ大統領は爆撃機に挙手をして敬礼をした。この爆撃機は先月、イランの核施設を爆撃したまさにその機種だ。トランプ大統領はさらに、自身が命名した「一つの大きくて美しい法案」(OBBBA)という滑稽な名前の法案の署名式を開いた。同法には「MAGA」(米国を再び偉大に)公約を実行する実弾が含まれている。トランプ大統領は「民主主義の誕生日に民主主義の勝利を示すもの」だとしたうえで、「この法が米国をロケット船へと変えるだろう」と述べた。米国経済がロケットのように上昇するという意味だ。まるで軍事パレードをしながら功績を誇る第3世界の独裁者を見ているようだ。
トランプ大統領の主張はその大半が大ぼらだ。同法には問題が多く、共和党議員にさえ反発されたが、「反対する議員の再選を阻止する」と脅迫するなど、ほぼ強引に可決した。主に富裕層に恩恵が与えられる4兆5千億ドル(約650兆円)規模の減税、不法移民取り締まりのための国境障壁と監禁施設の建設、敵国の弾道ミサイルから米国本土を防御するためのゴールデンドームの構築などが盛り込まれた。代わりに財源調達のためメディケイド(低所得層の健康保険)やフードスタンプ(低所得層の食料品支援)など福祉予算を削減し、再生可能エネルギー補助金を縮小または廃止した。だが、それでも間に合わず、大規模な国債を発行せざるを得ない。そのために連邦政府の負債限度を5兆ドルも増やした。
この法は民主主義の勝利どころか、その逆だ。メディケイドの削減で約1100万人の低所得層が健康保険の資格を失うと推定される。ホワイトハウスは減税が成長を刺激し、財政赤字を減らすと明らかにしたが、荒唐無稽な主張だ。一部の経済分析機関は、米国経済が短期的に上昇するかのように見えるが途中で倒れる危険が大きいと予測する。特に財政赤字がさらに増え、財政危機に陥る危険性を警告する。米議会予算局は同法の施行で財政赤字が2034年までに3兆4千億ドル増加し、国内総生産(GDP)に対する国家負債の比率は現在の90%台後半から10年後には124%に達すると予測した。米政府は今も国債利子だけで年7760億ドル(約110兆円)を支払わなければならない状況だ。米国の年間予算の16%ほどを利子支給に使っているのだから、このような状態で財政が持続可能なはずがない。にもかかわらず、大規模な減税を行ったのだから、正気の沙汰ではない。
トランプ大統領は「ビジネスマン」と「MAGA戦士」の間にいる人物だ。1期目のトランプ大統領がビジネスマンに近かったとすれば、2期目のトランプ大統領はMAGA戦士の方に傾いている。MAGAは基本的に極右ポピュリズム的な白人人種主義だ。今回可決された法案は、トランプ大統領のポピュリスト色を露呈している。ポピュリズムは現実の矛盾を批判し、もっともらしく見える解決策を提示するが、実際には問題をさらに悪化させるだけだ。ドイツのアドルフ・ヒトラー、アルゼンチンのフアン・ペロンなどが代表的な事例だ。ただし、ずる賢いトランプ大統領は任期内には問題が浮き彫りにならないように管理しようとしている。トランプ大統領が連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長に金利引き下げを圧迫するのも、そのためだ。金利引き下げを通じて国債利子の負担を減らそうとしているのだ。このようなやり方で一時的には危機を免れるかもしれないが、人為的な金利引き下げはインフレを誘発し経済に負担を与えるだろう。
関税賦課はもう一つの賭けだ。トランプ大統領は関税収入で財政赤字を挽回しようとしている。議会予算局は10年間の関税収入が2兆8千億ドルに達すると見通した。現在より3.6倍ほど増えることになる。米国が財布の紐を絞めて問題を解決しなければならないのに、財政を放漫に運営しておいて、外国から税金を強奪して埋め合わせようとしているのだ。関税賦課には根拠もなく基準もない。米国が貿易赤字だからその分を出せと叫んでいるだけだ 。まるで属国に横暴を働く帝国の皇帝のようだ。他国の被害と世界経済の萎縮などまったく気にしない。このようなやり方で同盟に接するなら、米国にはもはや覇権国の資格がない。覇権国は、世界経済と世界平和を維持する番人の役割を果たしてこそ、尊重される。恣意的に軍事介入し、日常的に国際ルールを無視するなら、それは「ならず者国家」にすぎない。
トランプ大統領は「パクス・アメリカーナ」時代の終焉を早める人物になるものとみられる。もちろん、世界最強国が一瞬にして崩れることはないだろう。トランプ大統領時代を賢く耐え抜き、利害関係が近い国々と連帯して乗り越えていかなければならない。中長期的には、覇権国の空白は新しい世界秩序が定着するまで、戦争をはじめとする途方もない混沌を伴ったという歴史的経験を教訓にし、これに備えなければならない。 何よりも経済的・外交的・軍事的な自強に力を入れなければならない。
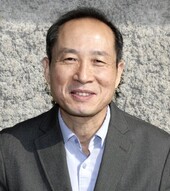
訳H.J

