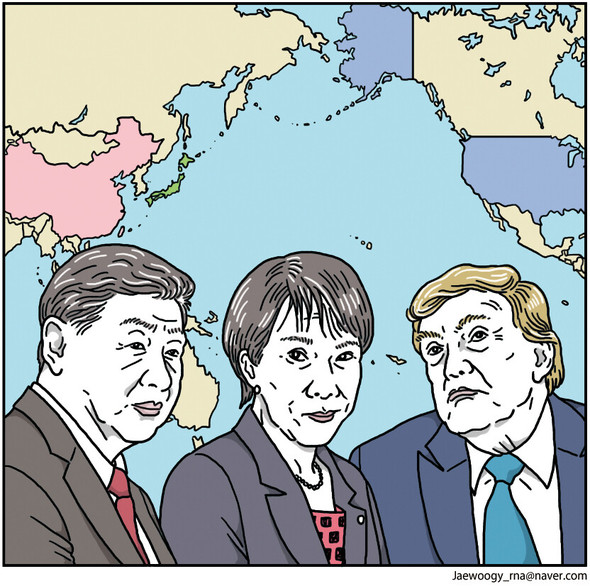[社説]韓国、2日間で100万人感染、「インフルエンザ致命率」と比べる時ではない

オミクロン株の大流行がピークに達し、17日の新型コロナウイルス感染確認数は60万人台にまで激増した。前日のシステムエラーで脱落していた患者数が1日遅れて反映された数値ではあるが、この2日間の患者数は100万人にのぼる。途方もない暴増ぶりだ。1日の死者数も400人を超え、過去最多を記録した。政府の中途半端な楽観が招いた防疫政策の失敗の結果ではないのか、振り返ってみるべきだ。
中央防疫対策本部の発表によると、17日午前0時現在で、過去24時間以内に新たにコロナ感染が確認された人の数は62万1328人。前日(40万711人)より22万人あまり多い。1週間で1日平均38万7000人あまりの感染者が発生している。死者も前日の2倍以上の429人に達した。このような増加は防疫当局の予測を上回るものだ。防疫当局は最近、国内の複数の研究機関の見通しにもとづき、流行のピークを16日から22日にかけて、流行の規模を32万から37万人(1週間の1日平均)の範囲内と予測していた。さらに大きな問題は、現在の増加傾向に照らすと、流行のピーク到達が遅れたりピークの期間が長くなったりしたうえ、ピーク時の感染規模も予想より大きくなり得るということだ。
このように防疫当局が提示したピーク予測が毎回外れるのは、政府が研究機関のシミュレーション結果を根拠に楽観論を示しつつ、「防疫緩和」の信号を何度も発していたからだ。社会的距離措置(ソーシャル・ディスタンシング)などの防疫政策の基調が緩和の方向へと進み続けているため、防疫の緊張感が緩み、感染規模が予測を上回る事態が繰り返されているのだ。
政府は楽観論の根拠として「季節性インフルエンザ」程度にまで下がった致命率と重症患者用病床の余力をあげる。もちろん、最近のオミクロン株の致命率は0.09%で、インフルエンザ(0.04~0.08%)と似たような水準にまで下がっているのは事実だ。しかし、オミクロン株の感染力や感染規模は、インフルエンザとは比べ物にならないほど大きい。インフルエンザにかかるのは年間250万~500万人だが、オミクロン株感染者はこの2カ月だけで650万人に達する。致命率が似ているとしても、多くの死者が出るのは避けられない。重症患者用病床もまだ余裕があるというが、今のような規模の流行が続けば、いずれ病床不足が起こる可能性もある。病床が不足すれば、高危険群が必要な時に治療を受けられず命を落とすという事態が続出しうる。
オミクロン対応防疫システムの核心は、高危険群の保護と被害の最小化だと言える。医療対応余力を超える規模で感染が広がれば達成は困難だ。日常回復に対する焦りを捨て、厳しい現実を直視すべき時だ。
訳D.K