[キル・ユンヒョンの新冷戦韓日戦1]「昔の良き時代」になぜ戻れないのか
「昔の良き時代」は中国の浮上と北朝鮮の核開発という二つのショックとともに幕を閉じた。韓国と日本の戦略的利害はもはや一致しない。両国の対中・対北朝鮮観と東アジアの未来像に対する見解は大きく異なり、そのため互いに対する憎しみと不信を積み重ねる「構造的不和」に陥ってしまった。
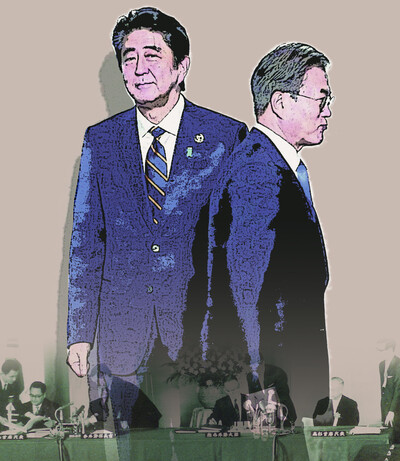
「山口県と秋田県で推進してきた『イージス・アショア』の配備計画を中止します」
先月15日午後5時30分、河野太郎防衛相が、このうえなく悪化した韓日関係にさらなる波乱をもたらす緊急ニュースを持ち出した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防のために黄みどり色のマスクをした河野防衛相は、やや躊躇するような声で、2017年末から推進してきたイージス・アショア配備計画を中止すると発表した。予期せぬ突然の発表だったため、東京都市ヶ谷の防衛省A棟1階の入り口に集まった記者の間でざわめきが収まらなかった。
日本はこれまで北朝鮮が自国に向けて弾道ミサイルを撃つ場合、第1次に東海上に浮かんでいるイージス艦がSM-3ミサイルを発射して阻止し、第2次に東京など大都市に配備されたパトリオット(PAC)-3ミサイルを撃って迎撃するという「二重のミサイル防衛(MD)体制」を構築していた。しかし、2017年に入り北朝鮮の核・ミサイルの脅威が高まると、同年12月に「海上の盾」と呼ばれるイージス艦に装着された弾道ミサイル迎撃システムを陸地に移した「イージス・アショア」を導入し「三重の防衛体制」を作ることに決定した。その後2年半の間、2023年を目標に設置計画を推進していたが、この日、迎撃ミサイルを発射する際に落ちるブースターから住民の安全を保障できないとし、計画を突然中止したのだ。
この決定は、東アジア全体を巨大な混乱の渦に巻き込みかねない連鎖の波紋をもたらした。3日後の18日、記者会見を行った安倍晋三首相は「わが国を取り巻く安保環境がさらに厳しくなっており、朝鮮半島では緊迫の程度が高まっている」とし、「今夏、国家安全保障会議(NSC)で(新しい安保戦略を)徹底的に議論し、迅速に実行に移す」と述べた。
これを合図に、北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応するには日本が軍事的役割を強化しなければならないと主張してきた自民党内の重鎮議員らが動き始めた。彼らは先月30日、「ミサイル防衛に関する検討チーム」を設置し、日本が直接北朝鮮のミサイル基地を攻撃できる「敵基地攻撃能力」を備えるべきだと主張した。最初の会議後、中谷元元防衛相は現行憲法の専守防衛の原則を守りながら「日本が敵のミサイル基地を叩くことは可能だ」と主張した。小野寺五典元防衛相も8日に開催された衆議院の安全保障委員会で「敵のミサイルを防ぐには発射前や発射直後が最も確実で効果的だ」と力説した。すると河野防衛相は「様々な選択肢について論議するのは当然」だとし、敵基地攻撃能力保有を公式に検討するという意思を明確にした。日本が遠からず、米国の力に頼らず直接北朝鮮を攻撃する能力を確保する可能性が高まったのだ。
日本は敵基地攻撃能力を保有すべきだと強く主張する中谷氏は、2015年10月、ハン・ミング当時国防部長官との会談で「韓国の主権範囲は休戦ラインの南側」という発言を残した人物として有名だ。この発言は、日本が北朝鮮から軍事的脅威を感じるなら「韓国の承認なしに」武力行使に出る可能性があることを暗示する言葉として、当時大きな波紋を呼んだ。このような考え方は「朝鮮半島で軍事行動は大韓民国だけが決定することができ、誰も大韓民国の同意なしに軍事行動を決定できない」(文在寅(ムン・ジェイン)大統領、2017年8・15祝辞)という韓国人の考えとは決して両立できないものだ。日本が敵基地攻撃能力を保有し、これを実際に行使しようとするなら、韓日は日本軍「慰安婦」や強制動員被害者賠償・補償などをめぐる「歴史問題対立」や、フッ化水素などの輸出規制をめぐる「経済対立」を超えて、骨が砕け肉が引き裂かれる「安保領域」で本格的な対立を続けるしかない。
昨年7月、日本のフッ化水素などに対する輸出規制で韓日関係が過去最悪に悪化すると、韓日双方で両国関係の全盛期だった1998年の「韓日パートナーシップ宣言」の頃に戻るべきだという主張が続いた。しかし、「中国の浮上」と「北朝鮮の核開発」という二つのショックですでに新冷戦に突入した東アジアで、「昔の良き時代」に戻ることは事実上不可能なことになってしまった。
振り返ってみると、1965年の国交正常化以降、韓日関係は大きく3つの時期を経てきた。第1期は国交正常化から1980年代末の冷戦解体に至る時期だった。この時期の基本条件は「冷戦」だった。殺伐とした冷戦秩序は両国に協力を強制した。両国は歴史問題を封印し、経済協力の道を開いたいわゆる「1965年請求権協定」を通じて国交を正常化した。韓国は共産圏の脅威から日本を防衛する一種の「防波堤」の役割をし、日本はそのような韓国に無償3億ドル、有償2億ドルという経済協力資金と技術力を提供し、これを支えた。
この時期の韓日関係の本質を示す象徴的な出来事は、小倉和夫元駐韓日本大使が書いた『秘録・日韓1兆円資金』という本に書かれている。12・12クーデターを通じて政権を握った全斗煥(チョン・ドゥファン)政権は、1981年4月、日本に向けて突然「韓国は自由陣営の主軸として国家予算の35%を国防予算として使っている。それによって最も大きな恩恵を受けている国は日本」だとし、100億ドルという巨額の経済協力を求める。これに対する日本政府の最初の反応は「韓国政府が狂った」(木内昭胤アジア局長・当時)だったが、公式と秘密ラインを行き来する1年半にわたる奇妙な交渉の末、結局40億ドルの借款を提供した。この時期にはむしろ日本が率先して中国(当時中共)と国交正常化を望む韓国の意向を伝えたりもした。韓日間の戦略的利害は一致し、そのため同じところを眺め力を合わせることができた。
第2期は、冷戦が解体された1980年代後半から、中国の浮上が可視化する前の2000年代末までと区分される。冷戦の解体とともに1987年の「6月革命」で韓国が民主化すると、日本の植民地支配によって苦しめられた被害者たちの賠償・補償要求があふれ始めた。これに刺激された韓日は、様々な紆余曲折の中でも、慰安婦動員の過程の強制性と日本政府の関与を認めた1993年の「河野談話」と、植民地支配と侵略に対して日本の謝罪と反省の意を込めた1995年の「村山談話」という成果を作り出した。金大中(キム・デジュン)大統領と小淵恵三元首相はこのような成果を集めて、お互いを対等なパートナーとして認める「韓日パートナーシップ宣言」を1998年10月に発表した。これを通じて大衆文化が相互開放され、2000年代半ばには日本社会で華やかな「韓流ブーム」が花開いた。
だが、「昔の良き時代」は中国の浮上と北朝鮮の核開発という二つのショックとともに幕を閉じた。2010年以降、中国と尖閣諸島(中国名・釣魚島)をめぐる領土紛争を経た日本は、中国の浮上に対抗するために、米国との同盟強化に乗り出した。両国は2015年4月、日米安保協力指針(ガイドライン)を改正し、日米同盟をこれまでの「地域同盟」から「グローバル同盟」へと位相と役割を強化させた。その後日米は、米国を媒介に別々に機能していた韓米同盟と日米同盟を一つの軸に結ぶ韓米日三角同盟の構築を試みた。このために、韓日協力の重大な“障害”だった慰安婦問題を2015年12月28日の12・28合意で「解決」させ、その基盤の上で2016年11月に韓日軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を締結し、2017年4月のTHAAD(高高度防衛ミサイル)配備まで一気に進むことができた。
この流れに歯止めをかけたのは、2016年末の韓国の民衆たちのろうそく集会だった。このまま韓米日三角同盟に引っ張られることに大きな不安を感じた韓国人たちは、2017年5月、文在寅を大統領の座に押し上げた。文大統領は就任後、12・28合意を無力化したのに続き、南北関係を改善して朝米間の妥協を促進した。北朝鮮と中国を抑制しなければならないという「現状維持」戦略を固守してきた日本は、韓国の「現状変更」の試みに危うさを感じ、強い抵抗に出た。これがこの3年間進められた韓日対立の停滞だ。新冷戦が「ニューノーマル」(新たなバランス)を取り戻すまで、この対立は続くだろう。
韓国と日本の戦略的利害はもはや一致しない。両国の対中・対北朝鮮観と東アジアの未来像に対する見解は大きく異なり、そのため互いに対する憎しみと不信を積み重ねる「構造的不和」に陥ってしまった。
これから約10回にわたり、文在寅政権3年間で行われた韓日対立の展開過程を振り返って書く。次のテーマは、文在寅政権の最初の選択だった12・28合意無力化決定とそれに対する日本の対応だ。(続)

キル・ユンヒョン|統一外交チーム記者。大学で政治外交学を専攻。駆け出し記者時代から強制動員の被害問題と韓日関係に関心を持ち、多くの記事を書いた。2013年秋から2017年春までハンギョレ東京特派員を務め、安倍政権が推進してきた様々な政策を間近に見た。韓国語著書に『私は朝鮮人カミカゼだ』、『安倍とは誰か』など、翻訳書に『真実: 私は「捏造記者」ではない」(植村隆著)、『安倍三代』(青木理著)がある。
訳C.M

