сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│№╝А№╝ЕсЂ«сђїтЙфуњ░тЈќт╝ЋсђЇсЂФ№╝А№╝ЕсЃљсЃќсЃФУФќт║ЃсЂїсѓІРђд№╝Е№╝Г№╝дуиЈУБЂсѓѓУГдтЉі
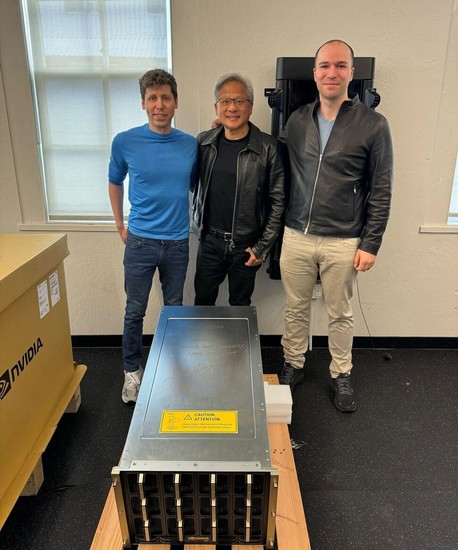
сђђСИќуЋїсЂ«С║║тиЦуЪЦУЃй№╝ѕAI№╝ЅтИѓта┤сѓњуЅйт╝ЋсЂЎсѓІтЁѕжаГС╝ЂТЦГсЂ«Тќ░уе«сЂ«жЄЉУъЇтЈќт╝ЋсЂ«сѓёсѓіТќ╣сЂїсђЂAIсЃљсЃќсЃФУФќсЂФтєЇсЂ│уЂФсѓњсЂцсЂЉсЂдсЂёсѓІсђѓсЃЂсЃБсЃЃсЃѕGPT№╝ѕChatGPT№╝ЅсѓњжќІуЎ║сЂЌсЂЪС╝ЂТЦГсЂДсЂѓсѓІу▒│тЏйсЂ«сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсѓёсђЂAIсЃЂсЃЃсЃЌжќІуЎ║С╝џуцЙсЂ«сѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓб№╝ѕNVIDIA№╝ЅсђЂAMDсЂфсЂЕсЂ«сђїтЙфуњ░тЈќт╝ЋсђЇсЂ«ТДІжђасЂїсђЂтцќтйбСИісЂ«тБ▓СИісЂеС╝ЂТЦГСЙАтђцсѓњУєесѓЅсЂЙсЂЏсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂІсЂесЂёсЂєсЂЊсЂесЂасђѓтЏйжџЏТЕЪжќбсЂ«ждќжЋисѓѓAIсЃљсЃќсЃФсѓњУГдтЉісЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓ
сђђ9ТЌЦсЂ«ТЦГуЋїсЂ«УЕ▒сЂФсѓѕсѓІсЂесђЂсЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфУГ░УФќсЂ«СИГт┐ЃсЂФсЂѓсѓІсЂ«сЂ»сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂасђѓтљїуцЙсЂ»6ТЌЦ№╝ѕС╗ЦСИІуЈЙтю░ТЎѓжќЊ№╝ЅсђЂAMDсЂеТѕдуЋЦуџёсЃЉсЃ╝сЃѕсЃісЃ╝сѓисЃЃсЃЌтЦЉу┤ёсѓњухљсѓЊсЂасђѓAMDсЂ»сѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓбсЂФТгАсЂљAIТ╝ћу«ЌућесЃЂсЃЃсЃЌ№╝ѕGPU№╝ЅтѕєжЄј2СйЇсЂ«тЇіт░јСйЊУеГУеѕС╝џуцЙсЂасђѓ
сђђсЂЊсЂ«тЦЉу┤ёсЂФсѓѕсѓісѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂ»сђЂAMDсЂїТЮЦт╣┤СИІтЇіТюЪсЂФуЎ║тБ▓С║ѕт«џсЂ«AIсЃЂсЃЃсЃЌ№╝ѕAIсѓбсѓ»сѓ╗сЃЕсЃгсЃ╝сѓ┐сђїMI450сђЇ№╝ЅсѓњТЋ░тЇЃтёёсЃЅсЃФтѕєУ│╝тЁЦсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂФсЂЌсЂЪсђѓсЂЮсЂ«УдІУ┐ћсѓісЂесЂЌсЂдсђЂAMDсЂ»УЄфуцЙсЂ«ТафСЙАсЂї1ТафсЂѓсЂЪсѓі600сЃЅсЃФсѓњУХЁсЂѕсЂЪсѓЅсђЂТЎ«жђџТафТюђтцД1тёё6000СИЄТаф№╝ѕТїЂТафсЂ«у┤ё10№╝Ё№╝Ѕсѓњ1ТафтйЊсѓі0.01сЃЅсЃФсЂДУ▓исЂѕсѓІТќ░ТафсЂ«тЈќтЙЌТеЕсѓњсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂФТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂФсЂЌсЂЪсђѓ
сђђAMDсЂ«уЈЙтюесЂ«ТафСЙАсЂ»С╗іТюѕ8ТЌЦсЂ«ухѓтђцтЪ║Т║ќсЂД1ТафтйЊсЂЪсѓі235.56сЃЅсЃФсђѓсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂ«тцДУдЈТеАсЂфсЃЂсЃЃсЃЌУ│╝тЁЦсЂїAMDсЂ«тБ▓СИісЂісѓѕсЂ│ТафСЙАтљЉСИісЂФУ▓буї«сЂЎсѓІсЂЊсЂесЂІсѓЅсђЂС╝џуцЙсЂ«Тафт╝Јсѓњт«ЅтђцсЂДТИАсЂЌсђЂсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂ«ТіЋУ│ЄсЂ«У▓аТІЁсѓњТИЏсѓЅсЂЎсЂесЂёсЂєТДІжђасЂасђѓAMDсЂ«сЃфсѓхсЃ╗сѓ╣сЃ╝ТюђжФўухїтќХУ▓гС╗╗УђЁ№╝ѕCEO№╝ЅсЂ»сђїAIсЂ«сѓесѓ│сѓисѓ╣сЃєсЃауЎ║т▒ЋсЂФтљЉсЂЉсЂЪсЂЙсЂБсЂесЂєсЂфсѓдсѓБсЃ│сѓдсѓБсЃ│ТѕдуЋЦсђЇсЂасЂеУЄфУЕЋсЂЌсЂЪсђѓ
сђђAIС╝ЂТЦГсЂ«тцДУдЈТеАсЂфтЙфуњ░тЈќт╝ЋсЂ»С╗ітЏъсЂїтѕЮсѓЂсЂдсЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓсѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓбсѓѓтЁѕТюѕ23ТЌЦсђЂсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂФТюђтцД1тЇЃтёёсЃЅсЃФсѓњТіЋУ│ЄсЂЎсѓІсЂеуЎ║УАесЂЌсЂЪсђѓсЂЊсЂ«ТіЋУ│ЄжЄЉсЂ»сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂїсѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓбсЂ«AIсЃЂсЃЃсЃЌсѓњУ│ЃтђЪ№╝ѕсЃфсЃ╝сѓ╣№╝ЅсЂЎсѓІсЂ«сЂФСй┐сЂєУеѕућ╗сЂасђѓсѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓбсЂ»сђЂAIсѓцсЃ│сЃЋсЃЕсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣С╝ЂТЦГсЂДсЂѓсѓІу▒│тЏйсЂ«сѓ│сѓбсѓдсѓБсЃ╝сЃќсЂфсЂЕсЂ«Тќ░ућЪС╝ЂТЦГсЂФсѓѓТіЋУ│ЄсЂфсЂЕсѓњтцДт╣ЁсЂФТІАтцДсЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓсЂЊсЂ«ТіЋУ│ЄжЄЉсѓѓтљїТДўсЂФсђЂТќ░ућЪС╝ЂТЦГтљёуцЙсЂ«сђїсѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓбсЂ«сЃЂсЃЃсЃЌУ│╝тЁЦсђЇсЂИсЂетєЇсЂ│сЂцсЂфсЂїсЂБсЂдсЂёсѓІсђѓ
сђђсЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфтЈќт╝ЋТДІжђасЂ»сђЂУАетљЉсЂЇсЂ»тЈїТќ╣сЂФсЂесЂБсЂдсђїСИђуЪ│С║їж│ЦсђЇсЂФУдІсЂѕсѓІсђѓсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂ»тцЕТќЄтГдуџёсЂфAIсѓцсЃ│сЃЋсЃЕТіЋУ│ЄУ│ЄжЄЉсѓњУф┐жЂћсЂЌсђЂсЃЂсЃЃсЃЌСЙЏухдС╝џуцЙсѓѓсђїтцДТЅІсђЇсЂ«тЈќт╝ЋтЁѕсѓњтЁѕтЈќсѓісЂЌсЂдтЈјуЏісѓњСИісЂњсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсЂІсѓЅсЂасђѓ
сђђсЂЌсЂІсЂЌсђЂтИѓта┤сЂ«уќЉтЋЈсЂ»т░ЉсЂфсЂЈсЂфсЂёсђѓтЙфуњ░тЈќт╝ЋсЂ«ТДІжђасЂ«СИГт┐ЃсЂФсЂёсѓІсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂїсђЂAIсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сѓњжђџсЂўсЂдсЂ«тЈјуЏісЂїСИІсЂїсЂБсЂЪта┤тљѕсђЂсЃљсЃќсЃФсЂїСИђТ░ЌсЂФсЂ»сЂўсЂЉсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂѓсѓісЂєсѓІсЂЪсѓЂсЂасђѓ
сђђсЃќсЃФсЃ╝сЃасЃљсЃ╝сѓ░жђџС┐АсЂ»8ТЌЦсђЂсђїсЂЙсЂЎсЂЙсЂЎУцЄжЏЉсЂФсЂфсѓіуЏИС║њсЂФжђБухљсЂЋсѓїсЂЪтЈќт╝ЋТДІжђасЂїТЋ░тЁєсЃЅсЃФУдЈТеАсЂ«AIсЃќсЃ╝сЃасѓњС║║уѓ║уџёсЂФТћ»сЂѕсЂдсЂёсѓІсЂесЂ«ТєѓТЁ«сЂїт║ЃсЂїсЂБсЂдсЂёсѓІсђЇсЂеТїЄТЉўсЂЌсЂЪсђѓ1990т╣┤С╗БтЙїтЇісЂ«сЃЅсЃЃсЃѕсѓ│сЃасЃљсЃќсЃФтйЊТЎѓсђЂсЃФсЃ╝сѓ╗сЃ│сЃѕсЃ╗сЃєсѓ»сЃјсЃГсѓИсЃ╝сЂфсЂЕжђџС┐АсЂ«УБЁтѓЎсЃАсЃ╝сѓФсЃ╝сЂїжђџС┐АсЂ«С║ІТЦГУђЁсЂФтиежАЇсѓњУъЇУ│ЄсЂЌсђЂУЄфуцЙсЂ«УБЁтѓЎсѓњУ▓исѓЈсЂЏсЂЪсђїсЃЎсЃ│сЃђсЃ╝сЃ╗сЃЋсѓАсѓцсЃісЃ│сѓ╣сђЇ№╝ѕСЙЏухдУђЁжЄЉУъЇ№╝ЅсЂежАъС╝╝сЂЌсЂдсЂёсЂёсѓІсЂесЂёсЂєУЕ▒сЂасђѓсЂЊсѓїсЂ»тйЊТЎѓсђЂсЃЅсЃЃсЃѕсѓ│сЃасЃљсЃќсЃФсѓњТІАтцДсЂЋсЂЏсЂЪтјЪтЏасЂесЂЌсЂдТїЄТЉўсЂЋсѓїсЂЪсђѓсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂ«С╗іт╣┤СИітЇіТюЪсЂ«тБ▓СИіжФўсЂ»43тёёсЃЅсЃФсђЂтќХТЦГУхцтГЌсЂ»78тёёсЃЅсЃФсЂФсЂ«сЂ╝сѓІсђѓ
сђђтйЊС║ІУђЁсѓЅсЂ»сЂЊсѓїсѓњСИђУ╣┤сЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂ«сѓхсЃасЃ╗сѓбсЃФсЃѕсЃъсЃ│CEOсЂ»сЂЊсѓїсЂФтЁѕуФІсЂц6ТЌЦсђЂжќІуЎ║УђЁсѓФсЃ│сЃЋсѓАсЃгсЃ│сѓ╣сЂ«уЏ┤тЙїсЂФсђїсЂёсЂЙсЂ»СИђуе«сЂ«сЃљсЃќсЃФсЂеУђЃсЂѕсѓІжЃетѕєсЂїсЂѓсѓІсђЇсЂесЂЌсЂфсЂїсѓЅсѓѓсђЂсђїсЂЊсѓїсЂ»тЇўсЂФТќ░сЂЌсЂёТіђУАЊсЂ«жЮЕтЉйсЂїжђ▓сѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІсЂЪсЂАсђЇсЂасЂет╝иУф┐сЂЌсЂЪсђѓсѓесЃїсЃЊсЃЄсѓБсѓбсЂ«сѓИсѓДсЃ│сѓ╣сЃ│сЃ╗сЃЋсѓАсЃ│CEOсѓѓ8ТЌЦсђЂCNBCсЂ«сѓцсЃ│сѓ┐сЃЊсЃЦсЃ╝сЂДсђї№╝ѕсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│AIсЂеAMDсЂ«тЈќт╝ЋТДІжђасЂ»№╝ЅТЃ│тЃЈтіЏсЂїтѓЉтЄ║сЂЌсђЂуІгуЅ╣сЂДжЕџсЂЈсЂ╣сЂЇсѓѓсЂ«сЂасђЇсЂеУЕЋСЙАсЂЌсЂЪсђѓ
сђђСИђТќ╣сЂЊсЂ«ТЌЦсђЂтЏйжџЏжђџУ▓етЪ║жЄЉ№╝ѕIMF№╝ЅсЂ«сѓ»сЃфсѓ╣сѓ┐сЃфсЃісЃ╗сѓ▓сѓфсЃФсѓ«сѓесЃљт░ѓтІЎуљєС║ІсЂ»у▒│тЏйсЂ«сЃ»сѓисЃ│сЃѕсЃ│сЂДжќІсЂІсѓїсЂЪУАїС║ІсЂДсђїуЈЙтюесЂ«С╝ЂТЦГСЙАтђцУЕЋСЙАсЂ»25т╣┤тЅЇсЂ«сЃЅсЃЃсЃѕсѓ│сЃасЃљсЃќсЃФсЂ«Т░┤Т║ќсЂФтљЉсЂІсЂБсЂдсЂёсѓІсђЇсЂесЂЌсЂдсђї№╝ѕТафСЙАТђЦУљйТЎѓ№╝ЅСИќуЋїухїТИѕсЂ«ТѕљжЋиујЄсЂїСИІУљйсЂЌсђЂУёєт╝▒ТђДсЂїсЂѓсѓЅсѓЈсЂФсЂфсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓІсђЇсЂеУГдтЉісЂЌсЂЪсђѓ
Уе│J.S