こっそり見ていた日本アニメ、どのようにして韓国のMZ世代を魅了したのか
CULTURE & BIZ

2023年の韓国映画産業の危機論のなかで顕著な現像は、日本アニメの強さだった。なかなか回復しない映画館に、『すずめの戸締まり』『THE FIRST SLAM DUNK』『君たちはどう生きるか』などの日本アニメがそれぞれ557万人、477万人、197万人の観客を得て善戦した。様々な原因が分析されたが、若い観客が世界最高水準の日本アニメに期待と信頼を持っているという点が大きかった。
実のところ40代以上の韓国人には、今も「日本」コンテンツに心理的な抵抗線がある。日本の大衆文化の開放前に青少年期を過ごし、幼い時から慣れ親しみ楽しんだ文化ではないためだ。日本の大衆文化の開放に関する論議に接しながら思考を育ててきたため、日本文化に対する視線は今でも気兼ねないものではない。しかし、幼い時から『となりのトトロ』をみて育った10~30代はそうではない。
そうした世代に、2000年以前の韓国では公式には日本の大衆文化を楽しむことができなかったという話をすると、首をかしげる。過去の韓国政府が日本の大衆文化を規制する際には、主に3つの論理が活用された。1つ目は政治的理由で、日本の大衆文化はそれ自体が日本の象徴であるため、日本の植民地支配を経験した韓国が日本の大衆文化を公に受けいれることはできないというものだった。2つ目は文化的理由で、日本の大衆文化は変態的かつ猥褻な傾向が強く、青少年ら国民に害となる影響を与える可能性があるというものだった。3つ目は経済的理由で、韓国よりも多くの資本と技術を有する日本の大衆文化を開放した場合、韓国文化産業は壊滅しかねないという不安と懸念のためだった。
■社会的議論にともなう規制
日本の大衆文化の禁止は、明文化した「法」のような制度的装置ではなく「因襲」に近い規範により維持された。日本の大衆文化の禁止の正当性を社会的には共有したが、「日本大衆文化禁止法」のような法令が存在したことはなかったためだ。代わりに、1961年に制定された「公演法」第19条第2項「外国公演物の公演制限」に、「国民感情を害する恐れがある、または公序良俗に反する外国の公演物を公演することはできない」という項目、1973年に制定された「外国刊行物輸入配布に関する法律」第7条に「公安または風俗を害する恐れがあると認められる外国の刊行物を輸入する時には、配布または販売を中止または内容の削除を命じることができる」という項目などが、日本の大衆文化の禁止の根拠として活用されたりした。
そのため、政府が禁止する日本の大衆文化、すなわち「倭色(日本的なもの)」の意味も規制する対象も、時期によって違った。代表事例が、歌謡曲「椿お嬢さん」の放送禁止だった。朴正煕(パク・チョンヒ)政権期の歌手のイ・ミジャが発表した「椿お嬢さん」は、日本の歌謡曲の演歌に似た「倭色風」という理由で1965年に放送が禁止され、1968年にはレコードの発売が中止された。かつて韓国のトロット(韓国演歌)のほとんどが演歌風だったことを考慮すると、「椿お嬢さん」の禁止は少々皮肉だった。
この措置は本来の目的とは関係ない政府の必要のためだった。当時は、国民の反対を押し切って韓日基本条約が締結された時だった。親日の性格だという論議があった朴正煕政権は、韓日基本条約に反対の世論が高まると、自分たちが「民族主義者」であることを誇示しようとした。そのため、大人気を得ていた大衆歌謡を「倭色」で禁止することによって、政権が帯びていた親日のイメージを刷新しようとした。
このように日本の大衆文化の禁止は、初期には植民地残滓を清算するという意味があったが、時間が経つにつれ、意味が変質した。国民を統制したり政権の政治的目的で維持される性格が強かった。国民感情も複雑だった。植民地残滓の清算には共感したが、東アジアで最も水準の高い日本の大衆文化を消費したい欲求も強かった。しかし、政府がこの枠組みを破ることは難しかった。開放に立ち向かう瞬間に出てくる「親日」フレームのためだった。結局政府は、公には日本の大衆文化の流入を禁止しても、裏口はこっそり開けておく奇形的な形態を取った。
これにともない、日本の大衆文化は歪曲されたかたちで広範囲に流布した。1970年代以降、『鉄腕アトム』や『キャンディ・キャンディ』『マジンガーZ』のような日本のテレビアニメは、背景や主人公の名前を変えて「倭色除去」をした後に放映された。日本のロックグループやJ-POPのレコードは「闇市場」で誰でも買うことができた。釜山(プサン)などの地では、衛星放送などを通して日本の放送番組を楽しめた。日本映画やアニメは「海賊版」ビデオテープで幅広い支持層を維持した。
■「親日フレーム」から自由な政権
不完全な体制は、韓国が万国著作権条約に加盟しなかったことで可能だった。しかし、1980年代に米国政府が財政赤字と貿易赤字を打開するために知的財産権問題を掲げたことで、変化を迎えた。1985年に米国は韓国の著作権侵害に「スーパー301条」を発動すると発表した。これを受け、韓国政府は1986年に万国著作権条約(UCC)に加盟し、「著作権法改正案」を通じて著作権保護体制のなかに編入された。
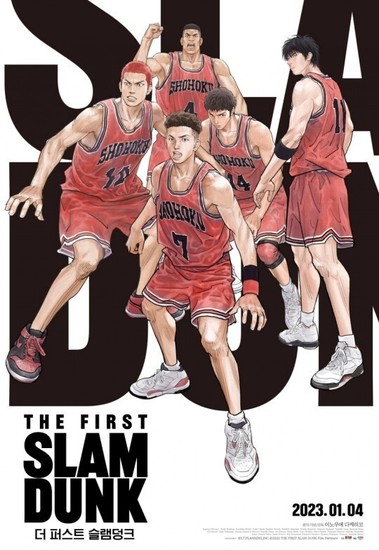
米国との交渉が結ばれると、日本も黙ってはいられなかった。それまで日本は、自国の文化商品が韓国に流布することを認知していたが、あえて是正しようとはしなかった。過去の植民地国家から日本帝国主義文化の復活というけん制を受ける可能性があり、大衆文化を積極的に輸出しようとする意志が弱かったためだ。しかし、万国著作権条約の枠に入ると、日本も変わらざるをえなかった。日本は韓国政府に正式に大衆文化の輸入と著作権を認めるよう要請した。結局、1989年にマンガなどの出版界では禁止が解除された。
それでも政府は、引き続き日本の大衆文化の禁止体制を維持した。検閲の道具が必要だったからだ。しかし、民主化の進展で大衆文化政策にも変化が起きた。1988年にハリウッド映画の直接配給やケーブルテレビの開局などを通して世界の大衆文化が押し寄せると、外国文化開放は重大な懸案となった。ソ連や中国などの共産主義文化まで入ってきているのに、日本の大衆文化だけを禁止するというのは皮肉なことだった。
では、誰が門戸を開くことができるのだろうか。過去の政権にはいずれも限界があった。朴正煕政権は韓日国交正常化の締結などの問題で、民族主義者としての面貌を示したがった。クーデターで政権を取得した全斗煥(チョン・ドゥファン)政権は、国民を統制するために「禁止」の手段の維持を望んだ。盧泰愚(ノ・テウ)政権と金泳三(キム・ヨンサム)政権になると、「開放化」や「グローバル化」という議論が広がり始めた。結局、選挙による政権交替を最初に成し遂げた金大中(キム・デジュン)政権で開放に踏み切ることができた。金大中政権は「親日」問題からも自由であり、国民を統制する必要もなかった。
日本の大衆文化が開放される頃、金大中大統領は関連省庁に「恐れることなく臨め」という指示を与えた。過去数十年間、日本文化について韓国社会を支配していた命令は「恐れろ」だった。日本の大衆文化が好きだと明らかにしたり開放を主張すれば、「親日派」として追及された。しかし、誰からも「親日派」と主張されることはありえない金大中大統領が「恐れるな」という一声を投げることによって、開放の流れは加速した。
■開放の最後の山、国内産業保護論
最後に足手まといになったのは「国内産業保護論」だった。かつては政治社会的な理由が強かったが、1990年代になると、韓国の文化産業の基盤が揺らぐことになりかねないという経済的反対論が強く浮上した。特に1999年から「輸入先多辺化制度」が廃止され、輸入が禁止されていた日本の自動車、テレビ、携帯電話などの輸入が許される予定だったため、なおさらだった。そうした状況で日本の大衆文化まで入ってくることになれば、市場蚕食が広がるという心配が多かった。
ついに1998年10月に日本の大衆文化が開放された。映画・ビデオ産業と出版産業から始まり、2004年まで分野別に段階的開放が進行された。しかし、4次にわたる日本の大衆文化の開放の結果、韓国の文化産業に及ぼした影響は懸念していたよりはるかに小さかった。映画の場合、1999年の第2次開放後に上映された映画『ラブレター』『鉄道員(ぽっぽや)』『SFサムライ・フィクション』などがソウルの観客を10万人以上動員することもあった。しかし、第3次開放後はその水準の興行は、2000年の『ポケットモンスター』、2001年の『となりのトトロ』のようなアニメ程度に過ぎなかった。音楽もむしろ韓国のレコード輸出額が1999年の20億ウォン(現在のレートで約2億2000万円)から2000年には59億ウォン(現在のレートで約6億5000万円)と約3倍に増加したことのほうが目立った。
こうした結果となった理由は、2000年代に入ると韓国の文化産業が旺盛に成長したためだ。国際通貨基金(IMF)の外国為替危機後、政府は文化産業を次世代の成長動力と宣言し、各種の振興計画を発表した。ベンチャーキャピタルが映画投資に参入し、映画産業も大きく成長した。H.O.T.などのアイドルグループは中国や東南アジアにまで進出し、「韓流」ブームが起き始めた。その反面、当時の日本の大衆文化は衰退期に突入していた。日本の大衆文化は、1980年代後半から1990年代末まで「大衆文化ルネサンス期」を謳歌した。しかし、韓国が門戸を開いたとき、日本の文化産業はアニメなどのいくつかの分野を除き、やや沈滞に陥り始めた。
複雑だった「禁止」と「許容」という論議から抜けだし、20年ほどが経過した。日本の大衆文化は当時も今も、自分たちが得意とする分野を変わることなく生かしている。浮沈を繰り返したのは韓国映画だった。若い大衆は先入観なしに選択した。2023年の韓国市場で日本アニメがファインプレーをした理由としては、韓国の不振の側面がより大きかったということだ。自分が得意とすることをより得意にすることも優れた能力だ。韓国の映画産業がこの現象に対して何か考えるべきだとすれば、韓国にそうした点が確かにあるのかを、一度きちんと見直さなければならないということだ。
訳M.S

