EVはエコなのか?…問題はカーボンニュートラルではなく「金属」【レビュー】
デジタル時代の再生可能エネルギーの陰を告発
代案はリサイクル・消費縮小・自転車使用の拡大

フリージャーナリストのヴィンス・バイザーは、初めての著書『砂と人類: いかにして砂が文明を変容させたか』(韓国語版2018年、日本語版2020年)で、人類の文明の土台を成す砂の過去と現在、そして未来を調べて好評を得た。彼の2番目の著書『パワー・メタル』(韓国語版2024年、未邦訳)は、砂と同じくらい人間の暮らしに必須である金属についての話だ。特にバイザーは、デジタル技術の普遍化とクリーンエネルギーシフトが話題になった21世紀、その核となる金属をめぐる角逐と葛藤、そしてクリーンな再生可能エネルギー技術の不都合な真実を追跡し、読者に気候危機と持続可能性について考え直す機会を提供する。
2018年に初めて電気自動車(EV)を購入した経験が、この本の出発だった。気候危機に対応して持続可能性に貢献するという自負を持ったのはしばしの間だった。EVのバッテリーに含まれるリチウム、コバルト、ニッケルなどの金属を採掘して加工する過程で深刻な環境破壊が引き起こされ、挙句の果てにクリーンエネルギーだと信じていた太陽光や風力発電さえも、問題の解決ではなく別の問題のスタートにすぎないという事実をまもなく知ることになった。そのような問題意識で、世界各国の鉱山や研究所、廃車場、ごみ埋立地などを訪ね、投資家や草の根活動家、科学者、政治家、肉体労働者など様々な人たちに会って取材した結果が、著書『パワー・メタル』に込められている。
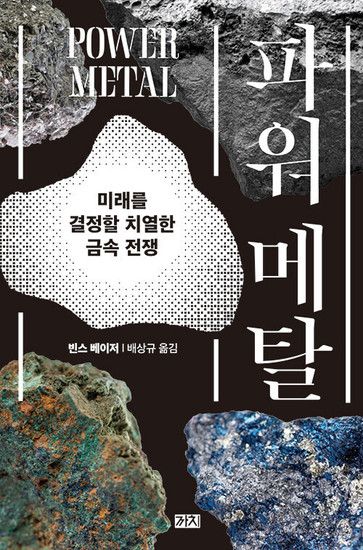
著者が購入したEVのバッテリーは「ニッケル、コバルト、リチウムが約45キログラムと、それと同程度の量の銅を加えて作る」。そうかと思えば、「重さ約130グラムのiPhone1台を作るためには、約35キログラムの鉱石を採掘しなければならない。鉱石は粉砕後に金属を分離する過程を経るが、このとき、携帯電話1台あたり炭素約45キログラムが排出される」。スマートフォンの画面や回路、スピーカーには、各種のレアアースが不可欠だ。レーザーやレーダー、暗視スコープ、ミサイル誘導コンピューターのような軍事技術も、レアアースに依存する。風力発電機1基には230キログラムのレアアースが使われもする。
「銅なしでは脱炭素もない」という言葉があるほど、エネルギーシフトに必須である銅、デジタル時代のコア・テクノロジーであるバッテリーに使われる決定的な素材であるニッケル、やはりEVのバッテリーに必須であるコバルト、デジタル機器とEV用バッテリーになくてはならない重要素材であるリチウムなどは、採掘と加工の過程で、途方もない環境破壊や汚染、児童労働のような非人間的な搾取を引き起こしている。全世界のレアアースの3分の1を保有している中国と、新たにレアアースの供給地として浮上したミャンマーの鉱山では、深刻な水質汚染や動物の大量死、人命への脅威などの問題が発生している。世界最大のニッケル輸出国として知られているインドネシアの場合、ニッケルを加工する作業に必要な電力を、主に石炭火力発電所で生産している。「カーボンニュートラルのためのバッテリーを作るために、炭素を膨大に排出する石炭をおびただしく燃やしているのだ」。この引用文がこの本で強調される一つの核心的なジレンマの一つだとすれば、もう一つの核心的なジレンマは、次のようなものだ。「デジタル技術とEVの拡散は、究極的には大多数の地域の大多数の人にとっての助けになるものだが、この過程で最も過酷な代価を支払うのは、一部の地域の一部の人たちだ」
前半で自ら「電気・デジタル時代」と命名した時代のこのような暗鬱な現実を容赦なく暴いたバイザーは、本の後半では、現実のジレンマを打開する代案を紹介し、その妥当性を追及している。地上の環境汚染を避けるための方法として深海採掘を主張する人もいるが、それは別の環境破壊と、さらに大きな問題を引き起こすことになりうる。「都市鉱山」と呼ばれる金属リサイクルは、一見するとエコにみえるが、金属スクラップを粉砕したり切断したりする作業過程で発生する金属粉末や毒性物質、金属スクラップを溶かす溶鉱炉を稼働するための石炭やガスによる発電などは、エコからはかけ離れている。しかも、「エネルギーシフトの過程で最も重要な機械である永久磁石、太陽光パネル、風力発電機などは、リサイクルがかなり難しい」

ならば、方法はないのだろうか。本の最後に著者は、ノートパソコンや携帯電話のようなデジタル機器の修理やリサイクルとともに、自動車を減らして自転車の使用を拡大しようという代案を提示する。上記のとおり、EVも深刻な環境破壊を招くだけに、「EVすら買わないほうがいい」。EVをはじめとするすべての自動車に追加の税金と料金を課し、その資金で公共交通と自転車インフラを支援するなど、「都市を人間中心に再設計しなければならない」。気候危機に対抗して再生可能エネルギーを活性化しようとするためには、金属が必要だが、「われわれ皆の暮らしは、金属の使用量を減らすほどさらに豊かになる」というのがこの本の結論だ。
訳M.S

