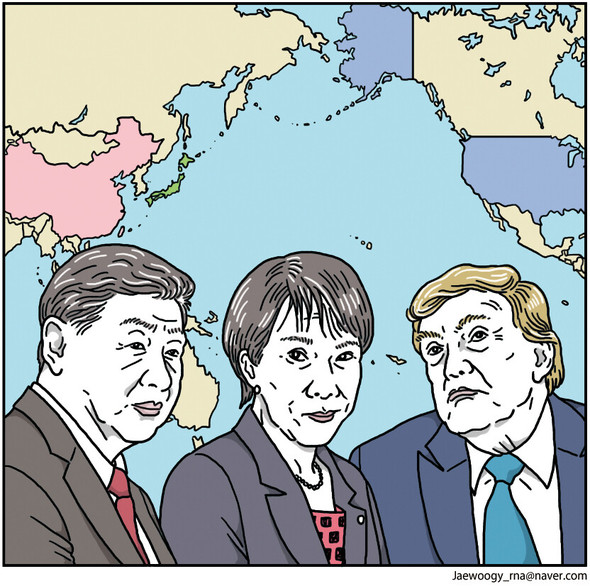水産物値下がりすれば政府が買い取り
漁業者は依然として「断固反対」

福島第一原発の運営企業である東京電力が、放射性物質汚染水を原発から1キロメートル離れた沖合に放出する方案を推進する。
東京電力は25日、福島第一原発から配管をつなぎ、1キロメートル離れた沖合に汚染水を放出することを骨格とする計画案を発表した。調査および関係当局の認可手続きを踏んだ後、2023年春から海洋放出をすることが目標だと発表した。
東京電力はこれまで、2011年の福島第一原発事故後に継続的に生じている汚染水を、福島第一原発のすぐ外側に送りだす方法と、配管をつなぎ海岸から一定程度離れた海中に排出する方案を検討してきた。東京電力は海岸から離れたところに放出すれば、海流に乗りやすく放射性物質がより早く薄められると見て、こういう方針を定めたと日本のマスコミは伝えた。
これに先立つ今年4月、日本政府は多核種除去設備(ALPS)で福島第一原発汚染水に混じっている放射性物質を除去した後に海洋放出することを決めた。水と近い性質のためにALPSでも除去できない放射性物質のトリチウム(三重水素)は、基準値の40分の1以下に濃度を薄め海に放出することにした。日本政府はトリチウムを除く放射性物質の大部分をALPSで除去するため、汚染水ではなく「処理水」だと主張している。
前日の24日、日本政府は水産物被害対策も発表した。原発汚染水の放出により水産物の価格が下落した場合、政府が買い入れるなどの対策を盛り込んだ。放射性物質汚染を憂慮して福島産食品などを忌避する現象、いわゆる「風評被害」対策の一つだ。政府が基金を用意して、冷凍可能な水産物は買い入れることにし、冷凍が不可能な生産物は新たな取引先を紹介するなどの方法で販路を確保するよう支援する予定だ。ただし、基金の規模など具体的な内容は年末までに確定する予定だ。
水産物対策は福島県だけでなく全国の水産物を対象とする。対策には消費者の理解を得るための広報強化なども含まれたが、どれくらい実効性があるかは疑問という指摘も多い。日本政府が今回、風評被害対策として以前にも実施してきた政策を含め様々な政策を出した理由は、漁業者が依然として汚染水の海洋放出に反対しているためだ。全国漁業協同組合連合会は「処理水の海洋放出に断固反対することを再度表明する。私たちの要請に国が明確に答えることを改めて要求する」と明らかにした。
訳J.S