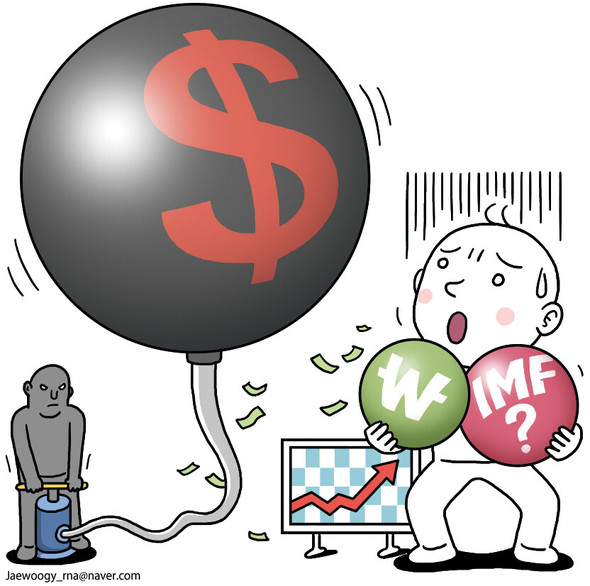伝統製造業の衰退や首都圏への流出などが原因
人口の増加は京畿が16万人と圧倒的

釜山(プサン)や大邱(テグ)、大田(テジョン)、光州(クァンジュ)、蔚山(ウルサン)など、地方大都市での人口減少が続いている。首都圏の人口が全体の50%を突破する状況で、地方大都市の人口減少は、地方の衰退の新たな危険信号となっている。
12日、行政安全部が発表した2019年末の住民登録人口統計によると、全国の7大広域市のうち、仁川(インチョン)を除いたソウルや釜山、大邱、大田、光州、蔚山の6都市で、2018年末よりも人口が減少した。減った人口規模はソウルが3万6516人、釜山が2万7612人、大邱が2万3738人、大田が1万5066人、光州が2868人、蔚山が7604人だった。7大広域市の中で唯一仁川だけは、人口が2384人増えた。
ソウルを除いた地方大都市の人口減少は、このような流れが長期間続いている点で、さらに深刻だ。釜山は1996年、大田は2014年、光州は2015年、蔚山は2016年から毎年人口が減っている。大邱は2004年から人口が減少したが、2010年に一時的に増えたものの、2011年から再び減少に転じた。核心産業地域の釜山や大邱、蔚山は製造業の衰退で直撃を受けており、大田は世宗市(セジョンシ)への流出、光州(クァンジュ)は首都圏への流出が主な原因に挙げられる。
広域市道のうち、2018年末より人口が増えたのは5カ所だが、そのうち京畿道は16万2513人も人口が増え、圧倒的な1位を占めた。京畿の人口増加は、デジタル産業の発展や新都市建設などによってソウルと地方の人口が流入したのが主な原因に挙げられる。その次に世宗が2万6449人、済州(チェジュ)が3798人、仁川が2384人、忠清北道が755人増えた。
基礎市郡区の中では63カ所で人口が増え、163カ所で人口が減少した。最も人口が増加したのは、京畿道華城(ファソン)市で、5万6674人だった。新都市の東灘(トンタン)地区への人口流入が多かったものと分析される。その次は京畿道始興市(シフン)市の2万4995人、龍仁市(ヨンイン)市の2万4483人、高陽(コヤン)市の2万2162人、仁川市延寿(ヨンス)の2万191人などだった。人口増加が多かった10の基礎自治地域はいずれも京畿と仁川など首都圏だった。人口が大幅に減った基礎地域のうち8カ所は首都圏で、その他に大邱西区、慶尚南道昌原(チャンウォン)市が含まれた。
年齢別には、40代(16.2%)と50代(16.7%)が全体人口の3分の1を占めており、60歳以上は22.8%、19歳以下は17.6%、30代は13.6%、20代は13.1%だ。ベビーブーマーの高齢化と低い出産率で、60歳以上は増え続けている一方、19歳以下は減少を続けている。
韓国人の平均年齢は42.6歳であり、最も若い広域は世宗市で、36.9歳だった。その次に、光州と京畿が40.8歳、蔚山が40.9歳、大田が41.3歳などだった。
全体人口は2019年末5184万9861人で、2018年末の5182万6059人より2万3802人増えた。人口は着実に増えているが、増加幅は大きく減り、2013年以降7年連続で5100万人台を維持している。
訳H.J