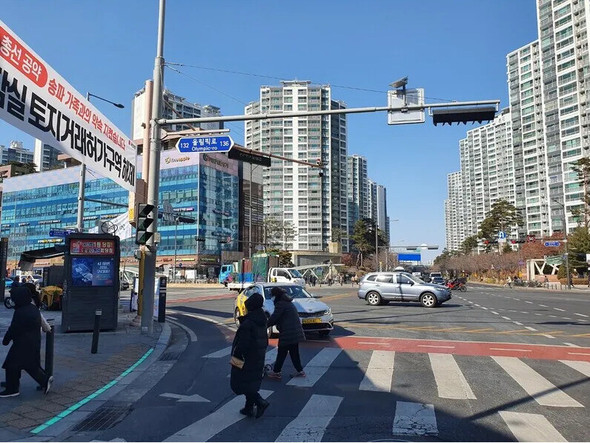‘1産業1産別労組’原則 崩れ
政治勢力化も組合員の共感を得られず
大企業正規職中心に切り回され
非正規職 組織化主体 不足
"18年 旗を再び立てるべき" 指摘も
去る3月20日、京畿道(キョンギド)果川市(クァチョンシ)市民会館。 全国民主労働組合総連盟(民主労総)代議員500人余りが集まった席で、全国学校非正規職労組(学非労組)組合員30人余りが涙で訴えた。 「どうか民主労総に残れるようにして下さい。 5月までに(所属する)連盟を定められなければ出て行かなければならないんです。」 19年間、学校調理士として働いてきたパク・クムジャ学非労組委員長と組合員たちは「民主労総が口では非正規職のためと言いながら、反対に非正規職労組を追い出すというのが話になるか。 私たちは学校現場でも冷遇され、今度は民主労総でもこのように冷遇されなければならないのか」と悔しさを爆発させた。
学非労組組合員の99%は非正規職女性労働者で、ほとんどが40~50代だ。 パク委員長も2010年に光州(クァンジュ)・全南(チョンナム)地域の学校現場を足で回って労組を作った。 2011年4月に学非労組をスタートさせ、2年で非正規職女性労働者を2万7000人近く組織し遂げた。 学非労組は給食室の栄養士・調理士・料理員と司書・行政補助員・スポーツ講師など80ヶ余りの職業群で構成されているが、給食室組合員が最も多い。
メーデーの1日、パク・クムジャ学非労組委員長は「民主労総は非正規職を組織化すると言って去る数年間に20億ウォン余りを使ったが、やっと数千人を引き込むのに終わった。 私たちはわずか2年で3万人近い女性非正規職を組織した。 民主労総より私たちの方がはるかに大きな仕事をしたわけだ」として、さびしさを隠さなかった。
民主労総に加入しようとする学非労組に対し、民主労総は去る1月「既存16ヶの傘下連盟の中の1ヶ所に加入しなければ規約の則り措置する」と決めた。 追い出すこともありうるという話だ。 学非労組は昨年1月、民主労総中央執行委員会の決定により全国教育労組協議会(全教組・大学労組など教育関連労組の集い)に参加して民主労総構成員としての権利と義務を行使してきた。 中央執行委員会は2013年定期代議員大会前までに学非労組を含む全国教育労組連盟(仮称)を結成するという決定も下した。 だが、全国教育労組連盟は結局失敗に終わった。 参加労組らが各自の特殊性を前面に出して連盟を結成することに煮え切らない反応を示したためだ。 学非労組はいっそ独自に17番目の新たな連盟を作ろうとしたが、民主労総は大きい単位の産別労組を指向するという原則に合わないという理由で拒否している。
総連盟である民主労総が仲裁力を発揮できない間に、すでに組織された非正規職労働者2万7000人余りが民主労総を去らなければならない境遇に置かれた。 このような状況のために、創立18年をむかえた民主労総が今どこに立っているのかという疑問を提起する声が労働現場から上がっている。
それだけではない。 来る4日にはチェ・ビョンスン、チョン・ウィボン氏など現代自動車社内下請け労働者の鉄塔籠城が200日をむかえる上に、双龍(サンヨン)自動車労働者の死の行列が絶えないなど重大な労働懸案は山積みであるにも関わらず、労働現場で民主労総が見えないという批判が出ている。 労働核心懸案で存在感を失ったわけだ。
状況がこのようになったのは、昨年11月初めキム・ヨンフン委員長が辞退した後、6ヵ月にわたり続いている民主労総指導部の空白状態が大きな役割を果たした。 民主労総は4月23日ソウル蘆原(ノウォン)区民会館で臨時代議員大会を開きイ・ガビョン-カン・ジンス(委員長-事務総長)候補パートナーに対する賛否投票を行ったが、投票者数が在籍過半数に至らず指導部選出が失敗に終わった。 投票者数未達で指導部選出に失敗したのは今回が初めてだ。
労働界はこれについて民主労総の慢性的問題である政派争いと大衆性喪失が呼び起こした惨禍と見ている。 まず当日の代議員大会自体がかろうじて成立した。 918人の代議員中でかろうじて半分を越える人員が参加し代議員大会が成立した。 指導部選出という政治的に最も重要な行事の参加率が低調だったのだ。 代議員の無関心がどんな水準なのかを知ることが出来る。
更に、投票数が在籍人員の過半数に至らず開票さえできずに指導部選出に失敗した点は政派争いの結果という解釈が優勢だ。 代議員大会に出席はしたものの投票はしないことによってイ・ガビョン候補組が単独出馬した選挙自体を無にし、再選挙を誘導しようとする一部政派が意図的にしたことという指摘が出ている。 これら政派が時代の変化について行くことができない結果として大衆から遊離したという評価は昨年7月に民主労総が開いた‘労働運動と政派’討論会でも指摘された。 すなわち‘労働解放、変革、自主民主統一’等1980年代式の抽象的目標では21世紀の現実で大衆を説得できないという評価とともに、長期的戦略の樹立よりは他の政派を非難して困難に陥れ自らの存在を強化させる悪循環が続いているという苛酷な評価が出てきた。
出席はしながらも投票しなかった学非労組の一部代議員たちも責任を免れない。 学費労組関係者は 「代議員大会には代議員16人の内5人が参加したが、午後2時の予定時刻を過ぎて3時30分頃に会議が始まったせいで投票できずに出てきた。 6月の全面ストライキ闘争を控えて午後4時から学校別全面ストライキ準備会を進めるためだった」と釈明した。
より根本的には民主労総が1995年に結成された時に目標にした‘産別労組体制への転換’がうまく軌道に乗らないせいだという分析も出ている。 産別労組は事業場単位の労働運動を抜け出し、同一産業に単一な1個の労組を作り共同対応するという‘1産業1産別労組’原則を前面に掲げた。 だが、金属と保健医療などを除いては時間が経過しながら‘形だけの産別’であり、実質的には事業場単位労組と変わらないという批判が提起された。 1産業1産別労組原則も不明瞭になっていった。 現在、民主労総の16ヶある連盟中、公共連盟と金属労組には分類上は他の産別連盟に属さなければならない労組が混入している。
‘企業フレンドリー’を前面に出した李明博政府の‘労働組合および労働関係調整法’改正も産別体制弱化に大きな役割を果たした。 以前は労組専従者の賃金問題を労使が自律的に協議していたが、法改正以後は組合員数に連動して政府が決める人数以上の専従者を置けないようになった。 上級労組に常勤者を派遣する際も、全て組合費で賃金を支給しなければならなくなった結果、財政負担のせいで産別労組運動も弱まったわけだ。 その影響で民主労総は常勤者40人余りの賃金が2ヶ月分以上未払いとなっている状態だ。
ハン・ジウォン労働者運動研究所研究室長は「産別労組を通じて公共部門は政府を相手に、民間部門は使用者団体を相手に中央交渉を行うことが目標であった。 これを通じて非正規職問題のような超企業的問題を解決するつもりであったのに、金属・保健・公共部門などでの交渉は不安定で、使用者側は一貫して交渉を忌避している。 民主労総の指針が産別に降ろされ懸案が解決されなければならないが、現実はそうではない」と話した。 民主労総が16ヶの連盟を引き寄せる求心力を発揮できなくなっているという話だ。
18年前、労働者の団結を掲げた民主労総の旗が、この間に大きく毀損されたという批判も起きている。 大企業労組中心の活動が主軸を形成した結果、非正規職問題を積極的に抱えられすにいるという指摘だ。 キム・スンホ‘チョン・テイルに学ぶサイバー労働大学’代表は「民主労総が大企業正規職中心であるため非正規職を組織化する主体が不足したようだ。 民主労総が内部の多様な運動団体を認めることが必要だ」と話した。
労働界では民主労総がこの際‘リモデリングを越えて、原点からやり直さなければならない’という主張が出ている。 キム・スンホ代表は「キム・ヨンフン前委員長が力を込めた民主労総の政治勢力化は完全に失敗した。 60万組合員を持って政治勢力化すれば執権できるだろうか? 組織の力を大きくし強化することが一層重要だ。 政治勢力化の失敗に対する正確な評価と省察があってこそ民主労総が新しく生まれ変わることができる」と強調した。 批判の接点は民主労総上層部の変化要求につながる。 イ・ナムシン非正規労働センター所長は「民主労総が中小零細未組織・非正規職の戦略組織化事業をすることにしたことは正しい。 正規職事業場で非正規職を組織することが重要だが、これができていない。 そのためには政派葛藤を乗り越えて統合的役割をする指導部が先ずできなければならない」と強調した。
政派間の葛藤を越えて産別労組運動の旗を再び立てると同時に、非正規職労働者を積極的に組織化していくためには、民主労総の前に数多くの課題が置かれているわけだ。
ソン・ジュンヒョン記者 dust@hani.co.kr
訳J.S(4087字)