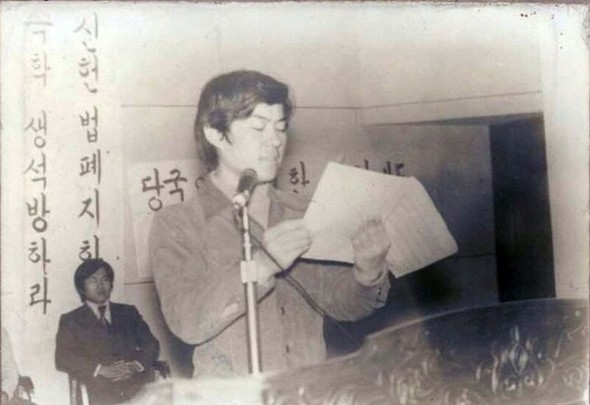日本で競売にかけられそうになった景福宮「璿源殿」の扁額、108年ぶりに帰還=韓国
1916年に日本山口県に流出、昨年返還

108年間、日本の地に留められていた。
朝鮮王朝の歴代王の肖像画を奉安し儀礼を行った聖域、朝鮮の法宮の景福宮で最も尊い建物として崇められた璿源殿(ソンウォンジョン)は悲しい運命にあった。この殿閣の正面にあった建物の名札である扁額の隠れた受難史が明らかになった。
国家遺産庁と国外所在文化遺産財団(以下、財団)は3日、1910年代に景福宮の璿源殿が日本の朝鮮総督府の蛮行で撤去された後、行方が分からなくなっていた璿源殿の木の扁額が、日本本土の本州の西端にある山口県に100年以上保管されてきたことを最近確認し、交渉を通じて還収したと発表した。
財団側は「2023年に山口県の所蔵者が競売に遺物を出品する予定だという事実をあらかじめ把握し、直接購入交渉を行い、ゲーム会社ライアットゲームズの支援で買い入れ、昨年2月に韓国に持ち込んだ」と説明した。
帰還した扁額遺物は、19世紀末、高宗の景福宮再建当時、宮域の北東側に璿源殿を建てる時に作られたものと推定される。縦140センチ、横312センチで黒く漆塗りした土台板に王室を象徴する「玉」の根源という意味を持つ「璿源」の文字が金色で刻まれている。金泥で書いた金字を載せ、殿閣の神聖な地位に合わせて四辺に突き出た枠で囲み、その上に扇やポジャギ(包む布)などの七宝模様を彩色して描き入れ、縁起の良い意味を強調した。扁額の四方の縁に長く突き出た部分は棒と雲の形を立体的に造形し、品格と様式美を見せてくれる。
朝鮮時代の王命と実行、朝廷の行政などを記録した「承政院日記」によれば、1868年に再建した景福宮の璿源殿の扁額は徐承輔(ソ・スンボ、1814~1877)が字を書いたと記されている。専門家が還収された扁額から筆画など書体の特性を調べた結果、徐承輔の字と推定されるとの結論が出たと国家遺産庁は明らかにした。扁額に使われた顔料を科学的に分析した結果、1900年に景福宮と昌徳宮の璿源殿の工事を記録した儀軌に出てくる材料とも大部分一致するという結果も出たという。
2023年12月に扁額を出品した競売会社側は、「19世紀の景福宮璿源殿の扁額」とし、日本による植民地時代に初代朝鮮総督を務めた寺内正毅(1852~1919)と関連があると説明資料で明らかにしたという。寺内総督が1916年に故郷の山口に戻った時、景福宮の一部(建物)を撤去・移転し、1942年に台風で建物が破壊され撤去する当時の作業に参加したある職員が今まで遺物を保管してきたということだ。
財団側は「競売会社の説明資料を見て経緯を把握した後、所蔵者側と直接やり取りをしながら、朝鮮王室の文化遺産である扁額は必ず韓国に戻さなければならないという趣旨を説得した」とし「扁額の具体的な搬出経緯についてはさらなる調査をしなければならないものとみられる」と明らかにした。
明確に外勢によって流出した朝鮮王室の遺産であるにもかかわらず、還収過程で数億ウォン台の巨額を払って買い入れたことが知られ、議論も起こる見通しだ。文化財界では、国外の私設機関や個人の収蔵者が朝鮮王室の遺産を持っている場合、後続交渉と還収過程について公開的な議論と再検討を通じて、新たに共感を得る努力が必要だという意見が出ている。
景福宮の璿源殿と付属殿閣は、1897年に高宗(在位1863~1907)が慶運宮(徳寿宮)に住居を移して空いていたところへ、韓日併合後に少しずつ撤去され、1932年に朝鮮総督府が安重根義士により射殺された初代朝鮮統監の伊藤博文(1841~1909)を追悼するために当時ソウル奨忠洞に建てた博文寺の資材に使うためほとんどが撤去されたものと推定されている。
1966年、朴正煕(パク・チョンヒ)政権が国立総合博物館の建設を推進し、璿源殿の圏域の旧殿閣9棟を取り壊し、痕跡が完全に消えた。1971年にこの場所に法住寺捌相殿と仏国寺の石垣などを組み合わせた建物である国立中央博物館が建設され、1993年に国立民俗博物館に変わり、今に至る。国家遺産庁は、景福宮の復元計画に沿って民俗博物館が数年内に世宗市に移転すれば、遺構調査を経て2030年から璿源殿の復元事業に着手し、還収した扁額を復元した建物に懸ける計画だ。
扁額の実物は27日午前、ソウル景福宮の国立古宮博物館でメディアに公開される。
訳J.S