[私の書斎の中の古典] 生き残ったことの「罪」、人間であることの「恥」、それでもきっと「希望」は?
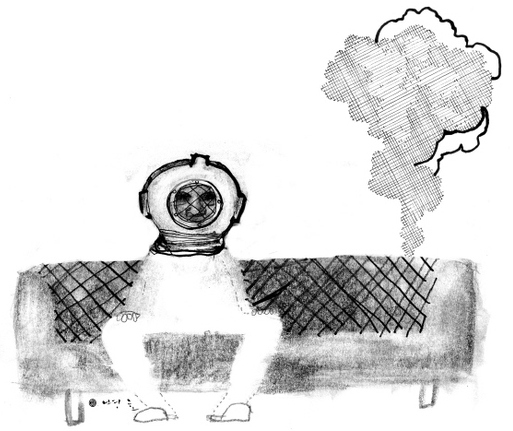

溺れるものと救われるもの
プリーモ・レーヴィ著、竹山博英 訳
朝日新聞社 1500円
私の書斎の一隅はナチズムとホロコースト(ユダヤ人虐殺)に関する書籍で埋められている。数十冊かそれ以上におよぶそれらの中から一冊だけ推薦せよと求められたら、私はプリーモ・レーヴィの『溺れるものと救われるもの』(Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, Einaudi, Torino Italy, 1986)を挙げるだろう。
若い頃もいまも、「絶望」という感情は私にはなじみ深いものだが、その感情の中身は確実に違ってきている。いま思えば、かつては高く厚い壁に閉じ込められているようで、どこにも出口が見当たらなかった。人々は「事実」を知らないのだ、と若い頃の私は思っていた。ここで「事実」といったのは、さしあたり、日本による朝鮮植民地支配と現在も続く在日朝鮮人差別のことであり、また当時の韓国軍事独裁体制のリアリティを指すが、それにとどまらず、南アのアパルトヘイト体制やイスラエルのパレスチナ人抑圧など、世界に遍在する非人道的反人権的な現実を指す。
人々が事実を知り、論理的に考えることができさえすれば、こんなことがいつまでも放置されることはないはずだ。漠然とそう思っていた。私の絶望感の核心にあったのは、自分が閉じ込められているため人々に事実を知らせることができない、閉じ込められたまま人生が終わってしまうかもしれない、そういう焦燥感だった。だが、若かった私には「時間」というあいまいな「出口」があった。生きてさえいれば時間が経過して状況が変化し、この壁の外に出ることができるかもしれないという根拠のない期待が、まだ残されていた。幸運というべきだろうが、時間が経過し、私は壁の外に出ることができた。そう思った。しかし、いまも私は絶望と縁を切ることができない。
人々は事実を知らないのではなく
知ることを拒否する
レーヴィはアウシュビッツ経験から
ナチに限定されない人間存在の危機を見た
今でもこの本を取り出すのは
安易な‘希望’に目を曇らせたくないからだ
日本では昨年末、右派政権が高い支持を受けて成立した。この政権はわずか2年前に起こった破局的な原発事故がまだ収束する見通しすらないのに、世界各地への原発輸出に余念がない。その際のうたい文句は「世界一安全な日本の原発技術」というのだ。これが図々しい嘘であることを、人々は知らないのだろうか?
テレビタレントから全国政党のリーダーにのし上がった大阪市長は、沖縄駐留米兵の性犯罪防止のため地元の風俗産業を活用することを米軍司令官に推奨した。そのことが問題化されると論点を日本軍慰安婦制度にズラし、これも批判を浴びると「真意を誤報された」とマスコミに責任を転嫁した。その不見識を外国や国際機関から批判されるとさらに論点をスリ替え、世界から日本だけが誤解され敵視されていると、まるで自分が日本の名誉のために闘っているかのように主張している。これがまったく理屈に合わない強弁であることを、人々は知らないのだろうか?
日本では極右団体が毎週、「朝鮮人を殺せ」とか「韓国人は出ていけ」とか野卑な叫びを繰り返しながら繁華街でデモするようになった。国連人種差別禁止条約が明白に禁止しているヘイトクライムであり、さすがの日本政府も表向きには眉をひそめてみせたが、デモは一向に収まる気配がない。彼らの主張は「在日朝鮮人は不当な特権をむさぼって日本人を脅かしている」というものだ。これが幼稚な嘘であることを、人々は知らないのだろうか?ほんとうの「朝鮮人」がどういう存在であるのかなど、彼らにとってどうでもよいのだ。「朝鮮人」というのは、暴力的なコメディで「悪役」に与えられる記号に過ぎないのだから。
多くの人々が、総理大臣から極右団体にいたるまでの非論理的で反倫理的な主張を、まるで劇場でコメディをみるように観客席から楽しんでいる。人々の関心事は論理的整合性や倫理的正当性などではない。面白ければよいのだ。現実はもはやコメディの域を逸脱して、平和や人間の尊厳といった価値を深刻に脅かしている。だが、人々はそんなことには関心がない。この人々は事実を知らないのではなく、知ることを拒絶しているのだ。事実を見つめて論理的に考えることができないのではなく、目先の私利私欲、卑屈な保身、知的怠慢と無気力、歪んだ自己愛、その他もろもろの理由でそれを拒否しているのである。
1990年代にはいって、もと日本軍慰安婦など長い間沈黙を強いられてきた被害当事者たちが声をあげ始めた。人々は事実を知る機会を与えられたのだ。しかし、20数年後の現在、目の前に広がっているのは、(韓国のことはさて措くとして)無残な日本社会の現実である。ことは日本社会にかぎらない。差別、不寛容、暴力が世界の各地で凱歌を上げつつある。
いまも私は絶望しているが、この感覚は若い頃とは違う。かつてのような外側から閉じ込められているのではなく、内側から執拗に疲労感と空虚感に蝕まれる感覚である。このような感覚は、いくらかはプリーモ・レーヴィに影響されたものであることを、私は認める。彼はアウシュヴィッツからの生還直後に「これが人間か」を書き、それからおよそ40年間を誠実な証言者として生きた後、『溺れるものと救われるもの』を出した翌年の1987年、自殺した。本書を貫いているのは、強制収容所経験のより透徹した考察であり、人間存在に対するより妥協のない認識であり、したがって、より深い絶望感である。それに比べれば、私の絶望など、とるに足りない。
「これが人間か」(日本語の訳書名は「アウシュヴィッツは終わらない」)を私は1980年に読んだ。私は日本にいたが兄二人は韓国の獄中にあり、時は光州5・18の最中で、母は末期ガンで死の床にあった。10年ちかく後に韓国で軍政時代が終了し、兄たちは解放された。私は大学の教壇に立つようになり、少しずつ著書も出す立場になった。壁の外に出て社会的に発信する機会を得たのである。数年が経って、レーヴィが自殺したことを知った。
1990年代半ば、ある有名出版社の渾大防三恵(こんだいぼう・みえ)さんという編集者と知り合った。彼女はもともと「これが人間か」の出版を手がけた人で、つまり日本におけるレーヴィ紹介の功労者だった。そんな人からレーヴィについて書いてみないかと提案された私は、もてる力のすべてを注いで「プリーモ・レーヴィへの旅」という著書に取り組んだ。そのためにトリノにもアウシュヴィッツにも足を運んだ。その本を書いている途中で、どうしても読まなければならないのにまだ日本語に訳されていない本があった。『溺れるものと救われるもの』である。渾大防さんが何年も前から翻訳出版の企画を温めていたのだが、まだ実現していなかった。仕方なく私は辞書を引き引き英語版(The Drowned and the Saved)を読んだ。そして、心が激しく震えた。「この人は自殺するしかなかったな…」と深く納得させられた。自殺すべきでなかったとか、生きていてほしかった、などという思いではない。
この本によってナチ犯罪の罪の深さ、真の恐ろしさにあらためて震撼したということはもちろんあるが、それ以上に、この本は「ナチの」と限定できない広がりと深さで人間存在そのものの危機をえぐり出していた。レーヴィはここで自分自身のルサンチマン(怨恨)を吐露したりはしない。「神」や「運命」といった超越的な観念を作り出して、それに怒りや悲しみをぶつけたり、慰めを求めたりもしない。それどころか、自分自身をも容赦なく切り開くのだ。彼はただ、深い絶望の諸相を科学者のような手つきで解剖する。冷酷とすらいえいる分析と記述が、あくまでも知的に、ときにはユーモラスに進められる。レーヴィが人生の最後にこの本を残したのは、他人に事実を知らせ、理解させるためですらないと私は思う。「人は証言に耳を貸さない」という証言を、その人たちに向かって語りかけてなんの意味があるだろうか。それでも、彼はこの証言を書き残した。個人の生物学的生命以上の価値(さしあたり「真実」と呼んでおくしかない)のために。そうやってレーヴィは、たとえどんなに絶望的なものであっても真実を見きわめようとすることの、そう言ってよければ、「ほんものの知的喜び」をも私たちに与えてくれるのである。
出来上がった私の著書のカヴァーにこんなキャッチフレーズが書かれていた。《生き残ったことの「罪」、人間であることの「恥」、それでもきっと「希望」はある…》渾大防さんが考えた文章だ。「希望はある」という部分に私は抵抗し、せめて「希望はあるか?」と疑問形にしてほしいと頼んだのだが、最後には妥協してしまった。そのことを、いまでも後悔している。

私の本は1999年に刊行され、渾大防さんの執念が実って『溺れるものと救われるもの』日本語版も翌2000年にようやく刊行された。その5,6年後、渾大防さんは交通事故であっけなく急死した。それからさらに2,3年後、私は所用でその出版社に電話をかけた。電話に出た書籍編集部員は私を知らないようだったが、それはよくあることだ。だが、渾大防さんの名を挙げても、彼女のことも知らなかった。「その人は外部委託の編集者だったのですか?」などと言う。30年ほども在社してプリーモ・レーヴィを日本社会に紹介するという文化的功績を残した人物を社内の後輩すら知らないのだ。この会社も他の出版社と同じように、目先の販売実績が見える本の出版へと方向転換していたのである。このように、レーヴィという存在を知ることを拒否し、その警告に顔をそむけて、救いのない深淵にすすんで堕ちてゆくのである。
私がいまでも折に触れて書棚からこの本を取り出すのは、安易な「希望」に眼を曇らされたくないからだ。『溺れるものと救われるもの』は日本では品切れ絶版である。韓国でも数年前から翻訳出版の企画はあるが、まだ実現していない。
(4359字)

