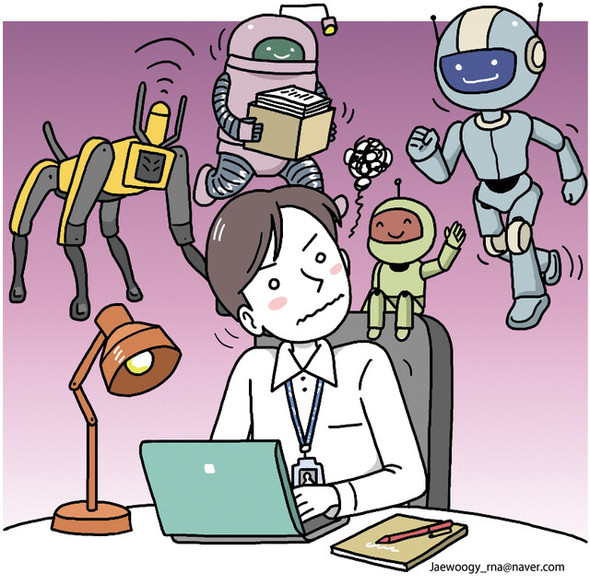原文入力:2011/11/21 19:03(1050字)
金融危機後、世界各国は金融消費者保護制度を強化する側に金融改革を推進している。 わが政府も金融消費者保護の素案を明らかにした。 金融監督院から消費者保護機能を切り離して‘金融消費者保護院’(金消院)という組織を新しく作り、不公正や略奪的な営業行為に対する処罰程度を高めるというのが主な柱だ。 だが、市場の反応は冷たいようだ。 形だけ整えた消費者保護対策という評価が多い。
昨日金融委員会が立法を予告した‘金融委員会設置などに関する法律改正案’と‘金融消費者保護に関する法律制定案’を見れば、何より 金消院の独立性に疑問を感じる。 金融委は金消院を‘准独立機構’と言っているが人事と予算はもちろん業務面でも金融委と金融監督院の影響が及びえることになっている。 そのうえ、金融監督院と同じように運営予算の大部分を金融会社から受ける分担金と手数料収入に依存し、業界からの独立性すら整えられずにいる。
金消院には金融会社を圧迫しうる検査権や制裁権もない。 問題が生ずれば金融会社に‘事実確認’次元の調査をして金融委や金融監督院に措置を建議できる権限しかない。金消院の役職員の裁量で積極的な消費者保護に出ることも難しい。 業界ではすでに金融監督院と金消院の重複規制にともなう市場混乱を憂慮している。
金融市場は常に供給者と需要者の間に情報の非対称性が存在する場だ。 情報力で優位にある供給者は市場で常に一方的に有利で、交渉力が特にない多くの金融消費者は自分の利益に合う最善の意志決定はできない。 そのために金融市場は消費者保護のための公的機能が必ず必要だ。
しかし今まで我が国の金融当局は金融産業育成に優先順位を置くあまり、消費者保護は後まわしにしていた。李明博政府の発足後は専門知識に乏しい‘天下り’達が監督機構の主要職務に大勢つき、権力者の機嫌だけうかがい、監督当局と金融業界の癒着はさらに深刻になった。 いまだ後遺症が残っている貯蓄銀行不良事態、問題化のおそれがある銀行や保険会社のいいかげんな販売被害は金融監督の総体的な欠陥がもたらした結果だ。 金融当局が本当に金融消費者保護の意志があるならば監督体系と規制の枠組みを根本的に構築する姿勢で臨まなければならない。
原文: 訳T.W