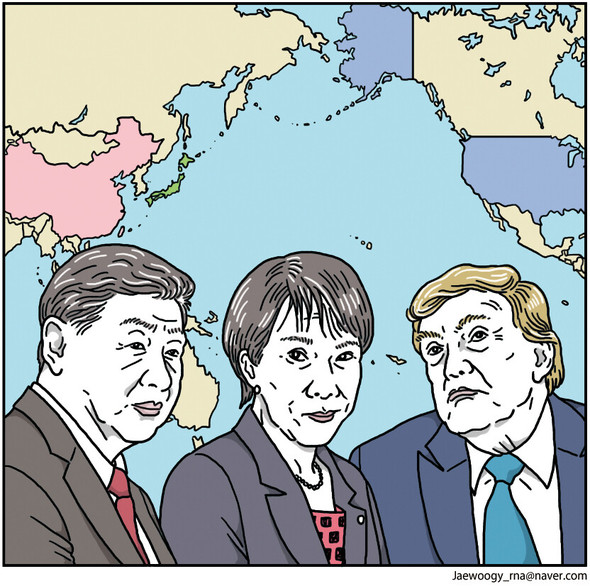原文入力:2011/04/29午前02:33(3442字)
朴露子(バク・ノジャ、Vladimir Tikhonov)ノルウェー、オスロ国立大教授・韓国学
学会参加のため訪れていた韓国から昨夜帰ってきました。国内滞在中はひどい風邪で苦労していたので、出国して飛行機に乗った時もその後遺症にずいぶん悩まされましたが、機内で非常に効率的に「読書療法」を利用することができました。私の場合は、個人的に好感が持てる本を読めば、気持ちがさわやかになり体の具合まで肯定的に影響される傾向があります。ということで、風邪をひく時は、よくソ連初期の真の意味での共産主義的な作家アンドレイ・プラトーノフ()の『チェヴェングール』(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80)のような、自我と他者の境界を無化することにより、ついに生と死の境界さえも超越していくロシア革命初期の共産闘士の物語を読みながら体の回復を促進させたりします。余談ですが、『チェヴェングール』が未だに韓訳されていないことは国内のロシア文学界の大恥です。一時イタリアの偉大な左翼作家で映画監督のピエル・パゾリーニを感動させたといわれているこの小説を読まないかぎり、たとえば共産主義のキリスト教的な起源のようなものを理解するのは困難です。実際、たとえ拳銃を常に忍ばせ、しばしば使ったりするものの、「ぬくもりを惜しまない太陽のように、自分のすべてを惜しまずに皆と分けることにより宇宙を暖かくしようとする」『チェヴェングール』の主人公たちは、イエス・キリストとその使徒たちの現代的な変形に近いともいえます。しかし、渡米留学派やドイツで保守的なスラブ学を学んだ方々に主導されている国内のロシア文学界に、共産主義の魅力を充分に伝える小説に注意を傾けてほしいと訴えることは、サハラ砂漠で水を求めるのと同じようなものではないかと思ったりします。いや、余談が長くなってしまいましたね。
今回私が機内で『チェヴェングール』の代りに読んだ「治療用図書」は、3年前に知識旅行社から出た『布施辰治 - 朝鮮のために一生を捧げた』という本でした。布施辰治(1880~1953)は、近代日本の代表的「良心」といわれている方です。売れっ子の弁護士として出発し1910年代末にはすでに東京の法曹界の大物になった彼は、3・1運動と日本国内の米騒動、そして遠くのロシア革命やドイツ革命の影響を受け、1920年に「自己革命」を宣言し、本格的な人権派弁護士としての新たな人生をスタートしました。彼は日本国内でストライキを決行し敗れてしまった東京市電の労働者のような弱者たちも誠実に弁護しましたが、特に植民化された朝鮮や台湾の人々と自分をほとんど同一視し、重要な独立運動が起こるたびに彼らと共にありました。彼は全羅南道羅州郡宮三面で争議を起こした農民を弁護しただけでなく、アナーキスト・朴烈やアナーキズム系列の義烈団から朴憲永などの法廷に立たされた朝鮮共産党の指導者たちにいたるまで、ありとあらゆる人々の弁護を引き受けたのです。彼自身は社民主義系列の日本の合法的な左翼政党に属していましたが、朝鮮に関する彼の意見はむしろ共産主義者やアナーキストたちの分析により近かったのです。すなわち、彼は朝鮮の植民化を「資本主義的帝国主義侵略」と規定し朝鮮民衆の解放問題を世界民衆解放運動の一環として捉え、朝鮮の無産者と日本の無産者との連帯が急がれると訴えました。絶え間ない無産者弁護の活動で彼が何度か逮捕や拘禁にあい、結局1930年代中盤以降は弁護士活動の機会を失い敗戦まで窮乏生活を強いられました。売れっ子弁護士が自ら進んで無産者たちと連帯して戦っているうちに本人もほとんど無産者になったので、真の意味の良心と言わなければならないでしょう。
さて、ここで一つ重要な問題が浮かび上がってきます。一時支配者側に近かった人は、いかにして無産者たちと運命を共にするようになったのでしょうか。もちろん、幼い頃から儒教的な普遍主義を身に付け、後にトルストイの博愛主義にどっぶりとはまった布施先生の個性も作用したはずですが、単にそれだけで説明するのは難しいです。実際のところ、自ら進んで無産者の闘いに合流し自分の階級的な位置さえもほとんど犠牲にすることは、儒教的な教育を受けトルストイに憧れた開明的な有名知識人の間でも決してよくあることではありません。李光洙や崔南善はトルストイが好きではなかったのでしょうか。階級社会の論理からは奇蹟に近いことなのですが、このことは単に一有名知識人の個人的な信念だけで解明しうる問題ではありません。一時進歩的な信念を仄めかしていたかと思ったら急に『朝鮮日報』の寄稿者に転落してしまった教授たちを、私たちは最近数十人近く見てきたのではありませんか。信念もさることながら、有名な有産階級の知識人をして「下の階級」の闘争に合流するように仕向けたのは、結局ある「力」の作用でもあります。それは単なる物理力のことではなく、思想体系と組職体系の力を意味します。支配者側に属しながらも魂がまだ生きている有名知識人は、「下」ではその魂の理想などを具体的に実践できる思想展開の論理があり、その理想のために闘いうる組織的な闘争の隊伍があることを目の当たりにすれば、結局 統治者側を立派に裏切ることもできるということです。裏切って合流しうる隊伍があることに気付けばということなのです。しかし、「下」での思想体系がうまく掴みきれず闘争や組織化の動きが積極的でなければ、支配者側に属する知識人としてはどうしてもその良心を社会的に生かすことは難しいのです。
布施は日露戦争に反対するトルストイの文をすでに1904年に『平民新聞』で読みました。つまり、彼は早くから平民社という初期社会主義者たちの集団が存在することを知りました。その後、彼は1911年に幸徳秋水先生の公判を傍聴するなど、初期社会主義者たちの思想と彼らに対する弾圧の様子をすでに知っていました。以後、彼は日本で労働組合、農民組合と緊密に協議しており、朝鮮では彼の講演会を社会主義団体の北星会が支援しました。このように、こちらの階級闘争勢力がすでに組職され活動していたため、布施のような名望家も民衆の味方になることが遥かに容易かったのです。もちろん彼の良心も一役買っていましたが、私たちが彼のことを考える際に、単に彼の良心のみを讃えるのではなく、彼を魅了させた日本と朝鮮の民衆闘士たちの血を流す努力と犠牲を先ず思い起こさなければなりません。「下」のこのような努力がなかったら、名望家の「良心」はそんなに簡単に発現したりしなかったはずです。全泰壱(チョン・テイル、1948~1970)が存在しなかったら保守的なキリスト教自由主義者 咸錫憲(ハム・ソクホン、1901~1989)は果してシアル(訳注:種粒のことで「民衆」を意味する土着語)思想の哲学者になれたでしょうか。ここで方法論的に重要な部分は、歴史を眺め評価する際は名望家を中心に見るのではなく、民衆の組職と闘争、民衆思想の形成に主眼を置かなければならないということです。そうしてこそ、歴史は名望家の「良心」だけの歴史ではなく無数の民草たちの闘いの歴史、すなわち真の意味の歴史として照らし出されるのです。
追伸1:一つ誤解を避けるために申し添えます。咸錫憲先生は既に1930年代の独自的な宗教哲学者として形成された方であり、1960年代には彼なりの民衆主義的哲学を一定程度、理念的/理論的次元で体系化しました。しかし、彼が抽象的な「民衆本位」思考からシアル哲学に裏付けられた積極的行動に転換するに際しては、全泰壱の焚身「事件」が大きな役割を果たしたことは良く知られた事実です。咸錫憲が積極的な民衆運動に転換するにあたって全泰壱事件が及ぼした影響については、イ・チソク,<シアル 咸錫憲 評伝>,時代の窓,2005,P.545-556参照。