еӣҪйҖЈгҖҢеҢ—жңқй®®дҪҸж°‘гҖҒпј”пјҳ%гҒҢж „йӨҠдёҚи¶ігҖҚвҖҰд№іе№је…җгҒ®пј’пјҷ%гҒ гҒ‘гҒҢйҒ©жӯЈж‘ӮеҸ–
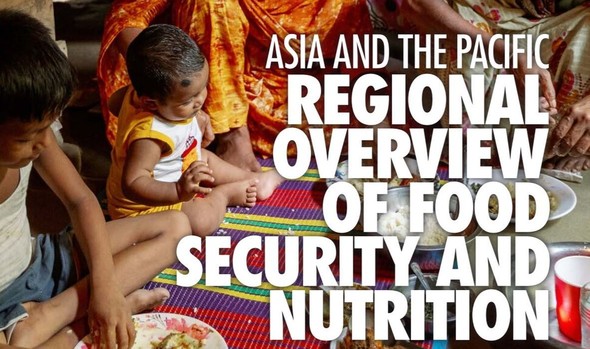
гҖҖеҢ—жңқй®®дҪҸж°‘гҒ®зҙ„еҚҠж•°гҒҢж „йӨҠдёҚи¶ігҒ«иӢҰгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮж „йӨҠж¬ д№ҸдәәеҸЈгҒ®еүІеҗҲгҒҜгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ§жңҖгӮӮй«ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӣҪйҖЈеӮҳдёӢгҒ®йЈҹзі§иҫІжҘӯж©ҹй–ўпјҲFAOпјүгӮ„дё–з•ҢйЈҹзі§иЁҲз”»пјҲWFPпјүгҖҒдё–з•ҢдҝқеҒҘж©ҹй–ўпјҲWHOпјүгҖҒгғҰгғӢгӮ»гғ•пјҲUNICEFпјүгҒҢ20ж—ҘпјҲзҸҫең°жҷӮй–“пјүгҒ«е…ұеҗҢзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖҢгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®йЈҹзі§е®үе…ЁдҝқйҡңгҒЁж „йӨҠгҒ®жҰӮиҰҒ2020пјҡж „йӨҠж”№е–„гҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒӮгӮӢжҜҚеӯҗгҒ®йЈҹз”ҹжҙ»гҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒ2017пҪһ2019е№ҙгҒ«еҢ—жңқй®®дҪҸж°‘гҒ®47.6%гҒҢж „йӨҠеӨұиӘҝгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҗҢжңҹй–“гҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹ30гӮ«еӣҪд»ҘдёҠгҒ®иӘҝжҹ»еҜҫиұЎеӣҪгҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮй«ҳгҒ„ж•°еҖӨгҒ гҖӮжқұгғҶгӮЈгғўгғјгғ«пјҲ30.9%пјүгҖҒгӮўгғ•гӮ¬гғӢгӮ№гӮҝгғіпјҲ29.9%пјүгҖҒгғўгғігӮҙгғ«пјҲ21.3%пјүгҒҢеҢ—жңқй®®гҒ®еҫҢгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒж „йӨҠдёҚи¶ідәәеҸЈгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҗҢе ұе‘ҠжӣёгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеҢ—жңқй®®гҒ®6пҪһ23гӮ«жңҲгҒ®д№іе№је…җгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒгҖҢжңҖдҪҺйЈҹдәӢж°ҙжә–гҖҚпјҲMAD=Minimum Acceptable Dietпјүд»ҘдёҠгҒ®йЈҹдәӢгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеүІеҗҲгҒҜгӮҸгҒҡгҒӢ28.6%гҒ гҒЈгҒҹгҖӮжңҖдҪҺйЈҹдәӢж°ҙжә–гҒҜгҖҒд№іе№је…җгҒҢйҒ©еҲҮгҒӘж „йӨҠгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢеҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жҢҮжЁҷгҒ§гҖҒгҖҢжңҖдҪҺйЈҹдәӢеӨҡж§ҳжҖ§ж°ҙжә–гҖҚпјҲMDDгғ»Minimum Dietary DiversityпјүгҒЁгҖҢжңҖдҪҺйЈҹдәӢй »еәҰгҖҚпјҲMMFгғ»Minimum Meal FrequencyпјүгӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҰиЁҲз®—гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ1ж—ҘгҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ4гҒӨгҒ®йЈҹе“ҒзҫӨгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒ—гҒҹгҒӢгҒӘгҒ©йЈҹдәӢгҒ®иіӘгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҖҢжңҖдҪҺйЈҹдәӢеӨҡж§ҳжҖ§ж°ҙжә–гҖҚгҒ«еҗҲгҒЈгҒҹйЈҹдәӢгӮ’гҒ—гҒҹеҢ—жңқй®®гҒ®д№іе№је…җгҒҜзҙ„46.7%гҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒ1ж—ҘгҒ«жңҖдҪҺйЈҹдәӢй »еәҰпјҲжҜҚд№іиӮІе…җгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ2пҪһ3еӣһгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜ4еӣһгғ»MMFпјүгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢйЈҹдәӢгӮ’гҒ—гҒҹеҢ—жңқй®®гҒ®д№іе№је…җгҒ®еүІеҗҲгҒҜ75%гҒЁиӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжңҖдҪҺйЈҹдәӢй »еәҰгҒҢзӣёеҜҫзҡ„гҒ«й«ҳгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒеҢ—жңқй®®гҒ§гҒҜ6гӮ«жңҲжңӘжәҖгҒ®д№іе…җгҒ®е®Ңе…ЁжҜҚд№іиӮІе…җзҺҮгҒҢ71.4%гҒ§гҖҒең°еҹҹгҒ§4з•Әзӣ®гҒ«й«ҳгҒ„гҒҹгӮҒгҒЁгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ1жӯігҒҢйҒҺгҒҺгҒҰгӮӮжҜҚд№іиӮІе…җгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢе ҙеҗҲгҒҜ68.8%зЁӢеәҰгҒ§гҖҒеҗҢең°еҹҹгҒ§гҒҜдёӯй–“зЁӢеәҰгӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж•°еҖӨгӮ’з·ҸеҗҲгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҢ—жңқй®®гҒ®д№іе№је…җгҒ®ж „йӨҠдёҚи¶ігҒҜеӨҡж§ҳгҒӘйЈҹе“ҒгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢеҺҹеӣ гҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮзү№гҒ«гҖҢжңҖдҪҺйЈҹдәӢеӨҡж§ҳжҖ§ж°ҙжә–гҖҚгӮ’жәҖгҒҹгҒҷйЈҹдәӢгҒ®е ҙеҗҲгҖҒйғҪеёӮпјҲ53%пјүгҒЁиҫІжқ‘пјҲ37%пјүгҒ®ж је·®гҒҢеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдёӯгҖҒ5жӯіжңӘжәҖгҒ®еҢ—жңқй®®е…җз«ҘгҒ§е№ҙйҪўгҒ«дёҚзӣёеҝңгҒӘдҪҺиә«й•·гҒ®гҖҢзҷәиӮІйҳ»е®ігҖҚпјҲstuntingпјүгҒ®еүІеҗҲгҒҜ19.1%гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®ең°еҹҹ35гӮ«еӣҪгҒ®гҒҶгҒЎ20з•Әзӣ®гӮ’еҚ гӮҒгҒҹгҖӮжқұеҚ—гӮўгӮёгӮўи«ёеӣҪгҒ®е№іеқҮгӮҲгӮҠгҒҜдҪҺгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ5жӯіжңӘжәҖе…җз«ҘгҒ®гҒҶгҒЎиә«й•·гҒ«дёҚзӣёеҝңгҒӘдҪҺдҪ“йҮҚгҒ®гҖҢж¶ҲиҖ—з—ҮгҖҚпјҲwastingпјүе…җз«ҘгҒ®еүІеҗҲгҒҜ2.5%гҒ§гҖҒиӘҝжҹ»еҜҫиұЎеӣҪгҒ®гҒҶгҒЎдҪҺгҒ„ж°ҙжә–гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
иЁіH.J