韓国国立外交院「朝鮮半島や台湾などでの大規模な軍事衝突の可能性は低い」
「2023国際情勢展望」報告書
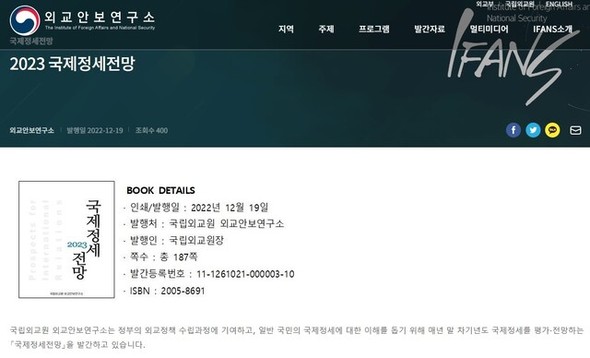
新年も北朝鮮は核武力の強化を続けつつ、いわゆる「責任ある核保有国」の地位を掲げ、非核化交渉を求める声を無視し続けるだろうという見通しが国立外交院から発表された。南北関係も冷え込んだ状態から抜け出せない見通しだ。
外交部付属の国立外交院外交安保研究所は、19日に発表した報告書「2023国際情勢展望」で、「北朝鮮は、対外政策はもちろん経済・社会・文化など全分野にわたって強力な過去回帰政策を本格化しており、第9回党大会の予定される2025年末までは現在の基調を維持するという対内外宣言を繰り返している」とし、「少なくとも今後2~3年間は、『自衛的国防力』と『自立経済』の構築に象徴される現在の路線を維持する公算が高い」と指摘した。
同研究所は「(今年9月に採択された)『核武力政策法』にもとづき、北朝鮮は『責任ある核保有国』の地位を主張しつつ、米国の求める朝米対話と核交渉を無視し続ける見通し」だとし、「韓国に対する挑発的行動を繰り返しながらも、国際社会の対北朝鮮制裁と新型コロナウイルス、洪水などの自然災害という『三重苦』によって、2010年や2017年のような極端な戦争危機と北朝鮮核危機を触発する大規模な挑発を試みる可能性は低いだろう」と指摘した。
そのため、同研究所は、北朝鮮非核化交渉を推し進める動力も「著しく低下する見通し」だとし、「代わって、北朝鮮の核の脅威に対応するための韓米同盟の抑止力強化が対北朝鮮政策の核心となる見通しだ」と述べた。北朝鮮の武力示威と韓米の対抗、これに対する北朝鮮の報復対応という緊張の高まりの「悪循環」が来年も続くということだ。
冷却期に入った南北関係も、突破口を見出すのは容易ではなさそうだ。研究所は「北朝鮮は核武力の高度化を追求するとともに、中国およびロシアとの関係に集中しつつ、南北関係の改善には背を向ける可能性が高い」とし「北朝鮮の態度の変化が先行しなければ南北は平行線をたどらざるをえず、南北関係の停滞は続くだろう」との見通しを示した。
米中の戦略競争の激化も続く見通しだ。研究所は「米国はウクライナ戦争を契機としてロシアの国力を弱体化させつつ、中国との戦略的競争に対する焦点を維持するだろう。そして軍事の革新、同盟の強化、競争的経済政策などを通じて中国に対するけん制を次第に強めるだろう」とし、「中国も米国の攻勢に対応しつつ、大国へと浮上するために軍事力と影響力の強化に向けた積極的外交基調を維持する可能性が高い」と述べた。
ただし研究所は「相互依存的な経済関係や軍備競争の水準などを考慮すると、冷戦的関係が形成される可能性は低い」と指摘した。また「バランスの域外の当事者である米国の力の優位によって、地域体制は全般的な安定を保つだろう」とし「朝鮮半島や台湾などでの大規模な軍事衝突の可能性は低い」と付け加えた。
訳D.K

