キム・ヨンチョル|元統一部長官、仁済大学教授
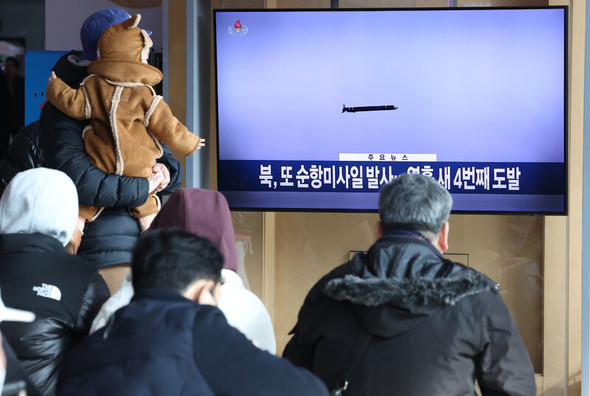
「一つの血筋、一つの言語、一つの歴史、一つの文化を持つ」南と北だと、2018年4月の南北首脳会談の際に金正恩(キム・ジョンウン)委員長は語った。だが今年の最高人民会議では「もはや同族関係ではなく敵対的な二つの国家の関係、戦争中の二つの交戦国の関係」だと規定した。認識の転換は南北関係の悪化を反映しているが、それがすべてではない。実際のところ、民族主義的アプローチはとっくの昔に終わっている。黄昏に残されていたわずかな光がついに消えたに過ぎない。
北朝鮮の民族の概念は二つある。一つは統一言説で、1972年の7・4南北共同声明の「民族大団結」から2000年の6・15共同宣言の「わが民族同士」、2018年の首脳会談の「一つの民族」まで続いた。もう一つは「朝鮮民族」ではなく「北朝鮮民族」だ。金正日(キム・ジョンイル)時代の「金日成(キム・イルソン)民族」や「朝鮮民族第一主義」は北朝鮮の理念、制度、指導者を正当化する概念だ。金正恩時代の「金正日愛国主義」も「金日成民族」概念にもとづくものだ。
北朝鮮の歴史において「わが民族同士」は南北関係が良好だった時期に登場した言説だ。それほど長い歴史を持つものではない。対内的には、体制の正当性言説である「北朝鮮民族」を強調していた時期の方がはるかに長かった。2019年1月に金正恩体制が強調した「我が国第一主義」は、「民族」から「国家」に転換したものではない。二つの民族概念の中の統一言説としての民族概念を廃棄し、「北朝鮮民族」を国家という概念で代替したものだ。
分断後の南北関係も、民族主義的アプローチとは距離がある。朝鮮半島問題が国際化したせいで、いつも国際秩序の変化に影響を受けてきた。これまでに行われた5回の南北首脳会談は一つの例外もなく、朝米関係が良くなり南北米の三角関係が好循環していた時期だったから可能になったものだ。南北の二者関係だけで懸案を解決することはできないからだ。「わが民族同士」は慣性によるスローガンに過ぎず、政策の現実ではなかった。
「統一を目指す暫定的な特殊関係」も終わったのだろうか。「特殊関係」は二つの国家という国際法的な現実と、「民族統一」の未来という二重性をつなげた概念だ。現実と未来とをつなぐかけ橋は関係の水準にあるものだが、未来の扉を閉じてしまえば当然残るのは二つの国家という現実だけだ。もちろん、二つの国は目新しいものではない。国連に加盟した時から国際的に南と北は二つの国家であり、大韓民国政府の公式統一案の肝である南北連合も、文字通り二つの国家の連合だ。重要なのは二つの国家そのものではなく、二つの国家の関係だ。
今は波ではなく、波を起こす風を見るべき時だ。深層から吹いてくる風の動きを読めず、民族主義に訴えていた時期が終わったことを認めるべき時に来ているのだ。金正恩委員長を含む南北の分断第3世代は統一に否定的だ。南北関係の相対的自律性も低下したことで、敵対的な相互認識も肥大化している。「北朝鮮の核問題」を交渉で解決する可能性も急激に低下した。戦術的ではなく戦略的な変化であり、事件ではなく構造が変化しつつあるのだ。
さらに憂慮すべき構造の変化は、軍事境界線が単なる南北を分ける小分断ではなく、東アジアと世界を分ける大分断の線になりつつあるということだ。新冷戦が完成されるまでには時間がかかるだろうが、軍事分野では陣営対決が深まっている。北朝鮮は南方政策に期待するのをあきらめた。米大統領選挙後の交渉再開や、あるいは交渉力を高めるための「瀬戸際戦術」のような単語は、もはやふさわしくない。米国では改めて中国役割論が提起されているが、過去の北朝鮮の核問題の解決時期の米中協力を再現するのは難しい。中国とロシアの対北朝鮮政策の違いは明らかだが、その隙に分け入って朝鮮半島情勢を安定させるべき外交の空間は存在しない。外交が消えてしまったから軍事だけが残っている。それが現在の危機の構造的特徴だ。
北朝鮮は、軍事境界線を大分断の線にすることで生存するという戦略を取っているのだ。大分断が固定化してしまったら小分断は克服できない。西ドイツの政策は対東ドイツ政策ではなく、なぜ東方政策と呼ばれたのか、ということだ。余地はあまりないが、大分断を防ぐ北方外交を放棄してはならない。「民族協力」や「吸収統一」は、異なるように見えても民族主義的アプローチであるという点で共通している。今や、変化した秩序を反映する脱民族主義的アプローチが必要だ。統一の未来はどうだろうか。北朝鮮が未来へのかけ橋を絶ち切ったからといって、韓国まで同調する必要はない。来ないと分かっていながらゴドーを待つのは、理由があるからだ(サミュエル・ベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』)。待つことそのものが人生の存在理由であるように、統一の未来は分断国家の宿命的課題だ。どんなに遠くても未来への扉を閉ざす必要はない。

キム・ヨンチョル|元統一部長官、仁済大学教授 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
訳D.K

