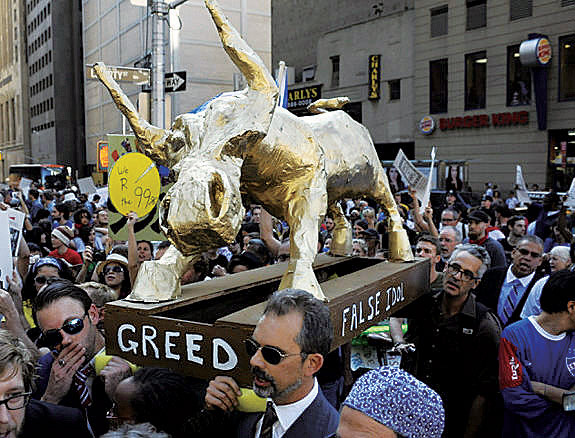
ジャネット・イエレン連邦準備制度理事会議長「富の不平等拡大傾向、強く憂慮」
上位5%世帯が富の全体の63%を獲得…下位50%は1%
「早期教育・高等教育・創業・遺産で分配政策を展開すべき」
ジャネット・イエレン米国連邦準備制度(連準・FRS)議長(58)が、米国の所得・富の不平等が最近100年で最も高い水準に近づき、19世紀以来最も長期にわたり拡大を続けていると警告した。
イエレン議長は17日(現地時間)、ボストン連邦準備銀行が開催した「経済機会と不平等」のカンファレンスでの演説を通じて、「米国の不平等のレベルと不平等の持続的拡大傾向を強く憂慮する」とし、このように明らかにした。米国の中央銀行である連準議長が景気状況や通貨政策ではなく不平等問題を公開的に論じるのは非常に異例なことだ。 これは過去の連準議長に比べて相対的に進歩的なイエレン議長の指向を示すものだが、米国の貧富格差が経済の健全性を害する程に深刻な水準に達したことを反映したものとも解釈される。
イエレン議長は、米国の貧富格差は2008年の金融危機時に上流層が富の相当部分を失い、低所得層に対する政府補助金支出が増えたことにより一時的に狭まったが、最近の景気回復で再び拡大していると診断した。 彼女は「現在の所得と富の不平等は、最近100年間で最も高い水準に近づいており、米国史上のほとんどの期間より高い」と指摘した。

イエレン議長は、大多数の家庭の全般的生活水準が高まり不平等が拡大することは大きな問題にならないが、今はほとんどの家庭の生活水準が停滞または低下している状況なので問題が大きいと指摘。 彼女は連準が6000世帯を対象に1989~2013年の家計収支を調査した結果、上位5%世帯の所得(インフレ調整後)は38%も増加したが、残りの95%世帯の増加幅は10%以下であり、上位層への所得集中度が高まったと明らかにした。
富の不平等はさらに深刻で、上位5%世帯が全体に占める富の比重が、1989年の54%から2013年には63%に増加した反面、下位50%世帯が占める富の比重は3%から1%に減少した。 彼女は「富と貧困の相続現象が深刻で、米国の階層移動性は他の先進国に比べて低い」として「このような状況が機会の均等という米国の伝統的価値と両立するのか問わなければならない」と話した。
イエレン議長は貧富格差の問題が政治的に敏感なイシューだという点を意識したためか、この日の演説では現象診断だけにとどめて具体的な解決法は提示しなかった。 彼女は「追加的な議論のための事実に基づく根拠を提供した」と話した。
ただし彼女は、階層上昇の機会に接近する重要な源泉として早期教育、高等教育、創業、遺産の4点を挙げて、この4点の分配も不均等だと指摘した。 政府がこの4点の源泉が各階層に等しく分配されるようにする政策を展開しなければならないと示唆したと見られる。 具体的には2008年の金融危機以後、早期教育のための公共投資が増えておらず、大学授業料の引き上げで高等教育にかかる費用は増えたと彼女は指摘した。
しかし、イエレン議長は連準の量的緩和・ゼロ金利政策が株式のような資産価格の上昇を煽ることによって、結果的に貧富格差の深化に一助となっているという批判に対しては言及しなかった。 『ニューヨーク タイムズ』は「イエレン議長が通貨緩和政策を通じて働き口創出を増やそうとする努力を越えて、中央銀行が経済不平等に関連した論争を刺激する研究の源泉になりうると見ている」と分析した。
訳J.S(1771字)

