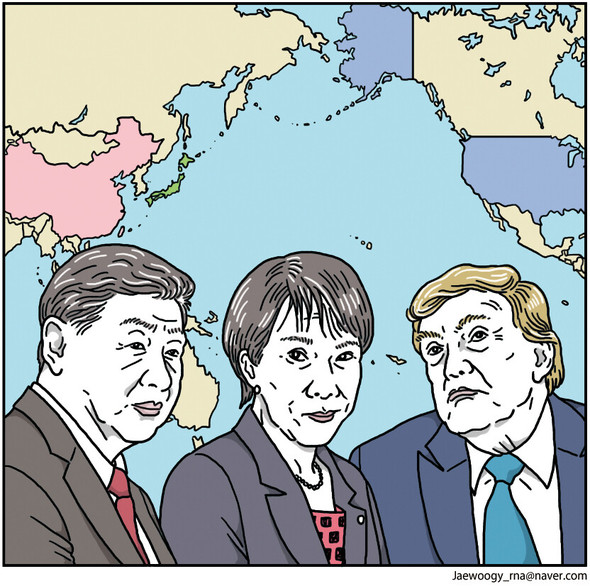[追悼:故・徐京植作家]文章を武器に闘った孤独な反植民地主義の闘士
絵と音楽に対する考えを拡張
国家主義、民族主義、母国語など
既成観念に対する新しい思惟の扉
社会的イシューへの関心と美学的品格を
同時に備えたエッセイスト
卑俗な時代、先生の不在に哀しみ

在日朝鮮人作家の徐京植(ソ・ギョンシク)先生が18日午後亡くなった。先生は今年5月、仁川ディアスポラ映画祭で講演し、9月にもソウルに2週間滞在した。腰・足の痛みのため杖をついて歩かねばならないほど不自由だったが良くなっていると言い、大勢で一緒に食事をしながら話をするのにも特に支障はなかった。新型コロナのパンデミックで数年往来が途絶えてからの再会をとても喜んだばかりなのに、思いもよらぬ訃報に韓国と日本の読者や知人たちは驚き、戸惑い、互いに連絡を取り合って哀悼した。
1990年代初め、本を通じて韓国に知られ始めた先生は、「日本より2、3倍」にもなると喜んだ韓国読者を対象に、活発な著述と講演などを通じて、「ディアスポラ」や「マイノリティ」、「境界人」など韓国社会に馴染みのなかった言葉を幅広い大衆的反応と共感とともに定着させた。そして「外部者」の独特な感受性で絵(美術)と音楽に対する考えと「他者に対する共感」、「他者の苦痛に対する想像力」を高次元に拡張し、国家主義と民族主義、日本、在日朝鮮人、本、家族、母語と母国語などに対する既成観念にショックを与え、新しい思惟の扉を開き、韓国の読書界と知識社会に大きな反響を呼んだ。一種の「カルチャーショック」だった。
「振り返ってみると、私が滞在した時代の韓国は金泳三(キム・ヨンサム)、金大中(キム・デジュン)、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権の文民政権時代、長い軍政を克服して、まだまだ問題だらけとは言いながら、希望や活力を感じさせる時代だった」。今年7月、18年間続けてきたハンギョレの連載の最後のコラムで、先生は「私の書いたものが人々に読まれ、受け入れられたのも、このような時代の空気のおかげであると自覚している」と書いた。
韓国社会のダイナミックな変化に大きな希望をかけていた先生は、その空気が再び変わってきている気配を早くからとらえ、不吉に感じていた。最近は「尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権の下で、韓国社会は逆回転に入ったようだ」として「すべてのものが浅薄になり、卑俗になっていくと感じる」と嘆いた。それと共に、勝算がほとんどないにもかかわらず、パレスチナでの正義実現のための実践的発言を続けたエドワード・サイードの言葉を思い起こし、「私たちも、勝算があろうとなかろうと『真実』を語り続けなければならない」と語った。
先生が早くから考察してきたルーマニア生まれのユダヤ系詩人、パウル・ツェランの「投壜通信」に例えた言葉が思い出される。「(書くこととは)離れ島に漂流した人が空き瓶に手紙を入れて海に流すような、または闇に向かって石を投げるような行為だ。誰かに届くのか、反響があるのかどうかも分からないまま、知らない読者に向かって語り続けるのだ」。考えてみれば、先生はその未知の友に向かって、届く確約もない手紙と石を最後の瞬間まで投げ続けた。
先生を知ったのは1992年、韓国語の翻訳本でベストセラーになった最初の本『私の西洋美術巡礼』(創批)を通じてだった。私が2005年に辞令を受けて入ったハンギョレの文化部で初めて任された仕事は、さまざまな本の話を盛り込んだタブロイド版のセクションを作ることだった。コラムもいくつか載せることにしたのだが、日本側の筆者としてまさにその『私の西洋美術巡礼』の著者が満場一致で選ばれた。奇しくも今年10月にハンギョレに掲載された先生の最後の文(「私の最初の本」)も『私の西洋美術巡礼』に関する話だった。
「ベルギーの古都ブリュージュの美術館で『カンビュセス王の裁き』に出会った時、『ああ、やっぱり…』という考えにとらわれた。その絵はまるで私を待っていたかのようだった。生きたまま皮膚を剥がされている犠牲者の姿に、数カ月前、深い失意の中で死んだ父親の姿を重ねて見たのだ。その3年前には病苦の末、母親が恨を抱いてこの世を去った」
その時が1983年。「祖国」で新しい出口を見つけたという家族の期待の中で、青い夢を抱いてソウル大学社会学科の修士課程(徐勝)と法学科(徐俊植)に通っていた2人の兄は、すでに10年以上にわたって投獄されていた。朴正煕(パク・チョンヒ)-金大中候補が激戦を繰り広げた1971年春、休暇を日本の実家で過ごし金浦空港に到着した彼らは、保安司令部に連行され「在日韓国人学院浸透スパイ団」ねつ造事件の犠牲者となった。この苦難は、翌年の維新憲法の公布で朴正煕の永久政権体制が稼動し、大統領を官制の間接選挙で選ぶことにした軍事独裁体制が、1987年6月の民主抗争で崩れるまで続いた。早稲田大学に進学した先生の人生は、兄たちを救うための活動と、息子たちを救うため60回も玄海灘を渡ったがついに釈放を見ることのできないまま生を終えた母親と家族の世話に方向が定まっていた。
文学評論家である淑明女子大学のクォン・ソンウ教授が書いた文(「徐京植を読み直す」)にこのような一節がある。「美しいエッセイは概して社会的イシューに無関心で、逆に社会的イシューに関心を傾ける鋭いエッセイは美学的に洗練されていない場合が多い。これに比べ、徐京植のエッセイは、政治的正しさと美学的品格を同時に備えている。尖鋭な政治的アジェンダを扱いながらも、深いペーソスと悲しみ、魅惑的な文体で満たされた徐京植の文章は、読者に格別の魅力を与えてくれる」

1995年に「日本エッセイスト・クラブ」賞を受賞した『子どもの涙』など30冊余りの著書の多くに美学的品格があらわれているが、『時代を渡る方法』(日本語題:『夜の時代に語るべきこと ソウル発 深夜通信』)などでも繰り返し描写される彼の幼少年期の悩みと傷、劣等感と自負、憧れと恐れ、不安、寂しさの交差は、読んでいる間じゅう深い悲しみを抱かせる。しかし不思議なことに、悲しみが力になる。その悲しみの源泉は、日本で「二等国民」とされ絶えず差別され抑圧されてきた在日朝鮮人の現実に対する透徹した正直な自己認識だ。
先生の政治的正しさと美学的品格の結合は、いまも作動している植民地支配構造と歪んだ政治の現実の深淵に対する正直で勇敢な凝視と深い思惟、節制され淡泊で流麗な表現、勝算の有る無しにかかわらず真実を語ろうとする「投壜通信」の勇気と意志があってこそ可能だったのだろう。これは植民地主義の心性に対抗し、時には激しい論戦を辞さない戦闘的な「論客」としての先生の一面とも矛盾しない。先生のこのような面について、私はこう書いたことがある。「彼は闘士だ。しかし、銃刀ではなく文章を武器に戦う孤独な反植民地主義の闘士だ」
逆回転しながらすべてのものが浅薄になり、卑俗になっている時代に、より大きく迫ってくる先生の不在に胸が痛み、悲しい。
訳C.M