хМщуОуЇяМхчЕщЈуууяМяМ+яМяМууЕуЄуЏуЋуухчЅуЇуу

ущхНуЇуЏцЏхЙДчД80фИфККушЖ ууфККу ухЎхЙДушПуучД85фИфККуцГхОфИуЎщЋщНЂш уЋуЊууфЛхО5хЙДуЎцЕууууууАу400фИфККушЖ ууфККхЃухЎхЙДуЎцЉуцИЁуууЈуЋуЊуу ууухЎхЙДущууфККууЁуЏуЉуЎуууЋцЎуууІуууЎу уууучууууЇуЏуЊууухЄууЎфККухЄЇхЄуЊцЅу ущуууІуууууЋшІууухшЛЂууЂущууууЋухЎхЙДхОуЋухДххИх ДуЋхОЉхИАууфККу уцАухууЊууЛуЉууухЎхЙДуЈхМщууЄуЊуцЉуЏхууухЎхЙДуууЊууЁхМщуЎхЇуОууЎцфЛЃуууЃуууфЛуЏщуучЇууЁуЎцфЛЃуЎхЎхЙДуЏщшЊчКчхЄБцЅуЇууучЕцДцчЕЖуЋщууЊууфИЛуЊхухЃуущшЗуухЙДщНЂуЏ40фЛЃхОхуЇууухМщццуЏ70фЛЃхуу ухЄЇщцАхНуЋфНухЙГхчуЊчЗцЇуОууЏхЅГцЇуЏхЎхЙДущуухОуууАууфЛфКууцухКууЊуу
ухЄууЎфККуфККчуЎцВчЗуЏщуЎхНЂуЎцОчЉчЗу уЈшууІууууЈууууууЎфЛЎхЎуЏщщуЃуІуууфККчуЎшЛшЗЁуЏууЎуууЊхНЂууЊууІууЊууууЎцВчЗуЋцВПуЃуІуууЈуууЊууЏхшЖГуЏчууІхОушЖГуЏщЗучЃуЎуууЋучМчНууучОНчЎуЋуЊууууууЊууххуЋчЈМуу ущуЇхОхуцЎуууІуууфККуЏущуЎуухАцАш уЋщууЊууцхО хЏПхНуЎхЛЖуГуууЈуЇшЕЗууІуучОшБЁу у
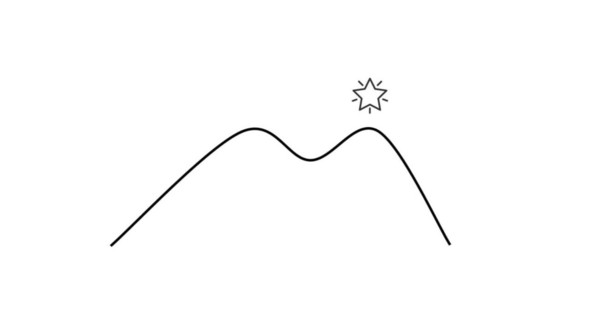
уууЎчЕЕууухЙГххЏПхН100цГцфЛЃуЎуцЌчЉуЎуфККчцВчЗу ухББуфИуЄуЇуЏуЊуфКуЄу ууууГууЉуЏууЇуЏуЊууууПуГууЉуЏууЋфММуІуууфККчуЎфИчЄухКчЙуЋцАууфИухухЇуОуухуГхББуЋчЛууЈууцхГуЊуЎууЃуІуууу уфИхЙДуЏхББуЎщ фИуЋхууЃуІшЕАуцуЇуЏуЊуу2хКІчЎуЎфККчуЋхууЊуууАуЊууЊуццу ухЙДщНЂучКуушІГчЙуЈшЇЃщухЄууЊуууАуЊууЊуу
уцхуЎхББуЎххуЏуцхуу учОчуЊчЋЖфКухуЁцууІуфНуЈуууЃуЈщЋуцуЋхууЃуІцБуцЕууЊуучЛуццу уцхуЎхЇПуЏуууущууушЊАууцхушПНуцБууу2уЄчЎуЎхББуЋуЏчЙуЋцБКуОуЃуххууЊуууууууцуухцууфЛуууАшЏуучцЖЏууууІхЖууухЄЂуЈууууу20фЛЃуЎ10хЙДщуЋцЕууцБуЇххщЈуЎт20хЙДучуу50фЛЃуЎ10хЙДщуЋцГЈуу уЈууЋуЎуМуЇхОхщЈуЎ20хЙДучуууЎу уууЎу10+20ууЎх ЌхМу2хчЙАушПууЎуучЇууЁуЎцфЛЃуЋхучцЖЏхЈцяМуЉуЄууЕуЄуЏуЋяМу уууЎх ЌхМуЋуууЈухОхщЈуЏххщЈуЎфЛщВуЇуЏуЊуууууууЎххЏОуЋшПууххщЈуЏхОхщЈуЎуууЎфКшЁчЗДчПуЈшІуЊууЎуцЃууцуцЙу уцЌхНуЋцухЄЂуЈхИцуЏхОхщЈуЋхЎчОуухЏшНцЇущЋуууу у
уфИхЙДцуЋх ЅуЃуфККу уЎхЄЇхЄцАухЎхЙДфЛЅхОуЎфККчухПщ уууцЃчЂКуЋшЈууЈуфККчуЎхОхщЈууЉуЎуууЋчууІууууЋуЄууІцЉуПухАНууЊуу30хЙДушЖ уущЗуцщуЎхЗучЁфКуЋцИЁууууЋуЏухуухП шІу уууууЇууІууЊууЈцууІууууу ушхОуЎцКхуЈуушЈшушууЈуфККу уЏцЁфЛЖххАуЎуууЋущуЎууЈух уЋцуцЕЎууЙуууууууЎфККчуЋууууушВЌфЛЛушВ уучуцЎуухГуЃуІуууЊуууАуЊууЊуууЎфИуЎфИуфЙухууууЋуЏуущухП шІу ушхЙДуЎшВЇхАуЏчНууЇууууЊууАуущууххуууАушЏуфККчяМgood lifeяМущуууу уууууууууууЊууууууЇуЏуЊууууууЊууущуЏхП шІцЁфЛЖуЋщуууххцЁфЛЖуЇуЏуЊууущу ууЇуЏххуЇуЏуЊуушЏуфККчущууууЋуЏущфЛЅхЄуЋуцКхууЊуууАуЊууЊушІчД ууууЋууушЏуфККчуЈуЏфНу уууу цЇу уЊхЎчОЉуЈшЇЃщуххЈуууцГЈчЎууЙууЊуЎуЏушЏуфККчууЎууЎуЇуЏуЊуушЏуфККчущууууЎуцЁфЛЖуу у
ух шМЉууЁуЎфККчуцшЈуЋуууЊуушЏуфККчущууууЎцЁфЛЖуЏхЄЇуухууІ4уЄуЋчЕуууухЅхКЗуущущуГяМшЖЃхГяМущЂфПу ухЅхКЗуЇууучЈхКІуЎущуцуЃуІууушЊху ууЎшЖЃхГуцуЃуІушПуфККу уЈшЏуфККщщЂфПучЖцууІуууЊуууАуЊууЊуучцЖЏуЎхОхуцЏууяМуЄуЎцБу уцБухЛКчЉуЎщууцЏуууууЋуууууууЃуІууфККчуЎщууЋшууууЈууЇууухЙДухууЈхЄБуууЎууууухОуууЎууууц чБуЈшІцАуЏшууІуууучЕщЈуЈхЙДшМЊуЋуЏхуПухКуучЎуЏууууЇууфИуЎфИушІушІщуЏцЗБуОуууЉууцЃЎуЇуЉууцВМуЊуЎуушІхуучЅцЕучуОууцщуЎхЏхКІущЋууцЙцГуфМхОуууфККчущЗучууфККу уушКЋуЋуЄуууучЙхЅуЊшНху уууЎхухОхуЎфККчуЎцЏууЋуЊуЃуІуууу
учЇуЏхчЉЋуЎхЃчЏу уухцуЋчЈЎуОууЎццуЇуууухЏухЌушуучПхЙДуЎцЅуЋхЎучЕуЖцЄчЉуЎчЈЎуЏчЇуЋуОуухуЃухАщЂуЇхЌучуцуущшуЎцЙууЏуууЋчууІууууууЎу уфККчуЏфИуЄуЇуЏуЊууфКуЄуЎхЁуЇууууЈуууЎшууЎщууфККчуЎшЊшЗЏучАуЊуцЙхуИуЈхАуущфИуЇщуЋшПЗуЃуІуучЉКуЋшМуууЊууЎуцууЋцВПуЃуІшЁууАучЁфКуЋчЎчхАуЋууЉучууу ууу
шЈГH.J