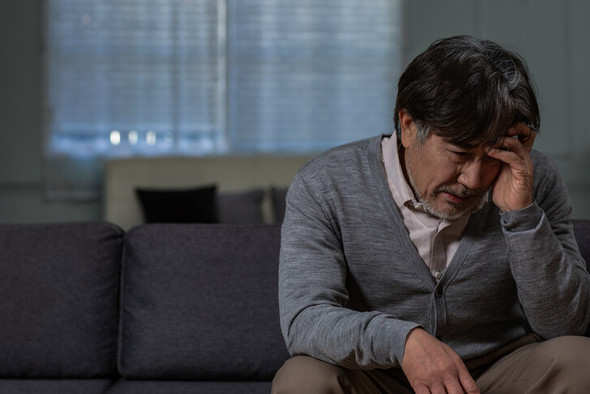
脳腫瘍は脳だけでなく、脳神経、脳膜、血管、頭皮など多様な部位で発生する可能性がある。最近、保健医療ビッグデータによると、国内の脳腫瘍患者は着実に増加する傾向を示している。2020年には良性脳腫瘍患者が4万7,675人だったが、2022年には5万5,382人に増えた。悪性脳腫瘍患者も同じ期間に1万1,603人から1万2,140人に増加し、悪性脳腫瘍の一つである膠芽腫は毎年約1,000人が新たに診断されている。
脳腫瘍は大きく良性と悪性に分けられるが、良性脳腫瘍は成長速度が遅く、脳以外で発生する場合が多く、比較的治療が容易な方だ。良性脳腫瘍には代表的に脳髄膜腫、脳下垂体腫瘍、聴神経鞘腫が含まれ、積極的な治療を受けた場合、脳髄膜腫の5年生存率は95%、脳下垂体腺腫の5年生存率は97%、神経鞘腫の5年生存率は94%だ。
一方、悪性脳腫瘍は急速に成長し、周辺組織を入り込み正常な脳機能を損傷させる危険性が高い。特に、他の臓器で発生したがんが脳に転移した転移性脳腫瘍は治療がさらに難しい方だ。悪性脳腫瘍の中でも神経膠腫は全体的に5年生存率が38%であり、その中でも最も悪性度が高い膠芽腫は5年生存率が7%で非常に低い。一方、悪性度によって生存率が異なり、退形成性星細胞腫は5年生存率が24%であり、低悪性度星細胞腫の場合、5年生存率が61%で比較的高い方だ。
2023年に発表された中央がん登録本部の資料によると、2017年から2021年までの5年間に診断された脳および中枢神経系がん患者の5年間の相対生存率は39.7%であり、性別によって男性は37.4%、女性は42.7%だった。このような数値は、脳腫瘍のタイプと悪性の有無、治療方法によって生存率が変わることを意味する。
脳腫瘍が発生した場合、代表的な症状の一つは頭痛だ。一般的な緊張性頭痛は午後に首の後ろが凝る症状が現れるが、脳腫瘍による頭痛は明け方にさらにひどくなる特徴がある。これは長時間横になっている時に呼吸量が減り、血液が脳血管に集中して脳圧が高くなるためだ。高麗大学安山病院脳腫瘍センター神経外科のキム・サンデ教授は、開け方に繰り返し頭痛がひどくなり、麻痺、視力低下、嘔吐などの症状が一緒に現れた場合は、脳腫瘍を疑ってみる必要があり、このような症状が続いた場合、早期に診療を受けることが重要だと強調した。
脳腫瘍の治療は腫瘍の大きさと位置、症状によって治療方法が変わる。小さな良性腫瘍の場合、放射線治療だけでも十分に治療でき、腫瘍が大きかったり悪性の場合は、手術が必要になることもある。悪性脳腫瘍の場合、手術を受けた後も放射線治療や抗がん治療を並行しなければならないケースが多い。最近は内視鏡を利用した手術が活発に行われているが、従来の開頭手術の代わりに、鼻や目の周辺を通じて内視鏡を挿入して腫瘍を除去する方式だ。この方法は、傷跡がほとんど残らず、早期回復が可能であるため、患者の満足度が高い。特に目の周りに発生した脳腫瘍は、経眼窩内視鏡手術を行った場合、より精密に除去できるうえ、神経と血管を保護しながら出血と合併症の危険を減らせるメリットがある。さらに、切開部位が最小化されるため、手術後の痛みが少なく、回復も早く進む。
脳腫瘍の治療において重要な要素の一つは、複数の診療科が協力して最適な治療方法を提供する学際的診療システムである。神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、内分泌内科など、様々な専門医が連携して手術の有無、放射線治療、抗がん治療などを総合的に考えるオーダーメード型の治療が可能になる。キム・サンデ教授は、脳腫瘍の治療では患者個人に合わせたアプローチと最新の医療技術が結合することが重要であり、腫瘍の位置と大きさ、患者の健康状態を考慮して最適の治療法を適用することが治療成果を高める核心要素だと説明した。
脳腫瘍はもはや治療が不可能な疾患ではない。積極的な治療を受ければ、良性脳腫瘍の場合、90%以上の高い生存率を示し、悪性脳腫瘍も手術と放射線治療、抗がん治療を並行することで生存率を高めることができる。また、学際的協診を通じたオーダーメード型治療が患者の生存率を最大化するのに、重要な役割を果たすため、頭痛、視力低下、麻痺症状などの異常シグナルが現れた場合、早期に病院を訪れ、正確な診断を受ける必要がある。
訳H.J

