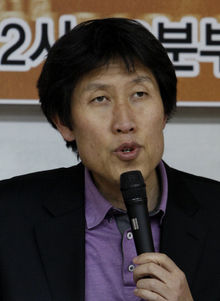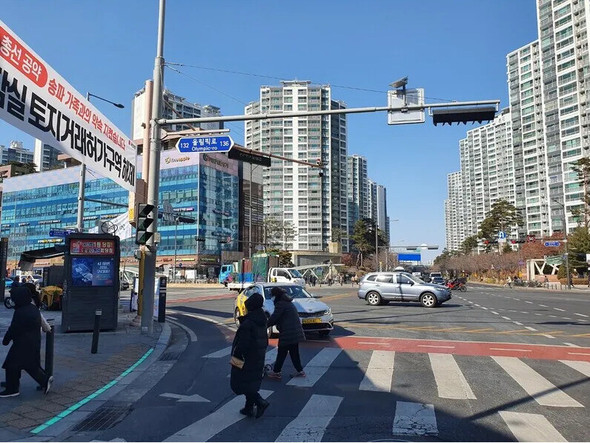原文入力:2011/10/25 20:45(2001字)
チェ・ウォンヒョン記者
‘批判社会学大会’金東椿(キム・ドンチュン)教授発表
反対勢力を‘敵’と見なし
検察・一部言論を動員し鎮圧
"開発独裁方式 新自由主義"
←2008年2月18日、盧武鉉前大統領と当時当選者身分だった李明博大統領が大統領府内の大統領官邸で会い国政懸案について意見を交わしている。 李明博政府は執権初期‘合理的保守’のイメージを掲げたが、ろうそく集会を契機に反対勢力、特に前政権の人々と民主化運動勢力を‘敵’と見なし鎮圧する方式の‘戦争政治’を繰り広げたとキム・ドンチュン教授は分析した。 大統領府カメラマン団
李明博政府は初めは主に経済自由化に忠実な新自由主義政権だと評価されていた。 しかし独断的な国政運営と民間人査察、過度な介入主義的経済政策などでその性格について各種の論難が起きた。 すなわち民主主義の手続きで執権したが、事実上30年前の権威主義政権と変わりない独裁政権であるとかファシズム政権だという評価まで出てきた。
こういう診断に加えてキム・ドンチュン(写真)聖公会大教授は21日に開かれた第14回批判社会学大会でMB政府の性格を‘戦争政治’という概念で説明し関心を集めた。彼は‘李明博政権の支配方式’というタイトルの発表を通じて李明博政府の政策基調の根底には「支配集団の危機意識と既得権喪失の不安感の中で主に現れる‘戦争政治’、すなわち民主主義の下での‘制度的クーデター’」が位置していると解説した。戦争政治とは国家が戦争状況にあるという前提の下で国家の維持、すなわち内外の敵から国家を保護することを最も一次的な目標にして、国内政治を戦争を遂行するように運営することを言う。すなわち反対勢力を‘左派’や‘敵’と見なした後、手段と方法を選ばずに鎮圧する方式の国政運営を一貫して継続してきたという指摘だ。
←キム・ドンチュン聖公会(ソンゴンフェ)大教授
キム教授は李明博政権がこの間 民主化成果を認定しながらも盧武鉉政府が一部抑制してきた新自由主義政策を民主的で漸進的な方式で遂行する可能性もあると見られたが、以後米国との牛肉交渉件に触発されたろうそく集会を政権存立の問題として受けとめ、それに伴い支配勢力の利害を強固にするため強迫的に戦争政治に乗り出すことになったと明らかにした。国家情報院、国軍機務司令部、検察・警察公安部署など‘影の政府’の地位が再び強化され、民主化運動勢力を清算しようとする試みはこういう戦争政治の支配方式が表面化した端的な事例と見る。
事実上の戦争政治は民主政府10年を除き韓国の歴代政府が例外なく遂行してきた支配方式といえる。しかし‘民主化’後に登場した李明博政府は過去の権威主義政府とは異なる方法を取っているとキム教授は指摘する。特に目立つのは検察とマスコミの役割だ。‘味方’には手抜き捜査をするが、反対勢力を捕らえるためには無理な起訴もはばからない検察、政府事業に対し広報性記事を吐き出す言論を「抑圧と正当化の二本柱として活用している」ということだ。
キム教授は「この政府を新自由主義政権とか権威主義政権などとして把握することは適切でない」として「この政府は何の価値や方向、理念にも後押しされない経済第一主義、市場主義の虚構性、そして韓国保守主義の退行的性格を最も露骨に現した」と批判した。
こういう戦争政治が一貫した計画や指揮の下に進行されたと見ることも難しく、むしろ支配勢力が去る10年間に若干喪失した利益を得るために手段と方法、体面と廉恥をかなぐり捨てたと見る方がより適切だと説明した。
こういう李明博政府の性格を韓国社会の全体の流れの中で把握するならば? キム教授は基本的に韓国は‘資本主義的民主主義国家’としての性格を継続維持してきており、1987年の民主化でもその支配勢力は大きく変わらなかったと指摘する。ところで1997年外国為替危機後に韓国資本主義の新自由主義的再編が起き、政治的民主主義と経済的自由主義の間に深刻な衝突が発生し、支配勢力と執権勢力(民主政府)の間の葛藤が露骨になったということだ。
こういう状況の中で‘反共主義・開発独裁勢力の再執権’という性格を帯びた李明博政府は、民主政府以前のように支配勢力と執権勢力を再び一致させることができる条件を作り、それに伴い経済的新自由主義の推進と政治的民主主義の逆進という流れを結合できたという。 端的に言えば、「開発独裁の方式で新自由主義を推進する」性格を持つという解説だ。
チェ・ウォンヒョン記者 circle@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/culture/religion/502415.html 訳J.S