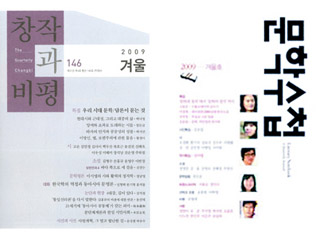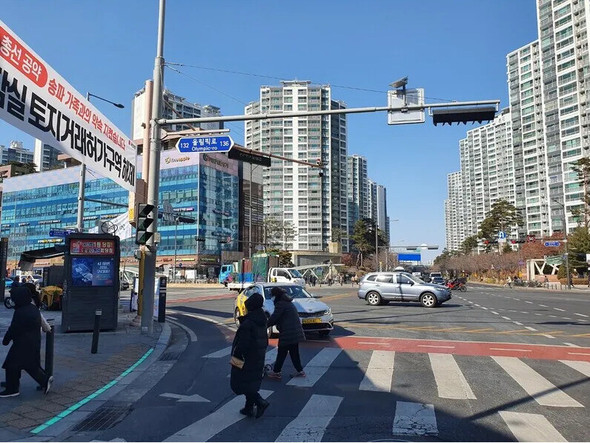原文入力:2009-11-19午後07:44:24
文人たち 龍山惨事1人示威…“今や法とも戦うべき”
189人 ‘作家宣言’ に続き文学の政治性論議 ‘ごうごう’
チェ・ジェボン記者
←若い文人189人が去る6月9日、ソウル,貞洞のフランチスコ教育会館で‘これは人の話-6・9作家宣言’を発表している。 <ハンギョレ>資料写真
“韓国文学の内部に尋常でない風が吹き始めたのではないか。自然と一体化した叙情の宇宙を謳歌した叙情詩人が、社会の分裂に悩み始め、事物と言語の間の不条理探求に没頭してきたモダニストが政治体の中での言語のイデオロギーを問い質し始め、批評は文学と政治という古ぼけた、だが忘れられた主題に帰還し始めた。”
評論家ハム・ドンギュン氏が<創作と批評>冬号に寄稿した‘余剰と超過で到来する詩たち’という文の一節だ。彼の話のとおり、今韓国文学は文学の政治性をめぐる悩みと討論で静かに煮え立っている。 民主主義が後退し民衆の生存権が脅威を受け、民族和解にひびが入るなど社会のほとんど全部門に現れる退行と堕落の兆しの前に、文学人だからとゆったりとしている傍観者の席に留まることはできない。去る6月9日ジャンルと傾向をあまねく網羅した若い文人189人が集まり‘これは人の話-6・9作家宣言’を発表したことは象徴的だった。文学の政治性に対する悩みがこれ以上、特定団体や少数の‘参加的’文人らだけのことではないまでに状況が急に悪化したことをそれは見せてくれた。
6・9宣言発表と龍山惨事現場でのリレー1人示威という現実の中の実践は、それに似合った作品の生産,そして文学と政治の相関性を巡る批評的・理論的議論につながった。ジャック・ランシエールとシャンタル ムフのような外国の理論家たちがその過程でしばしば議論された。新しく出てきた<創作と批評>冬号の特集‘私たちの時代文学/談論が尋ねること’と<文学手帳>冬号特集‘‘文学と政治’から‘文学の政治’まで は、そのような実践と議論の中間点検に該当するわけだ。
文学,‘退行する現実’に再び目を開く
“朝刊は訃報のようだ/人が度々死ぬ//(…)//計画的に/即興的に/合法的に/人が死んでいく//戦闘的に/錯乱的に/窮極的に,人が死んでいく//決死的に/総体的に/死んだはずのことたちが,死んでいない//死せる者は相変らず失踪中で/篭城中で/投身中だ//幽霊が漂う玄関ら,/朝刊は訃報のようだ”
<創作と批評>に載せられたハム・ドンギュン氏の文はイ・ヨングァンの詩<幽霊3>を通じ論議を継続する。それによれば「‘訃報’になった朝刊は、暮らしの共同体がいつのまにか巨大な墓になってしまった私たちの時代の総体的な‘表紙’」であり「生ける者たちの政治共同体から訴えられ暴行され死に追いやられ哀悼を受けることが出来ない、それにもかかわらず死なない者たちは彼らと接続した詩的無意識を通じて死せる者たちの法廷,詩の法廷に原告の席に回帰する。」 <文学手帳>特集に載せた‘収容所における文を書くこと’で評論家コ・ポンジュン氏が「‘法’という手段を通じて国家の暴力は合法化される」と書いたこと、そして時事週刊誌<ハンギョレ21>最近号で批評家シン・ヒョンチョル氏が龍山惨事関連裁判結果について「今や文学は法とも戦わなければならない」と明らかにしたこともやはり、ハム氏の話と同じ脈絡の発言であろう。
<創作と批評>特集に寄稿した‘現代時と近代性,そして大衆の人生’で、元老批評家ペク・ナクチョン氏はチン・ウンギョン,カン・ケスク,イ・ジャンウク氏など、若い評論家の最近の論議を検討し、文学の政治性に関する論議が美学的自律性を強調するところから一歩進んで大衆の人生と疎通する‘大乗’の道を模索することを助言した。ぺク・ジヨン氏は<創作と批評>特集でコン・ソンオク,チョン・ソンテの小説に登場する他者的経験と越境の叙事を分析し、イ・ギョンジェ氏は<文学手帳>特集でチョン・ドサン,カン・ヨンスクの小説とネイションの関係を問い質した。
チェ・ジェボン文学専門記者bong@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/388648.html 訳J.S