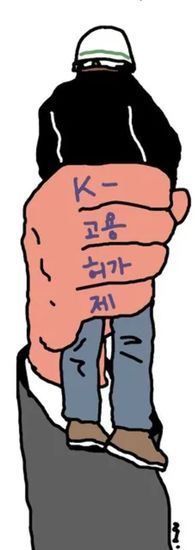原文入力:2009-09-10午後07:10:11
日本学 大衆学術誌‘日本批評’創刊
創刊号特集で 米・日関係 再照明
被爆後‘親米国家’誕生 深層 探索
イ・セヨン記者
←<日本批評>
‘大衆との疎通’を標ぼうする日本学大衆学術誌が登場した。ソウル大学日本研究所が図書出版グリーンビとともに出す半年刊<日本批評>だ。「日本に関する研究は活発だが、その成果を大衆化しようとする努力が足りず、日本に対する韓国人の理解が‘盲目的な敵対や憧憬’あるいは‘扇情的なゴシップ’水準に留まってきた」というのが研究所が明らかにした‘創刊の弁’だ。
編集長ユン・サンイン漢陽大教授は「日本は21世紀韓国人が思考の幅を拡張できる訓練の場」として「日本社会と文化に対する研究は隣接学問にも応用可能なことであり、究極的には韓国人の人生と現実を深く広く覗き見ることができる思惟に拡張されるべきだ」と強調した。
<日本批評>の紙面は企画特集と研究論壇,書評,講演録などから構成されるが、特に注目されるのは企画特集と書評だ。これらの構成は日本の国家と社会,文化に対する韓国人の顕在的関心を充足させる内容で満たされるというのが編集陣の説明だ。
創刊号の特集主題は‘現代日本社会の形成と米国’だ。1853年の開港から1945年敗戦にともなう民主主義国家への転換に至るまで、近代日本の経路を決定した2度の体制交替が共に米国の立会いの下になされたという事実に注目し、米国というプリズムを通し今日の日本の国家原理と日本人の精神的深層を探索した。クォン・ヒョクテ聖公会大教授が漫画家中沢啓治の作品を分析し、どのようにして日本人たちが原爆加害責任に対する追及を放棄し‘親米国家’日本を誕生させ豊かさと平和を享受することになったかを究明する一方で、パク・ジンウ淑明女子大教授は米軍政の積極的な介入により存続することとなった天皇制が戦後日本の歴史認識と対外関係にどのような悪影響を及ぼしたかを分析する。チョ・ガンジャ日本中部大教授は吉見俊哉の<親米と反米>に対する書評を通じ‘反米=進歩’‘親米=保守’という構図がなぜ日本では妥当でないのかを示し、日本と東アジアで米国が持つ意味の重層性を明らかにする。
<日本批評>編集委員にはパク・ジンウ(淑明女子大)・パク・キュテ(漢陽大)・チャン・インソン(ソウル大)・チョン・ジンソン(放送大)教授など国内の中堅日本学者7人が、編集諮問委員にはキム・ユンシク ソウル大名誉教授と酒井直樹米国コーネル大教授など両国の元老学者らが参加している。 イ・セヨン記者
原文: https://www.hani.co.kr/arti/culture/religion/376041.html 訳J.S