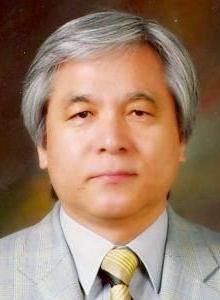原文入力:2009-03-23午後08:31:47
ユン・ジンホ仁荷大経済学部教授
去る1月、日本,厚生労働省のある高位官僚が、勤労者派遣法の緩和を防ぐことができなかったことに対して公開謝罪したことによって、日本社会に穏やかな波紋を起こした。日本,厚生労働省広島労働局の落合淳一局長は、2003年勤労者派遣法が改定され製造業にも勤労者派遣が可能になったことに対して「私は本来問題がある制度と考えていたが、当時市場原理主義が全面的に現れた時期だったためにこれを防ぐことができなかった。労働行政を担当していた誰かが辞職をしても(法改定を)防げなかったことに対して謝りたい」と話した。彼は引き続き「派遣勤労者も同じ職場の同僚として認識しなければならない。雇用契約を中途解除してはいけない。(派遣勤労契約を中途解除しないように)声を高め指導したい」と明らかにした。
勤労者派遣法改定当時、厚生労働省の賃金時間課長を受け持っていた落合局長のこういう公開謝罪はまもなく去る10年間にかけて進行されてきた日本の市場原理主義的労働政策に対する自己反省の表現といえる。事実、日本は1990年代中盤から構造改革の名の下に民営化・規制緩和など新自由主義的政策を導入した。特に2001年小泉政権がスタートし市場原理主義政策の導入が本格的になり、その一環で労働基準法・労働者派遣法の改正など労働市場に対する規制緩和措置が相次いで導入された。
しかし規制緩和の結果は労働市場の秩序崩壊として現れた。非正規職規制緩和で非正規職の数が急速に増え、労働市場の両極化が深刻化された。社会的にも貧困・家庭崩壊・ホームレス・離婚・病気・自殺・犯罪の増加など各種社会的問題が頻発した。特に昨年6月東京都内の秋葉原路上である青年派遣勤労者が通りがかりの通行人らに刃物をむやみに振り回し17人を殺傷した‘秋葉原通り魔殺人事件’は日本社会全体を驚愕させた。この事件の背景には多様な原因があったが、その中でも非正規職を転々として積もり積もった未来に対する絶望と社会に対する不満が重要な要因として作用した。この事件を契機に世論は非正規職に対する規制を再び強化しなければならないという側に集められ、日本の政府与党もこのような世論の圧力に逆らうことができず日雇い派遣労働の禁止など労働市場に対する‘再規制’法案を準備中だ。落合局長の発言はこういう背景から出たものといえる。
日本のこのような経験は韓国にも多くの示唆点を投げかける。政府与党は現在、非正規職勤労者の最大雇用契約期間を2年から4年に延長する内容の非正規職法改正案(実は改悪案)を準備中だ。労働部は来る7月に雇用期間が満了する非正規職の失業が100万人に肉迫するといういわゆる‘非正規職100万失業大乱説’を非正規職法改正の根拠に上げているが、色々な研究者の研究結果によれば、このような労働部の主張は誇張という事実が明らかになった。事情がこうであるにも関わらず政府与党は反対世論に対して目と耳を防いだまま非正規職法改悪案をゴリ押ししている。政府与党の非正規職法改悪の動きの本当の目標は、賃金が安く解雇がやさしい非正規職勤労者を企業が思いのままに使えるようにしてあげようということにあることを察するようにする処置だ。このように非正規職に対する規制が緩和される場合、私たちの社会にいかなる衝撃を与えることになるかは日本の事例でもよく知ることが出来る。労働市場の秩序が崩れ、各種社会問題が頻発することになれば、何年後かには韓国でも高位官僚が「当時職位を賭してでも非正規職法改悪を防ぐことができなかったことに対して謝る」という記者会見をすることになる日がくるかも知れない。
ユン・ジンホ仁荷大経済学部教授