[本] 良い音楽に心を動かされたとき、その感銘の由来を掘り下げてみたくなる
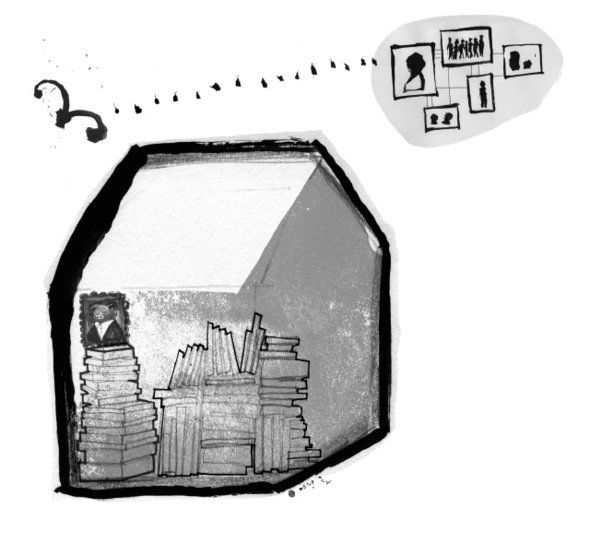
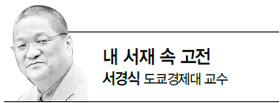
今回から「私の書斎」というタイトルで、数人の筆者が交替でコラムを執筆することになった。どんなことでもいいから本に関することを書くように、というのが担当者からの唯一の注文である。私がその一番手だ。
「私の書斎」だって? このタイトルを聞かされたとき、日本語と朝鮮語の語感の違いだろうか、それとも現代日本と韓国の生活感覚の違いだろうか、どことなく居心地の悪い思いがした。そのことから書き始めてみよう。
私は「書斎」という言葉はあまりつかわない。どうしてもという場合でも、せいぜい「勉強部屋」という言葉で代えている。「書斎が狭くてね、本が溢れちゃって困っているんだよ」などと口にする人物に出遭ったら、かつての私は反感を覚えたものだった。だが、いま、自分が無意識に同じようなことを口にしていることに気づいてハッとする。それは「書斎」という言葉自体に、羞恥に近い感情がまとわりついているからだ。
この感情の中身は二面的だ。まず、それは「ブルジョア的」ということである。日本の住宅事情では自宅に書斎を確保できるのはかなり限られた階層であろう。つまり、その人物は実は自分は書斎をもつほど豊かだと自慢したいのではないか。いや、それが相手にとってイヤ味な自慢話に聞こえるとは想像もできないほど、自分の豊かさに無自覚なのではないか。そういう反感である。

私は子どもの頃から、映画などでみる英国風の書斎への強いあこがれを抱いていた。高い天井までしつらえられたガラス戸つきの書棚にギッシリと詰まった革表紙の書籍。広く重厚な机。すわり心地の良さそうな椅子。低く流れるバロック音楽…。しかし、現実の私が本をよく読んだ場所は、寝床だった。枕元に乱雑に本を積み上げ、寝ころんだまま次々に読み飛ばしていくのである。それはそれで気楽で良かったのだが、そんな習慣がとうとう抜けないまま年をとってしまい、いまは書斎があるのに、これという本に出遭うと机に向かわず寝床に向かう。その上、悪いことに、若い頃と違ってすぐに睡魔に襲われて2,3ページも読まないままに眠ってしまう。つまり、私はもう本が読めなくなったのだ。
第二の感情は、書斎の話を不必要に口にする人がまるで、「自分はそれほどの読書家だ」とほのめかしているような気がすることだ。これは、私のヒガミである。私は思春期の頃から、友人が最近読んだ難しそうな本の話を出すたびに自分の不勉強を思い知らされ、そのくせ素直に勉強する気持ちになれないで、なんとか背伸びして対抗しようとした。そんなイヤな性格も治らないまま年をとってしまった。いまから治ることも、ないだろう。
物書き兼大学教授という職業にたずさわっていると、世の中には恐ろしいほどの読書家たちがいるものだと思い知らされることがある。そういう人たちの多くは(少なくとも私が日本で会う人たちは)書斎の話など出さない。本を読むのはこの人たちの仕事であって、当たり前のことだからだ。これも私の偏見だけれど、「書斎が狭くてね」などと口にする人は、本にではなく書斎に関心があるのであり、実はあまり本を読まないのだろう。だから私は、書斎の話などすると、自分の不勉強が見透かされるようで恥ずかしいのである。
さて、そんな私でも大学で教えるようになってから必要に迫られ、いつの間にか書庫兼勉強部屋を三か所もつようになった。ひとつは大学の研究室。そこには主に授業の参考にする人権問題、歴史問題などの文献が置いてある。もう一つは信州(長野県)の小さな山荘の一部屋で、ここには文学、芸術関係の文献を運び込んだ。いつかたっぷりと時間があるときに、なにものにも煩わされずゆっくりと読もうというありふれた欲望のためだ。しかし、ほんとうにそんな時が来るかどうか、あまり期待はしていない。三つ目は東京の自宅アパートの一室である。ここには、体系のないまま乱雑に本が放り込んである。この三か所のどこかで読書したり執筆したりするのだが、整理整頓が下手なので、研究室で執筆している時に必要な本は自宅にあり、山荘で本が読みたくなった時にその本は研究室にあるという具合で、本を探している時間ばかりがやたらに長く、無駄なこと甚だしい。
大学の同僚たちは定年退職の時期が迫ってくると、研究室の蔵書の処分に苦慮し始める。自宅に持ち帰るほど余裕のある書斎をもつ人は多くないからだ。さりとて、むかしと違って図書館などに寄贈しようとしても引き取ってくれない。古本屋に売ろうにも値段が付くどころか、むしろこちらから自費で運んで処分を頼まなければならない。学生にタダで上げると言っても迷惑顔される。学生としても狭い部屋で暮らしているのだから無理はないのだ。いきおい、本を捨てるということになる。半世紀前の学生反乱の時代、日本の寺山修司(てらやま・しゅうじ)という詩人の「書を捨てよ、街に出でよ」という詩句が流行語になったが、それは頭デッカチな知的世界にばかり閉じこもっているのではなく社会的な行動に起ち上がれという意味であって、実際に本を捨てろという意味ではなかった。「本を捨てる」…私の世代には馴染むことのできない発想だ。だが、何年先かはともかく、私にも着実にその時が近づいている。その時に、いま三か所に分散している本をすべて一か所に集めて、それでも余裕のある広大な書斎があったらいいのに……そんなことを思わないこともないが、もはや読むこともできない本のためにそんなことをするなど、まさしく「ブルジョア的」な恥ずべき所業だろう。それに、私のような中途半端に「ブルジョア的」な者には、そもそも財力が足りない。
そんな私が、それでも「私の書斎」というタイトルのコラムを執筆することになった。恥ずかしい気もちを抑えて引き受けたのは、現在の私は事実として書斎に相当する部屋をもっているし、不勉強ではあるけれど自分なりの読み方で読んだ本を他人に進めてみたい欲心もなくなっていないからだ。ただ、「書斎」という言葉を口にするときに自分に生じる戸惑いの感情だけは否定したくないので、こんなことを書いているうちに肝腎の本のことを書く紙面が少なくなってしまった。
今回は最近、私がもっとも楽しんで読んだ本を挙げておこう。エドワード・サイードの『サイード音楽評論1・2』(みすず書房、Edward W. Said, Music At The Limints, Columbia University Press,2008)である。
良い音楽を聴いて心を動かされたとき、誰かと対話して感銘の由来を掘り下げてみたくなる。だが、良い対話相手を見つけることは良い音楽を聴く以上に至難だ。それは、本書でサイード自身が述べているように、音楽という芸術が「最も無言のもの」であり、「最も閉ざされた」「最も論じにくい分野」だからだ。さらに、その対話の相手は豊かな感性と自由な精神をもつだけでなく、音楽理論に通暁し、音楽を文学や政治など他の分野と関連づけて読解できなければならない。サイードこそ、そんな人物だった。この本は寝床で読んでも眠くならなかった。毎晩すこしずつ、彼との対話を愉しみ、興が乗れば頁を閉じて彼が推奨する音盤に耳を傾けたりもした。
「右手が左手に呼応するように、一本の指はほかの九本に呼応していて、全体はその奥にある一つの魂に応えている」というグレン・グールドのピアノ演奏の描写。「モーツアルトは(オペラの)登場人物の心情や意志がもたらす合意とは無関係に、人々を翻弄する、ある抽象的な力を具現することを試みたのだと私は思う。道徳的におよそ不毛な台本を使ったことはその証左である」という指摘。ピアニストならグールドのほか、ポリーニ、ブレンデル、シフ。指揮者ならフルトヴェングラー、チェリビダッケ、アバド…これら天才たちに関する記述に、わが意を得たと膝を打ち、あるいは新たな発見に導かれる。
サイードは『オリエンタリズム』『文化と帝国主義』の著者として文化研究の分野で全世界に巨大な影響を与えただけでなく、パレスチナ解放と平和のための活動家兼理論家としてもきわめて重要な足跡を残し、米英軍によるイラク進攻の年である2003年、長く暮らしたニューヨークで世を去った。本書は、彼が1982年のグールドの死を契機に書き始め、自らの死の寸前まで20年間にわたって書き続けた音楽評論をまとめたものである。恐ろしいほど多忙であったに違いなく、しかも白血病という難病まで抱えていたサイードが、これほど勤勉に演奏会に足を運び、これほど心からの楽しみをもって(それも妥協のない知的楽しみである)音楽に接していたことは、驚くほかない。
パレスチナ・アラブ人、キリスト教徒、アメリカ合衆国国民であった彼は、専門的な高等教育を受けたピアニストでもあった。アメリカ有名大学の教授として裕福で満ち足りた人生を送ることも可能だっただろうに、サイードはつねに、不公正に苦しみ全世界から無視され続けているパレスチナ民衆の側に心を寄せて闘った。彼にとってパレスチナ解放闘争とクラシック音楽の楽しみは別々のことではなかった。他の分野と同じように音楽批評においても、つねに自己の複合的なアイデンティティに基礎を置く《内部の他者》の視点から、《中心部》の独善をあざやかに批判している。
家(Home)をもたないという信条のため、サイードは終生、不動産を所有せず賃貸住宅に暮らした。もちろん、仕事場としての書斎はもっていたに違いないけれど。サイードについて書きたいことは多い。おそらくこの欄で再びとりあげることになるだろう。■
徐京植 東京経済大学教授
(4157字)