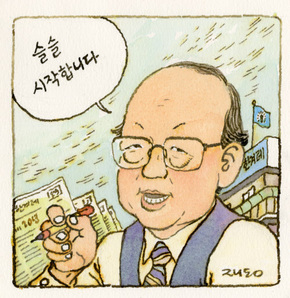2008年5月14日
任在慶(イム・ジェギョン)/言論人
絵 朴在東(パク・ジェドン)画伯
分断以来波乱と桎梏の韓国現代史の中には、各々志と情熱をつくして、より良い世の中、より正しい人生の道を探してきた「大物」らがとりわけ多い。 植民の圧迫と悲しみ、戦争の傷痕と離散の痛み、貧困と独裁、理念葛藤と南北対立、産業化と民主化、新自由主義と世界化に至るまで、時代の山々を押しのけて、一生を黙黙と、しかし熾烈に進歩に向かい、開かれた世の中のために、ひとつの道を歩いてきた各分野元老らの回顧談を『ハンギョレ』創刊20周年特集で連載する。低い声で語る彼らの話の中で、人生の知恵と次世代の道を共に訪ねて行くことを期待する。
1988年5月15日永登浦(ヨンドンポ)、梧木橋(オモッギョ)近くの楊坪洞(ヤンピョンドン)にあるバラック社屋の古い輪転機から流れて降りてくる『ハンギョレ新聞』を一抱え抱きかかえきて、2階の編集局に一気に駆け上がり、創刊祝いに集まってくれた客に新聞一部ずつを分け与えたその瞬間は、終生忘れることができない。その時私は52才、職責は編集者兼論説主幹。余生にどんなことが近づくかわからないが、その瞬間は私の人生の絶頂だった。だが七十に入った今、その時そこで味わった感激を繰返し口ずさむのはどうしても照れくさい。
1936年生まれの私は朴正煕(パク・チョンヒ)がクーデターを起こした1961年春、『朝鮮日報』見習記者として出発して、80年7月全斗煥(チョン・ドゥファン)一党がねつ造した、いわゆる「金大中内乱陰謀事件」の過度、内閣の名簿に名前が入っているという口実で『韓国日報』論説委員職を罷免されて、8年間就職不可レッテルが張られた「汚い」歳月を送った。
実際のところ職業人としての記者は一般的に大きなことを計画して成就するタイプとは距離が遠い。緻密な計算、確固たる決議そして粘り強い努力、三種類がみな足りないのだが、私もやはり例外ではないと信じる。分断された西ドイツの政治家の中で、左右を問わず識者層の幅広い信頼を受けた社民党(SPD)出身の総理ヘルムット・シュミットの「働き手(Macher)」とは全く違うタイプの人間が新聞記者だ。とにかくそのような私が『ハンギョレ』のようなとても風変わりな性格の新聞を作り出すという難しいことに没頭できることになろうとは夢にも思わなかった。「ペン一本を転がす人」、さらに率直に言えば「他の人より文章をよく書く能力の持ち主」くらいに自分自身を認識していたことは確かだ。少しひどく表現すれば、整えておいた食卓を前に置いて食べ物の味を恨むという悪い意味での書生あたりなのかもしれない。
編集路線と経営方式が既存新聞と全く違う新聞を作るという決心をすることになったことは誰が何と言っても6月抗争という時代的気勢に背中を押された結果だ。全斗煥軍事政権がすべての記事に「(記事を)出せ、出すな」「題名の大きさは1段、2段」という方式で報道機関に「報道指針」を下し、事前検閲を行う現実を国民皆が知った以上、新しい新聞の出現は避けられなかったのだ。単に誰がいつどのように作るのかということだけが問題であった。
87年1月「パク・ジョンチョル拷問致死事件」が、既存新聞に対する国民の不信と怒りを爆発させた代表的事例だ。 この渦中で「5・3仁川(インチョン)事態」で投獄中だった李富榮(イ・ブヨン)(75年『東亜日報』解雇、民統連事務局長、国会議員三選)が刑務所の中で特ダネをとったすごいいきさつも忘れてはいけない。彼は取材目的でそこに入ったのはないが、どんな状況でも不正の気配に感づいたら、我慢できないのが記者の魂だ。
75年朝鮮日報社と東亜日報社で解職された言論人ら、そして80年に全斗煥らによって、解雇された言論人らが主軸になって創設した「民主言論運動協議会」(議長は宋建鎬(ソン・ゴノ)、初代事務局は成裕普(ソン・ユボ)、略称「言協」。現在猛活躍中である「民主言論市民連帯」の前身)が地下機関紙の『マル(言葉)』を通じて、報道指針の内容を天下に知らせた。 彼によって「言協」二代事務局長金泰弘(キム・テホン)(80年『合同通信』解雇、『ハンギョレ』理事・販売局長、17代国会保健福祉委院長)と「言協」実行委員の愼洪範(シン・ホンボム)(75年『朝鮮日報』解職、『ハンギョレ』第二代目論説主幹)が拘束されて、6月抗争前後2~3ヶ月の間法廷闘争を行った。 これはフィリピンに続き韓国でも「民衆の力(ピープル パワー)」が現れることを予想した外国人記者らにとって、ソウルに来たときには省けない取材対象だった。 そんなわけで新しい新聞を作るというお荷物を解職記者らが担ぐのは誰も異議を唱えられない「時代の天命」だった。
次は「いつ」「どのように」であるが二つとも新聞を作るのに必要な資金を準備することと直結する問題であるから、解職記者らは色々な展望を口にするだけで確実な案を出すことができなかった。 その時存在感をあらわにしたのが鄭泰基(チョンテギ)(1975年『朝鮮日報』解雇、『ハンギョレ』常務理事と12代目代表理事)だ。国民募金とコンピュータ組み版というアイディアを出して押し進めることができたことは彼の創意と推進力のおかげだ。優れた存在は驚嘆と同時に時期の標的になるものだ。
鄭泰基は『朝鮮日報』を解雇された後、生計のためにいくつかのビジネスをしたがその最後の機会が小さいコンピュータ会社を経営するということだった。この時の経験を元にして、(新聞をつくる際に)鉛になった活字を家組(文選・組み版)するという過程をなくしてコンピュータで代行するという、当時としては革命的なアイディアを、『ハンギョレ』創刊を通じて実践するのに成功した。コロンブスが新大陸を「発見」したのか「到達」したのかについて、歴史家の間には紛々した議論があるが、どんな用語を使おうが私たちには重要ではない。87年秋、鉛になった活字を使わずに新聞を作るようになったことは、最小限の資金で新しい新聞を作らなければならない絶体絶命の必要性に直面した私たちには絶好の突破口であった。 すなわち必要は発明の母だ。
原文 https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/287602.html T.M