[レビュー]植民地史観と民族史観の間でロシア出身の韓国学者が著した古代伽耶史
博士学位論文をまとめ
『伽耶の準国家の歴史』出版
伽耶を通じて古代国家形成を研究

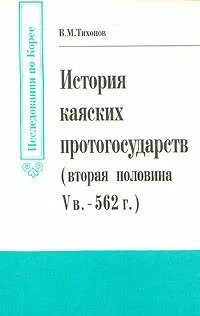
出版した年の順でみると、私の最初の著書は1998年に出た。発行場所はモスクワ、言語はロシア語、そして出版元はソ連時代からアジア関連の学術書籍を出し続けてきた「東洋学書籍出版社(Izdatel'stvo Vostochnaya Literatura)」だった。256ページのこの本は、私の博士学位論文をまとめたものだった。タイトルは『伽耶の準国家の歴史(5世紀後半~562年)』。おそらくいまだに、ロシア語だけでなくヨーロッパの言語で出版された唯一の伽耶史の研究書であろう。しかし、西欧や韓国の学界ではロシア語の堪能な人はそれほど多くないため、旧ソ連地域の学界ではたびたび引用されるものの、その外ではあまり知られていない本となった。
私が伽耶史に関心を抱いたのは大学の学部時代からだ。漢四郡とも日本列島とも交易を続け、広開土王の逆襲も百済の影響も受け、結局は新羅に吸収され、新羅の将軍である金庾信(キム・ユシン、595~673)や、その玄孫の易術家であり外交官である金巌(キム・アム、8世紀)らを輩出した新金氏の故郷である伽耶は、私の好奇心を刺激した。欧米圏やソ連では伽耶史の研究はほぼ皆無であり、日本の歴史学者の末松保和(1904~1992)が書いた『任那興亡史』(1949)は誰が見ても植民地主義的な歴史歪曲のにおいがした。同書の主張によると、「日本府」が4世紀中頃から任那、つまり伽耶を統治していたが、その時期には「日本」という名称そのものがまだ存在していなかったため、到底成立しえない話と思える。
しかし、私の師であるミハイル・パク(1918~2009)を一時痛烈に批判してもいた北朝鮮社会科学院の金錫亨(キム・ソクヒョン、1915~1996)院士が1963年に発表した、いわゆる「日本列島分国説」も、私としては納得し難かった。この学説によると、『日本書紀』にしばしば登場する「任那日本府」は、朝鮮半島出身者が日本列島内に建てた「分国」を管理するための機関であったが、私の見るところそのような分国の存在を考古学的に立証することは不可能であり、金錫亨の主張そのものは、日本の植民地史観に対する非常に過度な脱植民地主義的、民族主義的「対応」としての性格が強かった。植民地主義に対する「対応」という観点からは当然傾聴すべき話だったが、学術的な成立は困難な学説であった。私はそのため、植民地主義とも民族主義とも無関係な、「ひたすら史実」とマルクス主義的な国家成立論にもとづく伽耶史をひとつ書いてみようという野心から博士学位論文を書き、その後にその論文をこのように本にまとめた。
本書を貫く主な概念語は「準国家」だ。古代国家とは、中央権力が全社会の剰余に対してある程度の統制権を持つとともに、社会的資源を動員しうる階級的構造を意味する。伽耶の場合、慶尚南道咸安(ハマン)の阿羅伽耶(アラガヤ)や慶尚北道高霊(コリョン)の大伽耶(デガヤ)、慶尚南道金海(キムへ)の本伽耶(ポンガヤ)は「王」の称号を持つ最高支配者を持ち、戦争や外交の遂行能力を保有していたが、自国内の在地貴族や近隣の伽耶の小国たちの旱岐(首長)を制圧し、社会的剰余を収取する過程における優越的な地位を確立することはできなかった。比較すると、6部の首長たちを慶尚北道浦項冷水里(ポハン・ネンスリ)の新羅碑のような金石文によってすべて「王」と表記した、すなわち権力がまだ分散していた5世紀末~6世紀初めの新羅社会の性格と類似する側面が大きかった。ただし新羅とは異なり、国際貿易に非常に積極的だった伽耶の小国の諸勢力はその独自性が非常に強かったため、阿羅伽耶や大伽耶の君主たちはついにその統合と権力の中央化に失敗し、新羅に編入されるに至った。
私はこの最初の著書で、私の師ミハイル・パクの古代国家形成に関する研究を引き継いだつもりだ。ミハイル・パクは高句麗と新羅を中心に研究し、私はその研究を出発点として伽耶を扱った。しかし現在のロシアには、韓国古代政治・社会史の研究はほとんどない。このことが残念でならない。
訳D.K

