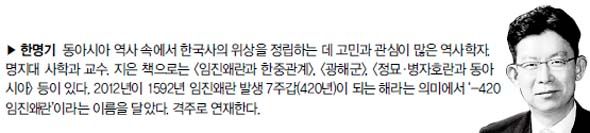原文入力:2012/02/17 22:22(4396字)
←1575年長篠の戦いの姿を描いた屏風図。 画面中央左側に鳥銃(火縄銃)部隊を配置した織田信長と徳川家康連合軍が障害物を設置した後、敵を凝視している。 中央右側の武田の兵力は騎馬隊が突撃する場面として描写されている。 鳥銃の威力が遺憾なく発揮されたこの戦闘を契機に織田は日本の覇権掌握に一歩近づいた。 その後、従来騎馬隊中心だった戦闘編成が鳥銃を持つ歩兵中心に変わることになった。 (東京徳川黎明会所蔵)、<図説 織田信長>2002,東京河出書房新社、72ページ)
ハン・ミョンギの -420 壬辰倭乱⑪戦争の火種(上)
壬辰倭乱は日本の朝鮮侵略であり明中心の東アジア既存秩序に対する挑戦だった。 既存秩序とは "天命を受けた明皇帝が‘四方の蛮夷’(四夷)を治め、蛮夷は皇帝に朝貢を捧げ事大する" という理念の下に維持されるシステムだった。 朝鮮はこの理念とシステムを忠実に尊重し、日本もまた15世紀中盤まではそのように順応する姿勢を見せていた。1404年室町幕府の将軍 足利義満が使節を明に送り、朝貢すると明皇帝は義満を‘日本国王’として冊封した。
揺れ動く政界…大名たちの内乱時代
日本が朝貢を通じて頭を下げて入ってくると明は勘合貿易を許諾した。 勘合とは朝貢しにきた者の真偽を確認するための信標を言う。 このようにして15世紀には遣明船と呼ばれる日本商船が明の寧波に入港し、生糸と絹織物、陶磁器などの中国物資が入ってきた。 文人と僧侶も往来した。 交隣の相手国朝鮮との貿易も栄えた。 朝鮮は米穀や木綿などの生活必需品だけでなく、高級文化商品である仏典や大蔵経も日本に渡した。 特に朝鮮から入った多量の木綿は日本人たちの衣生活に革新をもたらした。 木綿がなく主に麻で作った服を着なければならなかったそれまでの状況を変えたのだ。
だが、時間の経過と共に東アジア海域には激変の波が再び立ち始めた。 官僚制に土台を置いた中央集権体制が安定を維持していた朝鮮や明とは異なり、15世紀後半頃に日本の政界は揺れ動き始めた。 1467年以後、室町幕府の権威が深刻に動揺し各地域で群雄割拠と争闘が明確になる激動の時代になった。 以後100年近く続く戦国時代の幕が開かれたのだ。 天皇の存在感は消え、将軍の権威もまた地に墜ちた。 家臣が主君に立ち向かい、民は領主にさからい自立を企てる下剋上の風潮が威勢をふるった。 "強盗は武士の習い" ということわざが流行する中で戦国大名と呼ばれる有力勢力間の内乱が続いた。
弱肉強食の時代を迎えて軍事力と経済力を最高の価値とする大名にとって、過去に義満が受け入れた明中心の国際秩序に対する感覚や尊重の認識がまともに残っているわけはなかった。 結局、日本の内乱は朝鮮や明との関係にも大きな影響を及ぼすことになる。 すると朝鮮は1475年(成宗6年)以後、それまで日本幕府に送っていた使節の派遣を中断する。 内乱のためにはるかに危険になった日本に行くことを敬遠することになったのだ。 理由はともあれそれは非常に残念なことだった。 日本の動向や変化を探知できる機会がそれだけ減らざるをえなかったためだ。 李芸、宋希璟、申叔舟のように日本に精通した外交専門家たちが現れる土壌が消えつつあった。 長く平和に浸った朝鮮は日本に無関心になり始め、日本は内乱に陥り外を見て回る余裕がなかった。 そのような渦中にポルトガルとスペインに代表される西洋の勢力が東アジア海域に群がっていた。
天皇の存在感は消えうせ将軍の権威も地に墜ちて戦国時代の幕が上がった
15世紀ヨーロッパ大航海時代は日本に鳥銃を贈り
朝鮮は銀の製造術を渡し、明は交易の舞台を提供したので…
"鳥銃技術を外部に漏らせば死刑に処せ"
15世紀、ヨーロッパでは封建制度が力を失った。イベリア半島では国王権が強まり商人の発言権も高まるなかで国富を積みあげようとする気流が広がっていった。 このような雰囲気から当時までイスラムとイタリア商人が仲介していた東南アジアとインド産の香辛料を、現地へ行って直接取得しようとする熱望が高まった。 肉食を好むヨーロッパ人にとって防腐剤として重要なコショウをはじめとする香辛料貿易はその利益が莫大だった。 香辛料をリスボンに持ってくれば原産地の15倍以上の高値で売れた。
天文学と地理学、造船技術が発達し航海関連知識が蓄積されたことも一攫千金を夢見る者の冒険を煽った。 大西洋を西にずっと航海すればインドに到着するという信頼の下、コロンブスが航海に出たのが1492年だった。1498年にはポルトガルのパスコダガマがアフリカの喜望峰を回りインドに行く航路を切り開いた。 1521年ポルトガル人マゼランが率いるスペイン艦隊は南アメリカの南端を通過し太平洋を横断した後にフィリピンに到着した。 ついにいわゆる大航海時代が始まったのだ。
ポルトガルは以後、インドのゴア(Goa)に総督府を置き、アジア地域に対する貿易とカトリック布教に乗り出した。 彼らは1511年マラッカを占領し‘香辛料諸島’と呼ばれたマラッカ諸島まで勢力をのばした。 当時まで中国商人とイスラム商人が掌握していた海にポルトガル商人が割り込んできたのだった。彼らは再び明と日本に向かって東進することになる。
1543年シャム(タイ)を出発し明へ向かった中国船1隻が九州直下の種子島に漂着する事件が起きる。 そして、当時船に乗っていたポルトガル人が日本に最初に鳥銃を伝えたというのが通説だ。事実、鳥銃は中国で主に呼んだ名前であり、日本ではそれを鉄砲と呼んだ。
この新しい武器は戦国時代真っ盛りの日本社会に大きな波紋を及ぼす。鉄砲に最初に接した種子島の領主が家臣に模造品を作らせたのを始め、各地の大名が先を争い鉄砲の導入と製作に乗り出した。 一部では鉄砲やその製作技術を他の‘国家’に洩らした者は死刑に処するという規定を定め独占を試みた例もある。
←1575年長篠の戦いでの勝利を契機に戦国時代の最強者に浮上した織田信長。 1582年本能寺で部下の明智光秀に裏切られ49才で最期をむかえる。 (<図説 織田信長> 2002,東京河出書房新社、5ページ)
戦国時代の大名の中で鉄砲の製作と活用に最も積極的だった人物が織田信長であった。 彼は早くから鉄砲製作の中心地であった堺(今日の大阪周辺)地域を掌握し鉄砲部隊の育成に拍車を加えた。 1575年5月、織田の軍勢と武田勝頼の軍勢が正面対決した長篠戦闘は以後の日本政局の行方を決めるほど重要な戦いであった。織田はこの戦闘で早くから勇猛果敢に突撃戦を駆使した武田軍騎馬隊の突破を阻止するために陣地前方に木柵を設置した。 やがて武田軍が木柵に阻まれあわてる隙に後方に配置した鳥銃手3000人が射撃を加え彼らを制圧した。鉄甲で重武装した伝統の騎馬隊が鉄砲を持つ歩兵に無惨に倒れたのだ。‘鉄砲’と‘無鉄砲’の間に起きたこの殺風景な対決は15年後に朝鮮の戦場でもそのまま再現された。
スペインを跳び越えた新しい‘銀の国’
1503年(燕山君 9年) 5月の<燕山君日記>には銀の製錬と関連して次の記録が見える。 良人 金甘仏と掌隷院の奴婢 金倹同が鉛[鉛鉄]から銀を吹き分けることを「鉛1斤(600g)から銀2トン(7.5g)ができます…吹き分ける方法は銑鉄火鉢や鍋の中に猛灰を並べて鉛を細かく砕き満たした後、割れた素焼きの土器で四方を覆い、おこした炭で上下から溶かします」と言うので、言われたとおりに“試してみよ”と言った。
当時、先端銀製錬術だった鉛銀分離法が朝鮮で開発され活用されていたことを示す重要な資料だ。ところで灰吹法とも呼ばれたこの技術は朝鮮よりも日本で花を咲かせることになる。 朝鮮に出入りしていた日本商人によってまもなく日本へ流出したのだ。
灰吹法が導入される以前の日本の銀製錬技術は原始的な水準を抜け出せなかった。採掘した銀鉱石を積み上げ、5日以上 木を燃やし加熱した後、酸化されて残った灰から銀を抽出する水準だった。製錬にかかる費用に比べ経済性がまったく思わしくなかった。 ところが灰吹法導入を契機に1530年代以後、日本の銀生産量は飛躍的に増加した。各地で銀鉱開発ブームが起きた。 富国強兵のための財源作りに苦心していた大名は銀鉱山開発に熱中した。 日本は16世紀中盤にはスペインが開発した南米地域の銀生産量に次ぐ‘銀の国’として登場する。 そして17世紀始めには日本の銀は全世界生産量の4分の1以上を占めることになる。
銀は当時 国際交易の決済代金であり‘世界の貨幣’であった。あふれ出た日本の銀は交易の利益がある所に向かって集まる一方だった。それは他でもない中国の江南地方だった。シルクと生糸、陶磁器など世界中の人が好む商品の主産地であった。 だが、交易ははかばかしくなかった。 明が設けた海禁という障壁のためだった。 かつて明の朱元璋は朝貢を捧げる国家だけに勘合貿易を許容しただけで、民間人どうしの蜜交易は厳格に禁止していた。 “板子一枚といえども海に持ち出すことはできない”という言葉が象徴するように民間人は海外渡航と貿易は不可能だった。
だが、交易の利益を権力で統制することには限界がある。銀という貨幣を手に入れた日本商人は江南商人らと密貿易を行ったり武装船団を率いて明の東南沿海地域を略奪した。 これらを普通‘16世紀倭寇’、‘後期倭寇’と呼ぶ。これらの中には中国人も多数混ざっていた。 浙江と福建沿海の豪族は公然と倭寇と取り引きを行い、倭寇の親分として名をはせた中国人も少なくなかった。 このような状況で明朝廷は倭寇を根絶できなかった。 実際、1547年に倭寇禁圧の命を受けて浙江巡撫に赴任したチュファン(朱紈)は倭寇と手を結んだ地方豪族の讒訴にまきこまれ自殺してしまう。
要するに16世紀初期の大航海時代が東アジア、特に日本に追い立てた波紋は大きかった。 新武器である鳥銃は、既に長期にわたる内戦を通じて鍛練された日本の軍事力を画期的に増強させた。そしてこの頃、銀の生産量が画期的に増えたのは日本の経済力が大きく向上したことを象徴する指標であった。 このような状況の中で織田信長を経て豊臣秀吉に至り全国が統一されるや、凝縮された日本の力は明と朝鮮をねらうことになる。 壬辰倭乱はまさにその帰結だった。
↑ ハン・ミョンギ 東アジア歴史の中から韓国史の位相を定立することに熟慮と関心が多い歴史学者。明知大史学科教授。著書には「壬辰倭乱と韓中関係」「光海君」丁卯・丙子胡乱と東アジア」などがある。2012年が1592年の壬辰倭乱勃発7周甲(420年)になる年という意味で「-420 壬辰倭乱」と名づけた。隔週で連載する。
原文: https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/519636.html 訳J.S