пј»жӣёи©•пјҪжқұжҙӢдәәгҒҜгҒ„гҒӢгҒ«й»„иүІдәәзЁ®гҒ«гҒ•гӮҢгҒҹгҒӢ
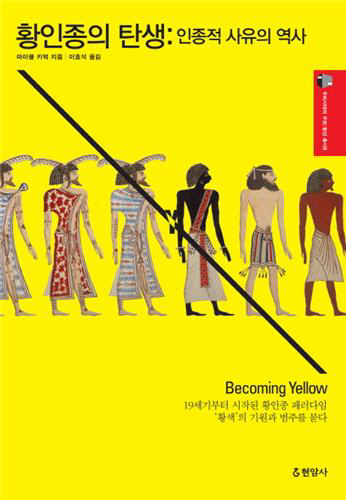
гҖҖгғһгғ«гӮігғ»гғқгғјгғӯгҒҢеҸЈиҝ°гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢжқұж–№иҰӢиҒһйҢІгҖҚгҒ§дёӯеӣҪдәәгҒҜгҖҢзҷҪдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжҸҸеҶҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ18дё–зҙҖгҒ®е®Јж•ҷеё«гҒҹгҒЎгҒҢж®ӢгҒ—гҒҹиЁҳйҢІгҒ«гӮӮгҖҒж—Ҙжң¬дәәгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢжқұгӮўгӮёгӮўдәәгҒ®зҡ®иҶҡгҒҜзўәгҒӢгҒ«зҷҪгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢ19дё–зҙҖгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒгҒІгҒЈгҒқгӮҠгҒЁгҖҢй»„иүІ(yellow)гҖҚгҒ«еҸ–гҒЈгҒҰд»ЈгӮҸгӮүгӮҢгӮӢгҖӮж—…иЎҢиЁҳгҖҒ科еӯҰи«–ж–ҮгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиҠёиЎ“дҪңе“ҒгҒ§гӮӮжқұгӮўгӮёгӮўдәәгҒҜй»„иүІгҒ„иӮҢгӮ’жҢҒгҒӨдәәгҖ…гҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒӢгӮҢе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгҒқгҒ®й–“гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„дҪ•гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
гҖҖгғһгӮӨгӮұгғ«гғ»гӮӯгғјгғҗгӮҜеӣҪз«ӢеҸ°ж№ҫеӨ§ж•ҷжҺҲ(54)гҒҜ2011е№ҙгҒ«еҮәзүҲгҒ—гҒҹи‘—жӣёгҖҢй»„иүІдәәзЁ®гҒ®иӘ•з”ҹгғјдәәзЁ®зҡ„жҖқжғҹгҒ®жӯҙеҸІгҖҚгҒ§гҖҒдёҖжҷӮгҒҜгҖҢзҷҪдәәгҖҚгҒ гҒЈгҒҹжқұгӮўгӮёгӮўгҒ®дәәгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«гҖҢй»„дәәгҖҚгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгҖҒгҒқгҒ®ж·өжәҗгҒЁжқҘжӯҙгӮ’зІҳгӮҠеј·гҒҸжҺўгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ
гҖҖжқұгӮўгӮёгӮўдәәгҒ®йЎ”гҒ«й»„иүІгҒ®гғ¬гғғгғҶгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҹжңҖеҲқгҒ®вҖңе®№з–‘иҖ…вҖқгҒҜгҖҒгҒӢгҒ®гӮ«гғјгғ«гғ»гғ•гӮ©гғігғ»гғӘгғігғҚ(1707~78)гҒ гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгғӘгғігғҚгҒҜгӮўгӮёгӮўдәәгҒ®иӮҢгҒ®иүІгӮ’жҡ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ®гғ©гғҶгғіиӘһгҖҢгғ•гӮ№гӮҜгӮ№(fuscus)гҖҚгҒЁиЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ1758~9е№ҙгҒ«еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢиҮӘ然гҒ®дҪ“зі»гҖҚ第10зүҲгҒ§гҒҜгҖҢгғ«гғӘгғүгӮ№гҖҚ(luridusгҖҒжҹ”гӮүгҒӢгҒ„иүІгҖҒйқ’зҷҪгҒ„)гҒЁе…·дҪ“еҢ–гҒ—гҒҹгҖӮгғӘгғігғҚгҒҢеЎ—гҒЈгҒҹиүІгӮ’и¶…гҒҲгҖҢгғўгғігӮҙгғӘгӮўгғҚгӮ№(mongolianness)гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе…ЁгҒҸйҒ•гҒҶж¬Ўе…ғгҒ®зғҷеҚ°гӮ’жҠјгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгғЁгғҸгғігғ»гғ•гғӘгғјгғүгғӘгғ’гғ»гғ–гғ«гғјгғЎгғігғҗгғғгғҸ(1752~1840)гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
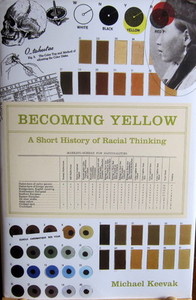
гҖҖжҜ”ијғи§Јеү–еӯҰгҒ®еүөе§ӢиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгҒ“гҒ®гғүгӮӨгғ„гҒ®еӢ•зү©еӯҰиҖ…гҒҜгҖҒжқұгӮўгӮёгӮўдәәгҒ®иӮҢгҒ®иүІгӮ’гҖҢжө…гҒ„й»„иүІ(gilvus)гҖҚгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒӢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«иёҸгҒҝиҫјгӮҖгҖӮгғЁгғјгғӯгғғгғ‘дәәгҒ«гҒЁгӮҠдёҚеҗүгҖҒи„…еЁҒгҒЁгҒӘгӮӢеҚҳиӘһгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгӮўгғғгғҶгӮЈгғ©гҖҒгӮёгғігӮ®гӮ№гӮ«гғігҖҒгғҒгғ гғјгғ«гӮ’йҖЈжғігҒ•гҒӣгӮӢгҖҢгғўгғігӮҙгғ«гҖҚгӮ’еј•гҒЈејөгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ гҖӮжңҖеҲқгҒҜдёҚж…ЈгӮҢгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжқұгӮўгӮёгӮўгӮ’иЁӘгӮҢгҒҹж—…иЎҢиҖ…гҒҢзҸҫең°дәәгӮ’й»„дәәгҒЁзӨәгҒҷдәӢдҫӢгҒҢеҫҗгҖ…гҒ«еў—гҒҲгҖҒгҖҢй»„иүІдәәзЁ®гҒҜ19дё–зҙҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдәәйЎһеӯҰгҒ®ж ёеҝғиҰҒзҙ гҒ«дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖҚгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒй»„иүІгҒ®зғҷеҚ°гҒ«гҒҜе·®еҲҘгҖҒжҺ’д»–гҖҒжҡҙеҠӣгҒҢеҮқзё®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдё–гҒ®дёӯгҒ«зҙ”зІӢгҒӘзҙ”й»’дәәгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒҫгҒЈй»„иүІгҒӘдәәгӮӮгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгғЁгғјгғӯгғғгғ‘дәәгҒҜиӮҢгҒ®иүІгӮ’вҖңеүөйҖ вҖқгҒ—гҖҒгғўгғігӮҙгғ«зӣ®гҖҒи’ҷеҸӨж–‘гҖҒи’ҷеҸӨз—Ү(гғҖгӮҰгғіз—ҮеҖҷзҫӨ)гӮ’ж–°гҒҹгҒ«вҖңзҷәжҳҺвҖқгҒ—гҒҰгҖҒй»„иүІдәәзЁ®гӮ’йқһжӯЈеёёгҒ®д»ЈеҗҚи©һгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгӮўгӮёгӮўгҒӢгӮү移民гҒҢж®әеҲ°гҒҷгӮӢгҒЁдәәеҸЈйҒҺеү°гҖҒз•°ж•ҷгҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒӘ競дәүгҖҒж”ҝжІ»зӨҫдјҡзҡ„гҒӘдҪҺдёӢгҒӘгҒ©гҖҒгҒӮгӮҠгҒЁгҒӮгӮүгӮҶгӮӢеҗҰе®ҡзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігӮ’еҗ«и“„гҒҷгӮӢгҖҢй»„еҢ–(yellow peril)гҖҚгҒ®иӯҰе ұгҒЁгҒ—гҒҰеҜҫеҝңгҒ—гҒҹгҒ®гӮӮеҪјгӮүгҒ гҖӮзҷҪдәәгҒ®дёӢгҒ«й»„дәәгҒЁй»’дәәгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгӮӢгҖҢйҡҺзҙҡ秩еәҸгҖҚгҒҢиӘ°гҒ®еҲ©зӣҠгҒ«её°зөҗгҒҷгӮӢгҒӢеҲӨж–ӯгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®гҖҢдәәзЁ®зҡ„зҗҶеҝөи«–гҖҚгҒ®йҡ гӮҢгҒҹж„ҸеӣігҒҢйҖҸгҒ‘гҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖи‘—иҖ…гҒҜйҹ“еӣҪиӘһзүҲгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жӣёгҒ„гҒҹеәҸж–ҮгҒ§гҒ“гҒҶиЁҳгҒҷгҖӮгҖҢй»„иүІгҒЁгҒ„гҒҶе·®еҲҘзҡ„(дёӯз•Ҙ)еҚҳиӘһгӮ’гӮӮгҒҜгӮ„дҪҝгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„жҷӮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҖӮ348гғҡгғјгӮёгҒ®жң¬гҒ®3еҲҶгҒ®1гӮ’еҚ гӮҒгӮӢе°ҫжіЁгҒЁеҸӮиҖғж–ҮзҢ®гҒҢеҪјгҒ®дё»ејөгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
йҹ“еӣҪиӘһеҺҹж–Үе…ҘеҠӣпјҡ2016-07-21 19:58